
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
ゆとり世代には「ビニールハウス症候群」の傾向があります。環境の良い、暖かいビニールハウスの中で、ぬくぬくと育ちたいと考える人たちのことです。きれいなオフィスで、おしゃれなデスクに座って最新型のパソコンを与えられる。そういう、いたれりつくせりの環境で働きたいという、まさに環境依存・他責型人間の典型です。こうした人間は、逆境や困難に直面したとき、すぐに心が折れたり、逃げたりしてしまいます。
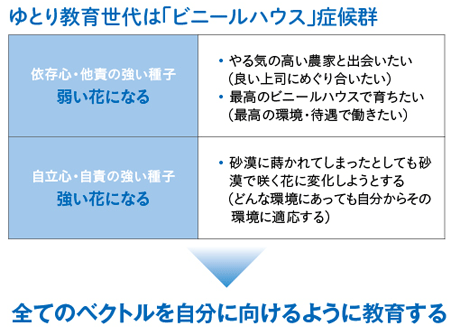
例えば、自分がひまわりの種だとして、砂漠にまかれたらどうなるでしょうか?「すみません、僕はひまわりなんで、砂漠じゃ育たないんですけど」と言うのが環境依存・他責型人間です。「砂漠でも育つように自分が変わればいいじゃないか」。この考え方を彼らに持たせることができれば、ビジネス社会に適応できるようになります。
会社に入って1年目、仕事がなかなかうまくいかないという経験は、上司世代を含めてみんながしています。社会に出れば、自分が思っていたよりうまくいかないことのほうが多かったはずです。これまでの世代は、集団の中で誰がうまくいって、誰が失敗したかを知らされてきました。相対的に誰が上手で誰が下手かということを、さまざまな局面で知らされ、経験してきました。
その経験の中で「あいつは成功したがオレは失敗した」というちょっとした屈辱の経験を積み重ねていますから、失敗に対する免疫力を大学生までの22年間で少しずつ身に付けてきています。ところがゆとり世代は、絶対評価の中で「昨日はできなかったが、今日はできた」という自分自身だけのことにしか向き合っていません。集団の中で、自分が上手か下手かという立ち位置の把握をしないまま、社会に出てきました。
極端な話、人生23年目で初めて「(職場という)集団の中で、自分だけがうまくいかないという状況」に直面するわけです。上司や先輩は自分たちも同じように、新入社員時代に失敗した経験をしていきていますから、「そんなものだろう」「できると思ってたわけじゃあないよね」と軽く言います。しかし、ゆとり世代の心の折れ方は尋常ではありません。それでみんな、「なんでだ?」と首をかしげてしまいます。
たとえていえば、ゆとり世代は無菌の水槽で育った魚を、汚い海にいきなり放したようなものです。上司世代はもともと、ある程度汚い川で育ち、その延長線上の海に出た。「うわぁ、いろんなのがいるなぁ」という感じです。汚い水の中での暮らし方は分かっています。これに対して、ゆとり世代は水槽で育ってきましたから、汚い水自体に面食らっています。海で出会うさまざまな困難をどうやって乗り越え、生きていけばいいのかが分からないのです。
大切なのは、「仕事がうまくいかなかったときに、何をしなければいけないのか」というパターンをしっかりと教えておくことです。仕事がうまくいかなかったとき放っておけば、ゆとり世代は責任を自分以外に求める「他責」に進んでいきます。
「上司が毎日面倒をみてくれないから、育たないし、やる気も出ません」
「やる気を上げてくれる上司と一緒に仕事がしたいです」
「自分のやる気が下がるような人は悪い人で、嫌な人です」
こんな「他責」の考え方を持ちやすいゆとり世代に、まずは自分の力で対応し、変わっていく「自責サイクル」の考え方を植え付けましょう。
自責サイクルとは、
仕事がうまくいかないのは、自分に責任がある
↓
反省し、失敗の原因を検証・分析して改善していかなければならない
↓
しかし、それを一人でやるのは(新入社員だから)難しい
↓
上司や先輩からアドバイスを受けることが大切
↓
職場での人間関係を良好にする
という流れです。この自責サイクルをうまく回していくには、周囲の人間関係が大切であると教える必要があります。
なにぶん、自責サイクルを回した経験がありませんから、本人一人だけではすぐに行き詰まってしまいます。仕事で「うまくいかないこと」が起きたときに、上司や先輩からのアドバイスを受けたり、同世代の社員からアドバイスを受けたり、と周囲の人間の力をうまく使うように仕向けてください。仕事がうまくいき、上司からほめられれば、何も問題はありません。しかし、新入社員であればだいたい10回のうち、うまくいくのは1回、うまくいかないことが9回とほとんどでしょう。
うまくいかないときに指導されたり、怒られたりすると、「他責」の考えの社員は気持ちが落ち込んだりやる気を失ったりして、マイナスのスパイラルに陥っていきます。よくても開き直って何も改善しないか、最悪の場合は「自分にはこの会社は合っていない」と辞めてしまいます。
しかし、「自責」の考え方を持っていれば、指導されたり、怒られたりしたときに「何が間違っていたのか」を反省し、検証・分析して改善策を考えることができます。その改善策を実行し、もしうまくいかなかった場合でも、「自責」の考えに基づいてもう一度、検証・分析・改善・行動のサイクルに入っていくことができます。
入社3年以内に辞める社員の多くは、この「他責」からマイナスのスパイラルに陥っています。「自責」の考え方を身に付けさせることによって、企業の戦力になるだけでなく、社員自身の能力を継続して高めていけるのです。ただ、自責を伝えると、「能力がない」などと自分を責め過ぎることがあります。「自虐も他責である」と教えるのも大切です。
ゆとり世代の新入社員は「野球がうまくなりたい!」と、野球部に入り、バットとボールを初めて持った少年のようなものです。意欲はあるが、やってみてもいきなりうまくはいきません。そこで監督やコーチに「お前、ヘタだなぁ」と怒られ、ヘコんでしまいます。このとき、「ぼくは野球に向いていない。辞めよう」と思わせないためには、監督やコーチとの人間関係、先輩部員との人間関係が大切です。
先輩部員との間に、相談できるほどの親しい関係があれば、教えてもらって、徐々に上手になっていきます。「教えてください」と言える相手がいなければ、いつまでたっても上達しません。
ちょっと思い出してみましょう。下手でも、その運動部にずっといる部員っていますよね? それはたいてい、監督や先輩に好かれている部員です。逆にすごく上手なのに、運動部を辞めてしまう部員はたいてい、監督や先輩ともめ事を起こしています。会社も同じです。人間関係が良好なら教えてもらうことができる。これは、自責サイクルを回すために必要なだけでなく、後述する4つ目の心構え「教えられ上手を目指せ」にもつながってきます。
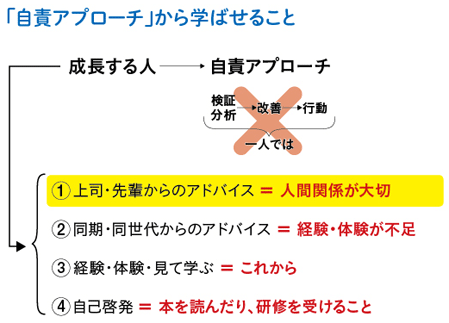
私は新入社員研修から始め、3年目くらいまでのフォローアップ研修をすることがよくあります。その中で、先日ある入社3年目の社員の性格分析をしたところ、やる気がものすごく下がって、ぼろぼろの状態になっていました。お酒を飲みながら話を聞いたところ、今の上司ととにかく合わないらしいと分かりました。
そこでこう言ったんです。「もしかしたら上司が悪いかもしれないが、君が上司を怒らせた原因をつくっているかもしれないよ?」「合わないと決めつけず、もう一度反省すべきところを反省し、検証して次につなげれば、君自身が成長するよ」と。ゆとり世代はきちんと説明すればしっかりと理解し、実行します。彼も「分かりました」と努力するのを約束してくれました。「自責」の考え方によって、こうした人間関係などの面でも、彼らの成長を促すことができます。
執筆=柘植 智幸(じんざい社)
1977年大阪生まれ。専門学校卒業後、自分の就職活動の失敗などから、大学での就職支援、企業での人財育成事業に取り組む。就職ガイダンス、企業研修、コンサルテーションを実施。組織活性化のコンサルティングや社員教育において、新しい視点・発想を取り入れ、人を様々な人財に変化させる手法を開発し、教育のニューリーダーとして注目を集めている。さらに、シンクタンクなどでの講演実績も多数あり、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、経済界、日経ベンチャーなど多数のメディアにも掲載される。
【T】
“ゆとり君”と働くために覚悟しておくこと