
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
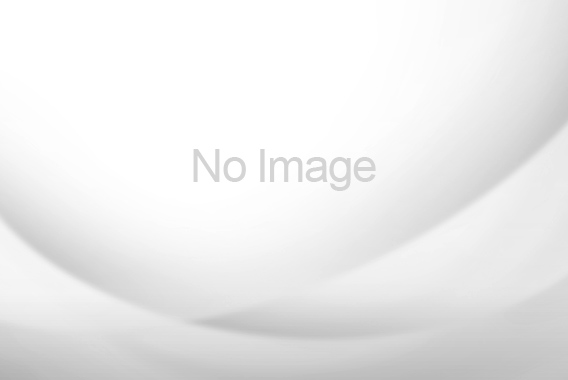
私が初めて「安全率」を学習し、実際の設計の演習でその掛け算を行ったのは大学3年の機械設計演習のときだったと思います。「安全率」とは計算上、物が壊れるときの負荷を、予測される最大負荷で割った比率です。
例えば、考えられる最大負荷が1のとき、設計はその負荷を倍の2と仮定してちょうど壊れないぎりぎりの寸法を決めてやると、安全率は2です。学生のときは言われるがままに整数3(だったと思います)を想定される最大負荷に掛けて、模範解答と同じ数字を導き出したのですが、違和感があったと覚えています。
今ではその違和感を説明できます。有効数字3桁の材料の降伏点(降伏点とは、負荷がなくなったときに元に戻れないほどの変形を材料に与える最小の負荷)と部材にかかる最大負荷、それにいくらでも正確に計算できる材料の断面積から部材の寸法を計算するにあたって、想定される部材に作用する最大負荷に、3.01でもなく、2.9でもない、3という有効桁数1の数字を掛けるのが違和感の元でした。この安全率について、みなさんと一緒に考
えてみたいと思います。
私は5月5日と聞くと、忘れられない事故を思い出します。2007年のこの日、大阪万博跡地にできたエキスポランドで、走行中の6両編成立ち乗りジェットコースター「風神」の1両から、4つある片側抱え込み式の車軸ブロック固定端で車軸が折れ、端部はナットと共に落下。しばらくはそのまま走行を続けましたが、終点まで200メートル余りのところで車軸がついにすっぽり抜け、車軸ブロック全体が落下。4つある支えの1つをなくした車体は大きく傾き、ジェットコースター走行レールの隣に並行していた保守通路の手すりに、乗客の1人が頭部を強打して即死しました。
捜査を担当した大阪府警は、写真付きで車軸の折れた部分を公開し、金属疲労によって発生した傷が徐々に進行したと説明しました。エキスポランドでは、「風神雷神II」(それぞれ6両編成の風神と雷神が交互に走行するのでこの名前になりました)を設置してからこの事故までの15年間、車軸を交換しておらず探傷検査も簡単な目視で済ませていました。最も大きな問題はこの保守の手抜きですが、もともとの設計も怪しいと失敗学会が発行する「失敗年鑑」に説明しました(注1)。
日常では体験できないようなスリル感が面白く、人はジェットコースターに乗るのですが、いつの頃からか3次元空間を複雑なねじり回転や360度以上の回転を交えながら、人を楽しませるようになりました。
しかし、そのような動きを2本の曲線レールを抱え込んだ状態で、何両も連なった列車が高速走行する場合を考えてみます。どんなに精度良くレールを設置しても、その2本をピッタリ抱え込んだ状態で車両が走るのは無理で、製作誤差から来るガタが残りますから、車両の車輪はその誤差を吸収する構造になっていなければなりません。
また、鉄の熱膨張率を考えれば、30度はある夏と冬の寒暖差では、100メートルを超えるレールの空中軌跡はセンチ単位でずれていると分かります。事実、大阪府警が発表した写真を見ると、車輪はレールの上で5センチほどの横滑りを常に起こしていました。
つまりジェットコースターは空中を滑らかに滑走するのではなく、車輪にガタガタと非常に負荷をかけながら、あの動きを実現していると思わなければなりません。近くを通るジェットコースターから発生する機械音がとても大きいのは、これから乗ろうとする人の恐怖感をあおる効果もあるのですが、構造的にそのような音が出ているのです。
このように過酷な条件下で使用している機械ですから、普通に動的荷重の安全率を掛けてはいけないのです。単純な負荷の中でも過酷な、引っ張りと圧縮を繰り返す「両振り繰返し荷重」の安全率、8を掛けるべきでしょう。
2011年のアメリカ機械工学会の設計工学国際大会では、エンターテインメント工学というパネルセッションが行われました。講演を行ったウォルト・ディズニー・イマジニアリング、マクラーレン・エンジニアリング・グループどちらの工学者も、いくつかの問いに対して、口をそろえて安全率は10と言っていました。彼らは両振り繰り返し荷重の8よりもさらに大きな安全率を当たり前に使用しているのです。
ウォルト・ディズニー・イマジニアリングは社名から察しが付くように、ディズニーランドのアトラクションを設計している会社であり、マクラーレン・エンジニアリング・グループは、あのF1レースのコンストラクターのエンジニアリング部門ではなく、世界屈指のエンターテインメント集団「シルク・ド・ソレイユ」のステージなどを手がける会社です。
シルク・ド・ソレイユのステージは、世界中を巡業する一時舞台物もすごいのですが、ラスベガスの固定シアターでの常設ショーの迫力はずばぬけています。その中でも度肝を抜く仕掛けが、重量が150トンを超える砂のメインステージを使った壮大なショー、「カー(KA)」です。このステージは7.6×18メートルあり、3次元空間を回転しながら立ち上がり、最高点は20メートルを越す高さになります。
航空機工学の安全率は、1.5といわれています。ただし、すべてが1.5ではなく、部材や不確定性により違う数値を使っています(注2)。この小さな安全率を実現しているのは、飛行ごとに行われる点検をはじめ、飛行距離や時間に応じた定期点検や整備、飛行中も行っているモニタリングです。
2018年10月から2019年3月にかけて起こったボーイング737MAXの事故は急上昇を防ぐ目的で開発された新規制御システムの不具合によるもので、これは安全率が問題ではありませんでした。むしろテスト回数が少なすぎたのでしょう。
航空機事故は、原因を調べると意外に多いのが操縦ミス、コミュニケーションミス、修理ミスなどで、この他にも衝突、意図した爆破、意図しなかったバッテリーからの発火などさまざまなものがあります。私たちの脳裏に残る御巣鷹山事故は、修理ミスの末に進展した金属疲労による亀裂が原因でした。安全率というよりは、修理ミスと不具合を発見できなかった保守のミスでした。
安全率を負荷に乗じる理由について、目に見えない材料の欠陥、寸法の不確かさ、予想を超えた負荷の作用など、いろいろ言われますが、大きな理由は、設計者の予測能力の不確実性だろうと思います。ですからそのようなものを定量するにあたって、3.2などと有効桁数2桁の値に定めても無意味で、やはり1桁の値しか割り当てられません。
しかし、安全率が1桁なのだから最大負荷の計算を1桁でやればいいというわけではありません。設計計算はあくまでも科学的に行うべきです。確立された式の変数に与えられた数字を漫然と入れて行うのは学生までであり、プロになれば式の意味を理解し、考えながら行うものです。
これにより設計者は勘を鍛え、やがて機械を見ただけでどこが壊れそうだとか、この部材は細すぎるなどと分かるようになります。安全率が大きい産業は安心度も高いと思うのは間違いです。大きな安全率は、設計者の予測能力が現実よりも小さい表れであると意識する必要があります。
(注1) 失敗年鑑2007「エキスポランド、ジェットコースター事故」飯野謙次
(注2) 構造試験、航空実用事典、日本航空
執筆=飯野 謙次
東京大学、環境安全研究センター、特任研究員。NPO失敗学会、副理事長・事務局長。1959年大阪生まれ。1982年、東京大学工学部産業機械工学科卒業、1984年 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了、1992年 Stanford University 機械工学・情報工学博士号取得。
【T】
経営に生かす「失敗学」