
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
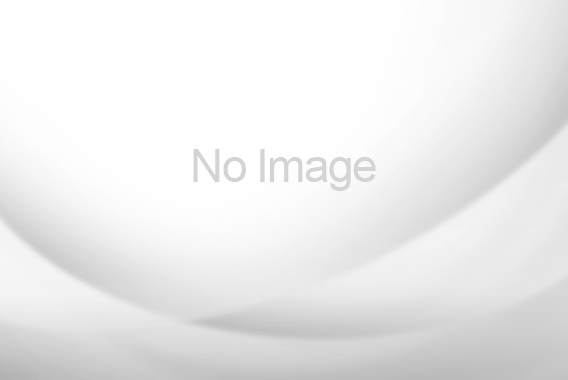
アメリカのプレゼンテーションは、最初に気の利いたジョークで笑いをとることがよくあります。私は工学者なので、工学系の学会や講演会に参列する場合が多いのですが、皆芸人ではないので、そうそうウイットに富んだ小話が即興で出るわけではありません。プレゼンテーションを練習するとともに、ジョークを一生懸命に考えるのです。
あるアメリカ機械工学会の国際大会で、中国人女性がプレゼンテーションの冒頭にジョークで笑いを取りました。いわく「ヨーロッパは伝統に押しつぶされて弱まり、日本は業務の煩雑さで競争力をなくし、アメリカはお互いを訴訟し合うことに忙殺される。これからは中国の時代だ」。
アメリカでのプレゼンテーションだったので、パンチラインは、訴訟社会のアメリカを皮肉ったところですが、参加者は大いに笑わせてもらいました。しかし私たちは、日本の業務の煩雑さが、ジョークになるくらい国際社会に知れ渡っている点に、危機感を覚えるべきです。
1998年12月施行の特定非営利活動促進法(注1)の波に乗り、失敗学会はNPO(非営利組織)としてスタートしました。ネットの情報を頼りに設立準備会を開催したのが2002年5月21日。それから半年かけて、ようやく東京都に設立が承認されたのが11月の終わりでした(注2)。
当時設立に奔走した私は、ネットで開示されていたNPO定款のひな型はあくまでも参考のものであり、自分たちの事情に合わせて適宜記述を変更したうえで設立を申請するものだと思いました。特に総会の表決では、法人、個人の会員が「書面をもって表決」とあったのを、電子的に表決できるように文面を変えて申請しました。これが東京都の承認に引っかかりました。
当時、封書は80円。送信と返信に160円はかかります。個人・法人を合わせて1000人近かった会員とこのやり取りを行うだけで、10万円は軽く超えます。私たちが送った封書を手にすれば、誰でも返信できてしまうのに対し、ネットにはログインの仕組みを作ってあるので、より確実だと説明しても受け入れられず、ついには当時カタカナが残っていた民法まで持ち出されて面食らいました。
公開されているひな型は、名称と住所、目的と事業内容のみを変えるだけで、ほかはその通りに使用するものだとこのとき学習しました。先ごろの改正でも、指導された通りの文面に定款を変更してことなく終えました。しかし、予算が限られたNPOでは、収入もない総会にそんなにコストをかけられません。2年目は料金別納のバーコードを会員ページに作成し、会員に印刷をお願いしてコストを半減しました。
しかし、これが面倒だったのでしょう。総会が成立するための正会員過半数の表決をかき集めるのに苦労しました。その翌年はネットでの表決を、事務局で印刷して書面にすることに同意していただき解決しました。ただし、本当に1表決を1枚のA4紙に印刷するので、資源の無駄です。さらに会員資格の更新が遅れれば、資格を一時的に失効させ、真剣に継続を希望する会員に絞って表決者の過半数達成をしやすくしました。全国のNPOは同じ仕組みに従って活動をしなければならないのです。
失敗学会を立ち上げた頃、20数年ぶりに日本に出張ベースで戻っては仕事をしていました。当時、理屈が通れば業務を合理的に進めるのは問題なく認められるものと思っていました。あるとき、その出張がお正月時期に重なり、ピークを避けて航空券を購入すれば、値段が3分の1程度で済むと分かりました。日本で待機中はホテルではなく、実家に滞在して食事代の日当も不要として申請したところ、これが通らないのです。来日は仕事の直前、仕事が終わればさっさと帰らなければならないとのことでした。出費が3倍になっても、そうしなければ国民が納得しないとの理由でした。
私たちの社会は他国に比べてスピードは遅いものの、確実に進化を遂げているのは、前例がなくてもどこかで物事を進める力が働いているからでしょう。例えば、2021年に開催された東京オリンピックのネットからのチケットの購入申し込みシステムは、1998年の長野オリンピックのときにはありませんでした。使ってみると分かりづらく、一方的に「気が変わって第2希望の申し込みの競技を変えると、第1希望の申し込みが消えるかもしれない」というなんとも歯がゆい警告メッセージに悩まされました。
このように問題があっても、新しいことに挑戦し、失敗を経験してより良い解決法を見つけなければ世界に取り残されてしまいます。役所や企業の業務も、慎重であっても構いませんが、前例がないからといって業務改善の扉を閉ざしてしまうのではなく、効率的な進め方を考えてほしいものです。
日本にはさまざまな職種の職人がたくさんいます。そして、職人が世に送り出したものには敬意を払い、時には恐れおののいてしまうのが一般人です。神戸市の竹中大工道具館を訪れたとき、大工の棟梁(とうりょう)が出すカンナの削りくず(削り華)は、厚さ3ミクロンと聞かされ驚きました。3ミクロンなのだから、300枚集めて押しつぶしても1ミリに満たない薄さです。カンナを引いて使うのは日本だけと、そのとき館長さんに聞かされました。カンナの刃を自分で砥(と)ぐ日本の大工さんのまねは外国ではできないそうです。だから、なまった刃に力を入れられるよう、押して使うのです。
このような職人への敬意ならよいのですが、時にはそれが権威への過信となってしまい、とんでもない間違いを起こすときがあります。例えば、単一飛行機の事故としては最悪の、520人の死者を出した御巣鷹山ジャンボ機墜落事故があります。墜落事故が起こった7年前の尻もち事故で損傷した圧力隔壁は、製造社が修理を行ったのですが、その修理が不適切でした。それこそが墜落事故の原因であると知られています(注3)。
修理契約では、「新造機と同じ部材と結合方法」とされていたのに、製造社が調達した部材の寸法が足りずに、壊れた隔壁から部材を切り出して継ぎ足しました(注4)。しかも、新造機にはない第3のリベット(金属板を締結する部品)列が1メートルにわたって明らかに見えていたはずです。
当時、修理の納品検査がなかったとは考えられません。明らかに契約とは違う修理がなされたのにそのまま受け取ったのは、製造社に対する信頼か、それとも見ずに受け取ったのかは分かりません。ひな型、前例、権威を重んじることはすべて形を重視した日本の文化のたまものです。形を軽視すべきといっているのではありません。伝統文化や芸能は、形にこだわらなければ意味がありません。しかし、企業が諸外国と競争をするのは伝統芸能ではなく、効率と先駆性です。そこで形にとらわれていては負けてしまいます。業務の効率化を避けてはいけないのです。
注1:e-Gov電子政府の総合窓口、特定非営利活動促進法
注2:2002年11月27日、特定非営利活動法人失敗学会、東京都新宿区に正式登記
注3:航空事故調査委員会報告書62-2、日本航空株式会社所属ボーイング式747SR-100型JA8119、群馬県多野郡上野村山中、昭和60年8月12日、運輸省航空事故調査委員会、昭和62年6月19日、運輸省航空事故調査委員会
注4:御巣鷹山慰霊登山II、そして事故原因に関する新たな疑問、飯野謙次
執筆=飯野 謙次
東京大学、環境安全研究センター、特任研究員。NPO失敗学会、副理事長・事務局長。1959年大阪生まれ。1982年、東京大学工学部産業機械工学科卒業、1984年 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了、1992年 Stanford University 機械工学・情報工学博士号取得。
【T】
経営に生かす「失敗学」