
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
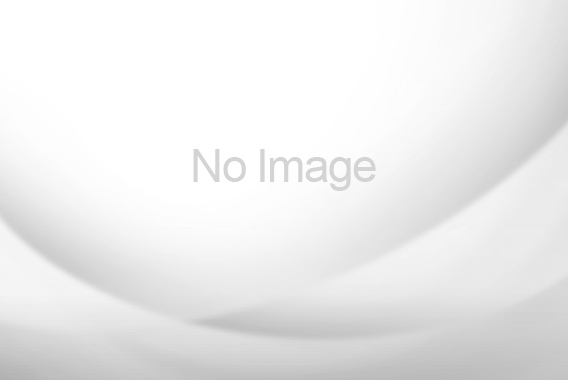
事故にはさまざまな規模があります。自分が出し得るよりはるかに大きな力、スピード、エネルギーを生み出せるのが、人間が考え出した機械であり、産業です。人間が機械を使わずに事故に遭うのはまれで、たまたま路面や階段から足を踏み外してけがをするときはあっても、ほとんどの場合、被害は自分の傷害で収まります。しかし産業事故の場合はそうはいきません。
自分が運転する自動車が生身の人間に衝突でもしようものなら、相手が死亡する場合もあれば、大きな後遺症を負わせる場合もあります。最近では自転車のような軽車両でも、対人事故の問題が取り上げられています。さらに大型の機械で事故が起こった場合には、複数の人命に関わったり、何百人、何千人と影響を受けたりする点は事故の歴史が物語っています。連載第2回はその産業事故について考えます。
人は障害なく育っていれば、その身体能力は極めて優れており、障害があっても訓練によっては健常者よりも優れた能力を発揮するときがあります。何万年もの太古から、常に運動を続けてきた人類は、歩行や階段の上り下りでの失敗はまずありません。それが道具を手にした途端に様相が変わります。
スタンリー・キューブリック監督の名作「2001年宇宙の旅」では、冒頭、猿人が骨を道具に使用することを発見し、その効果に歓喜してその骨を上に投げ上げると、それがいつの間にかスペースステーションに変わるところから始まります。
実際には猿も枝などの道具を使いますし、カラスもそうすると知られており、道具を使うのは何も人間の特権ではありません。人間の幼児も、教えられたわけでもないのに物心が付くと物を投げ始めるので、困った人も多いでしょう。さらに年長になると、石を使って水切りをするようになります。これも誰もが体験した遊びでしょう。このあたりから、道具と危険が表裏一体であると学び始めます。
川や池に向かって石を投げるのはいいとしても、決して人に向かって投げてはいけません。間違って人に当たろうものならけがを負わせてしまい、目にでも当たれば失明の可能性さえあります。子どもは、「危ないこと」だからそれをしないというより、人から教えられてそれは「いけないこと」として覚えるようですが、人のいないところを認識し、そこに向かって石を投げるのは、投げた石が他人に当たらないようにという意識と、思った方向に石が飛ぶように身体をコントロールする機能を使っています。
石を思った方向に、思った距離で投げるのはそう難しくありませんが、例えば自動車の運転となると、そうはいきません。座学の講習を受けてルールを覚えこみ、実機教習という練習を何時間も繰り返し、試験をパスして晴れて運転してよいとなります。
しかし、それでも自動車事故は起こります。無免許や酔っぱらいで事故を起こすのは論外ですが、健康な状態で何年もの運転経歴があっても事故を起こすときがあります。これは、自動車の運転という行為が、離れた目的の場所に素早く、かつプライバシーをある程度保ちつつ移動したいという人間の欲求を、自動車と人間の共同作業という“系”を持って実現しようとしたときに、その系が不完全であるから事故が起こるのです。
街中を走れば、予期せぬ外乱があります。運転手の注意力も常時100%ではなく、途切れる場合があります。運転手や同乗者を含めて1トンを優に超える鉄で囲まれた空間を、1時間で100キロ離れたところに移動させるのは、人間の身体能力をはるかに超えています。そのパワーが、衣服という外見だけの防御を身にまとった人間にぶつかれば、人間はひとたまりもありません。
つまり、運転という自動車と人間の共同作業が、不完全な系をなしていると考えなければなりません。自動車という強大なパワーが、目、耳、手足、そして脳を駆使して自分に与えられた作業分担をこなそうとする人間に頼り過ぎているといえるでしょう。最近は、コンピューターの処理速度が高まり、以前は時間がかかり過ぎて役に立たなかった機械による判断が瞬時にできるようになり、自動運転が話題になるほどです。しかし、この自動運転という言葉自体が誤解を招きます。
物事を大づかみに見ると、軌道を走るしかない「1自由度」の電車でさえ自動運転は実現していません。それなのに、道路表面上を前後左右に自由に移動でき、回転も付いて「3自由度」の自動車の運転が近い将来に「自動」でできるわけがありません。「運転支援」と呼ぶべきでしょう(注1)。
さらに系が大きくなると、一人の人間の手には負えず、大勢の人が関わって巨大システムの動作をコントロールする場合があります。こうなってくると、そのシステムの事故は大勢の作業員の安全だけではなく、近隣の住人にも影響を及ぼします。端的な例が福島第一原発事故です。被ばくによって直接被害を受けた人は少なかったものの、原発事故に関連した死者となるとかなりの人数になっていると考えられます。
この事故は人間の注意力に関連した事柄に由来するのではなく、起こり得ると分かっていた巨大津波に対して、事前にその対応を訓練していなかったことが原因であると失敗学会では結論付けました。トップの経営判断ミスというヒューマンファクターと言えなくもないのです。
ここではもっと規模が小さく、所内で収まったものの、4人の作業員の命を奪った事故について考えます。2007年12月、ある化学プラントで作業中の2人が、噴出するはずのないオイルを浴び、原因不明の着火によって火ダルマになって落命しました。その下でまったく別の作業をしていた2人も同様、火のついた油にまみれて死亡。現場は生産中ではなく、保守作業中での出来事でした。
作業は、通常は冷却オイルを通すパイプラインの途中にある、中実円板状の仕切り板を穴あきリング状のスペーサーに取り替えるときに起こりました。この作業を行うときは、冷却オイルが流れないよう、仕切り板の上流にある遮断弁を閉じた後、間違ってそれが開かないようロックを施し、かつその遮断弁を駆動する圧縮空気も、圧縮空気ラインの遮断弁を閉じて空気を抜いてやる手順がありました。
ところがその安全措置が、所内では常識と思われており、この日は、当の作業に当たった関連会社の作業員が、オイル遮断弁のロックも掛けず、圧縮空気遮断弁も閉じませんでした。さらに運悪く、仕切り板を持ち上げるのに使用していたチェーンブロックの手繰りチェーンを勢いよく手繰っていたら、それが暴れてオイル遮断弁開のスイッチに当たったというのです(注2)。
この作業を系としてみると、結局は人間の記憶、論理思考に頼り切った不完全なものだったのです。チェーンブロックの操作もこの系の中では手足、目、耳に頼った部分でしたが、こちらを自動化したところで、事故防止にはあまり有効ではありません。手繰りチェーンが暴れるのをなくすという意味では事故防止の一助にはなりますが、事故防止を考えるうえで、系の弱点をカバーする本質的な対策ではありません。
ヒューマンファクターの中で、手足という操作部は押し間違い、踏み間違い、目や耳の感覚部は見間違い、聞き間違いという問題をはらんでいるものの、今はまだそれらに頼らざるを得ない手順が多いのです。食品・飲料業界ではさらに味覚、化粧品ともなれば臭覚も必要でしょう。
しかし、記憶や論理思考に頼った系は、極力なくす努力をするべきです。脳をまったく使わなくなることはまずないとはいえ、重い負担をかけると正しい作業ができなくなるばかりか、機能が低下しているのに外から見てもまったく分からないのが問題です。ましてや協力会社の社員が、本社社員が安全の常識と思っていることを意識していなかったなどというのは、分からなくて当然でしょう。
この事故を起こした会社では、対策として抜けた上記手順を基準化したとあります(注3)。しかし、基準化しただけで作業員や協力会社スタッフは、それを常に意識してくれるものでしょうか。もっと根本的な解決が必要です。それが、チェーンが当たって想定外のオンになってしまったスイッチボックスにカバーを付けた同社の対策です。精神論ではなく、物理的にこの事故を繰り返さないようにしたこの防護が、最も効果的なのです。
(注1)自動ブレーキは「運転支援」 自動運転の説明厳格に、日本経済新聞、2018年11月2日
(注2、3)三菱化学工場火災、失敗知識データベース、CZ0200807
執筆=飯野 謙次
東京大学、環境安全研究センター、特任研究員。NPO失敗学会、副理事長・事務局長。1959年大阪生まれ。1982年、東京大学工学部産業機械工学科卒業、1984年 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了、1992年 Stanford University 機械工学・情報工学博士号取得。
【T】
経営に生かす「失敗学」