
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
2022年1月、電子帳簿保存法が改正されます。この改正には、電子取引のデータの保存方法に関するものも含まれ、企業に勤める会社員や店舗経営者、個人事業主などの立場に関わらず、すべての人が意識しておくべきものです。では、どのような点が改正され、何に注意をすればいいのでしょうか?
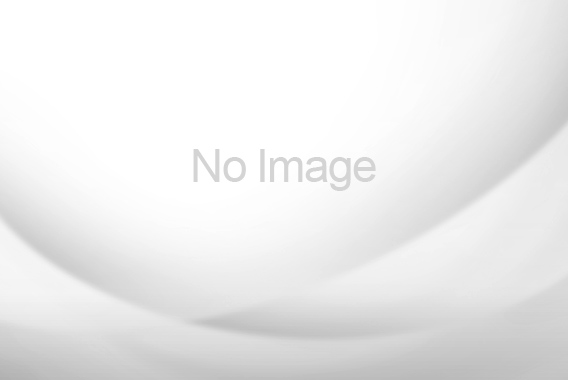
電子帳簿保存法とは?
「電子帳簿保存法」とは、元帳などの会計帳簿や、請求書や領収書などの主に会計関連の書類をデータで保存することを認めた法律です。
この法律ができる以前も、帳簿や取引を示す書面は保存が義務づけられていました。ただ、当時はデータでの保存よりも、現物である紙が重要視される時代であり、コンピュータで作成した帳簿データであっても、データでの保存は認められませんでした。そのため、経理担当者はすべてのデータを紙でプリントアウトし、ファイル等で物理的に保管しなければならなかったのです。それが1998年になって、業務の効率化を目的として電子帳簿保存法が施行されました。
電子帳簿保存法は、制定から現在まで何度か法改正が行われてきましたが、これは社会状況の変化に対応するためです。
例えば2005年の法改正では、紙の書類をスキャンし、データで保存することが可能となりました。つづく2016年には、スマートフォンやデジタルカメラで撮影したデータの保存も認められるようになりました。
このように、時代とともに企業が対応しやすい形へと変化しています。今回の改正もその一環といえるでしょう。
今回の法改正における大きな変更点は「電子取引に関する書類の保存方法」についてです。電子取引に関する書類とは、たとえば取引先とのメールに添付されたPDFの請求書や、ECサイトで会社の備品などを購入した際にダウンロードしたPDFの領収書などをさします。今までは、印刷し紙で保管することも可能だった電子取引に関する書類が、2022年1月からは電子データとしての保管が義務化されます。「電子で受け取ったものは印刷せずに電子で保管しなさい」ということです。
注意点は、経理上のすべてのデータを電子化するということではないこと。電子化が義務付けられるのはあくまで電子データで受け取ったもののみです。紙で受け取ったものに関しては、今まで通り「原則紙で保存だが、電子データ化して保存することも可能」ということに気をつけてください。
また、原則紙で保存すべき書類をデータ保存に変更する際には、税務署に対して事前に申請が必要でしたが、今回の改正によって緩和され、申請が不要となりました。
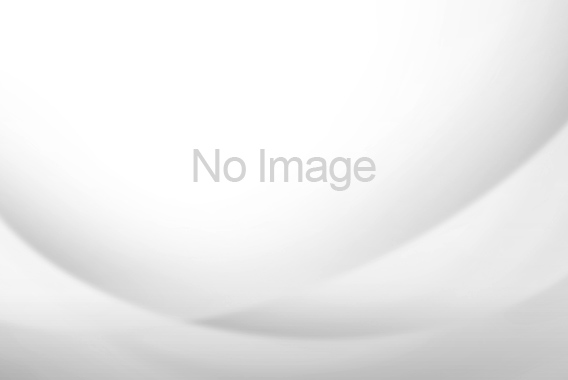
単なるデータ化ではない、2022年以降の注意点
「電子取引」によりやり取りされたデータは、そのまま電子データで保存することが義務化されますが、パソコンの中の適当なフォルダにオリジナルの電子データを保存すればOK、という単純なものではありません。そこにはさまざまな要件があり、適時・真正に作成されたデータであるという証明が必要です。
その代表例がタイムスタンプです。タイムスタンプとは、データの作成時点の証明と、改ざんがされていないことを証明するもののこと。単なる日付の記録ではありません。
発行者がタイムスタンプを付与した電子取引に関わる書類は、受領者側でもタイムスタンプ付与が必須で、紙媒体の書類をスキャナ保存する場合、その付与期間は3日間でした。今回の改正では、付与期間が3日から2ヶ月+概ね7日以内へと延長されました。
今回の法改正は電子取引の書類のタイムスタンプだけでなく、スキャナ保存の場合のタイムスタンプの要件も緩和されました。今までの要件だと3営業日以内にタイムスタンプを付与せねばならず、企業にとって現実的ではありませんでした。これを理由にスキャナ導入を見送っていた企業も、改めてスキャナ保存導入に踏み切るきっかけとなることが期待されています。
また、保存した電子データをすぐに見つけられることも電子取引のデータの取り扱いに関して重要なポイントです。
保管しているデータは「日付」「取引金額」「取引先」の3つの項目が見てわかるようにしなくてはいけません。さらに「日付」と「取引金額」は範囲を指定して検索ができることと、2つ以上の項目を組み合わせても検索ができることも求められます。
具体的な方法としては、請求書のPDFのファイル名を「日付_取引先_金額.pdf」とするなど、ルールを決めて保存していくことです。もしくは日付、取引先、金額などの要素すべてを正しく参照できる表を別途作成しておくのもひとつの手でしょう。
大切なのは電子取引のデータを受け取ったとき、それを社内でどのようなフローで回し、管理するのか、ということをしっかり決めておくこと。取引が多くなると単純に作業負担が増え、思いも寄らないトラブルを引き起こす可能性があるので、確実に実現可能な方法をあらかじめ検討しておきましょう。
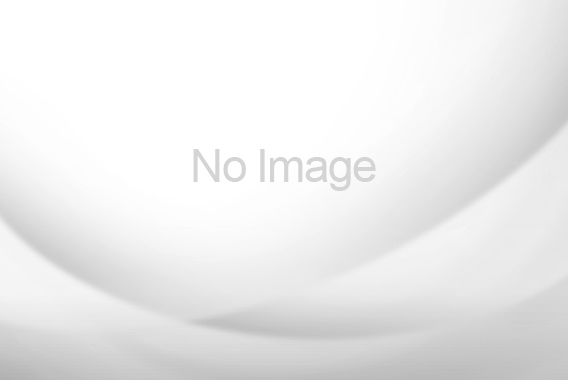
働き方で異なる対応方法
近年ますます重んじられるコンプライアンスの側面からも、企業における電子帳簿保存法遵守の重要性は増しています。今回の「電子取引のデータの電子保存」の義務化に関しては、まず「どれが電子取引なのか?」の棚卸しに時間がかかることが予測されます。大きな企業であればあるほど、取引も多岐にわたるためです。じっくり時間をかけて、負担が少なく実現可能な運用ルールをしっかりと定めましょう。
多岐にわたるのは取引だけではありません。それに携わる社員の数も多くなります。電子帳簿保存法の窓口である経理担当者ならその重要性をしっかりと理解していても、実務を担当する営業や購買の社員はあまり意識できていない、なんて可能性はありませんか?運用に関するルールはしっかりと周知を徹底しましょう。
電子取引の棚卸しやその運用方法の決定、また社内での周知の徹底など、準備しておくべきことはたくさんあります。施行されてからでは間に合いません。前もってしっかりと備えておきましょう。
また、例えば3月決算の企業だと「年度の替わる4月1日からの対応で構わないだろう」と思っていませんか?「電子取引データの電子保存」義務化のスタートは、2022年1月からです。たとえ年度の途中であっても、です。同じ年度の中でも電子書類の扱いが変わりますので注意してください。
個人事業主の場合は業務の中から、どれが電子取引に該当するかを容易に把握できるので、比較的フットワークの軽い対応が可能です。注意すべきは、しっかりとした業務フローが確立できていない場合、書類を溜め込んでしまいがちなこと。タイムスタンプには付与期間もあるので、こまめな処理を心がけましょう。
電子帳簿保存法をしっかりと遵守できていない場合、青色申告※の承認の取り消しの可能性がありますので、気をつけてください。
※青色申告… 確定申告を行う制度のひとつ。日々の取引を簿記に沿って正しく記帳することで、白色申告に比べ税制上のメリットが受けられる
ここ数年で紙の書類のやり取りはかなり減りました。この流れはますます増し、電子データを受領する機会も作成する機会も大幅に増えていくでしょう。ペーパーレスにより、目に見えないものを整理するには、頭の中できっちりと理解できていないといけません。
今一度、現状の書類のルールを確認しましょう。「電子取引のデータだからこう保存する」や「紙の書類はこう保存しよう」などとしっかりシミュレーションしておけば、今回の改正も恐れるに足りません。
また、何か困ったことがあった場合や、スムーズな管理と保存のために専門家に相談するのもひとつの手ではないでしょうか。
専門家プロフィール
島村 修平
2007年有限責任監査法人トーマツ入社、2012年デロイトトーマツ税理士法人転籍。その後、中小税理士法人の役員を経て2019年7月に島村修平会計事務所を大阪に設立。「会いたくなる、会計事務所」をキャッチコピーに上場企業からスタートアップまでの税務顧問を中心に活動。2018年4月より関西大学商学部非常勤講師。2020年2月度NewsPicksマンスリープロピッカー。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆= NTT西日本
【TP】
専門家が伝授する経営突破ナビゲーション