
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
前回の記事では「ほめる効果・効能」について、ほめる側の状況や変化を紹介しました。今回の記事ではほめられた側の効果・効能について論じていきます。
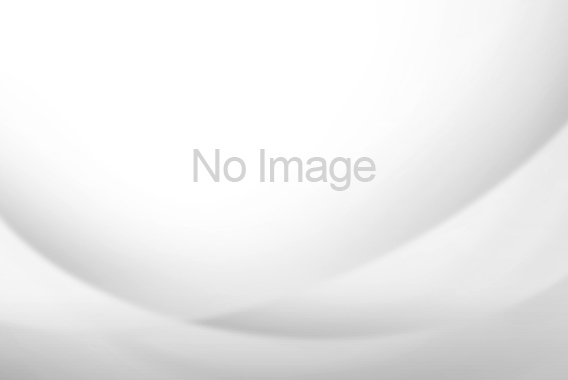
繰り返しになりますが、「ほめる」という行為は「他者に高評価を与える」ことに他なりません。つまり自分が行った努力や結果がほめられるということは、他者から見ても価値のあるものだと太鼓判を押されたようなもの。当然ほめられた人は、その評価を根拠に自信を持てるようになり、ポジティブな気持ちを持って次の行動に着手しやすくなります。
逆にほめられなかった場合や叱られた場合は他者からの評価を得られなかった証しとなり、「また怒られたらどうしよう」という思いから萎縮してしまい、次の行動に移るのをちゅうちょすることが少なくありません。そしてそれは新たにほめられるまで続きます。相手の成長を願うなら、ささいなことでもいいのでほめる言葉を投げかけてあげましょう。
部下がミスをした際、「叱りつつ間違いを指摘する」という行動をとる人が多いと思いますが、強く叱られると多くの人はある種の心のセーフティをかけて自分を守ろうとします。相手の話を聞かない、心の中で言い訳や文句を言い続ける、自分の世界に現実逃避するなど、要するに「聞く耳を持たない」という状態です。
指摘したにもかかわらず同じミスを繰り返す人がいる場合には、そもそも指摘を聞いていなかった可能性があります。しかし叱責の中にも「ほめること」を織り交ぜて話すと、相手は最後までコミュニケーションを放棄せず、指摘を受け入れる可能性が高まります。前述の「ほめると相手は心を開く」と似たような効果だと言えるでしょう。
ほめられた人は自信や喜びを胸に抱き、次の行動に移りやすくなります。他者から「ほめられる」という評価をもらった人は、「こうするとほめられる」という客観的な判断基準を得たということでもあるのです。
ここに「自己肯定感」と「積極性・行動力の向上」が加わります。行動力の向上が業務に向けられた場合、当然高いモチベーションによる生産性の向上が大いに期待できるでしょう。
いつの時代も部下は上司からの叱責を恐れています。なるべく叱られないように、目立たず無難に業務をこなすというのもそれなりの処世術ではありますが、それでは職場全体が縮こまってしまいます。現状の維持はできても、元気いっぱいの活力ある職場にはなりません。
しかし「良いことをすればほめられる」という行為が当たり前になった職場では、職場全体の雰囲気が明るくなったり、生産性が高まったりといった好影響が出ますし、「緊張感からの解放」という大きなメリットが見られるようになるでしょう。
「叱られるかもしれない」という緊張感は、次のミスを誘発する要素にもなりえます。職場を包む過度の緊張感をなくすためにも、「ほめる」という習慣を広めることは非常に有用だと考えられます。
多くの場合、悪いところをとがめるより、良いところを見つけてほめるほうが本人はもちろん、周囲にも有益な結果をもたらします。叱るべき点とほめるべき点の両方があった場合には、まずはほめることを優先してみてはどうでしょうか。
執筆=坂本 和弘
1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。
【T】