
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
 マーケティングで消費者の購買決定プロセスを説明するモデルの1つに、「AIDMAモデル」がある。AIDMAは「注目(Attention)」「興味(Interest)」「欲求(Desire)」「記憶(Memory)」「行動(Action)」という5つの行動プロセスの頭文字を取ったもの。それぞれのプロセスで適切なコミュニケーションを顧客との間で行い、最終的な購買につなげる方法だ。
マーケティングで消費者の購買決定プロセスを説明するモデルの1つに、「AIDMAモデル」がある。AIDMAは「注目(Attention)」「興味(Interest)」「欲求(Desire)」「記憶(Memory)」「行動(Action)」という5つの行動プロセスの頭文字を取ったもの。それぞれのプロセスで適切なコミュニケーションを顧客との間で行い、最終的な購買につなげる方法だ。
こうした考え方に象徴されるように、顧客の認知や興味の度合いなどによって、提供する情報の内容を変えると購買につながる可能性は高まる。狙った顧客に対して、的確に情報を変えてアピールする。これが業績向上の大きな武器になる。
「今日の日替わりランチ」「本日のタイムセール情報」「今だけお得なサービスメニュー」。飲食や商品、サービスなどを提供する店舗では、さまざまな“顧客に伝えたい”情報がある。流行の変化や商品開発のスピードが速まる中、そうした情報は増え、日々更新する必要が出てきた。
どうやって顧客に情報を伝えるか。数多くの店舗の中から自分の店舗を選んでもらいたい。少しでも強いアピールが重要になる。IT機器の普及が急速に進んだ今、こうした顧客へのアピール手段として頼るべきは「デジタル」のツールだ。
これまで、店舗から顧客へ情報を提供する手段として使われてきたメディアとして、看板、ポスター、サンプルなどが挙げられる。あるいは新聞に折り込んだり、店頭や駅前で配ったりするチラシも該当する。
ただ、これらはすべて、内容を柔軟に変更することが難しい。制作にコストと時間がかかるので、頻繁に作り変えるのは現実的ではないからだ。手軽に内容を変えるには、店頭に黒板タイプの看板を出して、書き換えるなどの方法が多かった。
最近は高性能なプリンターが登場したおかげで、ある程度のパソコンスキルがあれば、ポスターやチラシが手軽に作成できるようになりつつある。とはいえ、こうした制作物は、デザインの“素人”である店舗スタッフが作っても、クオリティーを上げるのは難しい。表現の手法も、文字にイラストや写真を組み合わせるくらいしかできない。
こうした旧来の情報メディアでは、最近の店舗アピールニーズに対応しにくいといえる。
まず、情報の増加やサイクルの短期化に対応できない。張りっ放しのポスターや、出しっ放しの看板、ほこりをかぶったサンプルでは、訴求力が落ちる一方だ。その“瞬間”に最適な魅力を訴求しなくては売り上げにはつながらない。毎日どころの話ではない。時間帯によってでも変更したいのが店舗の本音だろう。飲食店ならランチとディナーで提供情報も変えるべきだ。小売店なら、タイムセールや新入荷商品の情報を時間に合わせて提供したい。
さらに、アピールに動画や音声を使いたい。最近は、スマホやタブレットで動画を視聴するのが当たり前になっている。飲食店なら、肉を焼いたり天ぷらを揚げたりする動画や音で、食欲をあおる。衣料品店なら、販売している服を着たモデルが格好良く動くさまを見せて購買意欲をそそる。こうしたプロモーションは、従来メディアでは限界がある。黒板タイプの看板と、動画や音を使ったアピールと、どちらが効果的かは明らかだろう。
また、従来の方法ではインバウンド需要の取り込みも難しかった。日本語の看板やポスターに加えて、英語や中国語バージョンを用意したくても、その分用意するのは大変だし、スペース自体が店頭にないケースもある。
こうした従来メディアの課題を解決するのがデジタルメディアの活用だ。デジタルを活用すれば、情報の更新が簡単で、常にその時に出したい情報を顧客に見せられる。
動画や音声の活用もたやすい。店頭でいうと、動きのあるものに対して人間は興味を引かれやすく、目にも留まりやすい。多言語対応にも対応しやすい。同じ写真や動画に、複数の言語で説明をしたバージョンを用意して、切り替えれば多言語対応が実現する。
従来のチラシもデジタルに置き換えられる。例えば、商店街やショッピングセンターの無料Wi-Fiを使って、広告やチラシを配信できる。それらは、ユーザーのスマホやタブレットに届く。
従来、こうしたデジタルメディアの活用は、コストや技術の面で、中小の個人店レベルにはハードルが高かった。しかし最近は、大きな投資をせずとも既存のインフラも利用できるし、機器の価格もそれほど高くない。運用方法も簡単になっている。顧客に店舗の情報や魅力を訴求するデジタルソリューションが、非常に利用しやすくなっているのは確かだ。ぜひ、デジタル化の検討を進めたい。
執筆=岩元 直久
【MT】
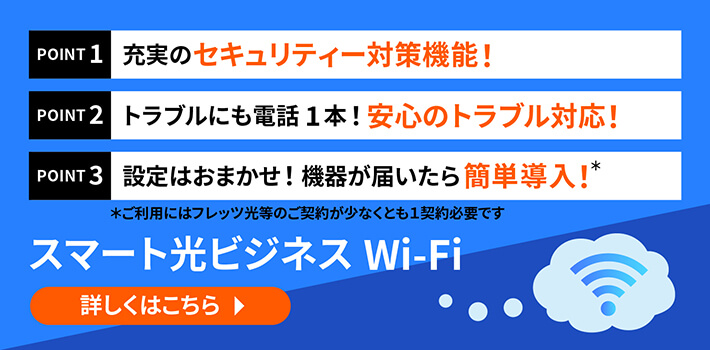
顧客対応でファンを増やす