
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
「病院内でスマートフォン使用はOK?それともNG?」この質問に皆さんはどう答えるだろうか。少し前までは「本当に限られた場所以外はNG」という病院が多かったが、最近はかなり状況が変わっている。
数年前までは、多くの病院で携帯電話などの使用は原則的に禁止されていた。なぜなら電波の使用を制限するためだ。医療機器が多数設置される病院内で電波を発信する行為は機器の障害、誤作動を引き起こし、人命に関わる深刻な事態を招く可能性がある。電車や飛行機などでの使用も同様の理由で禁止、もしくは制限付きという時代が長年続いてきた。
この状況に変化をもたらしたのが、2014年8月に電波環境協議会が発表した「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」だ。同協議会が1996年に出した指針では「屋内では電源を切ることが望ましい」とされていたが、その後の技術進歩や検証の積み重ねにより、手術室、集中治療室、検査室など一部のエリアを除き、医療機器から一定の距離を確保するなどの安全対策を行った上で使用可能という新たな見解が示された。
その後、待合ロビーや受付・会計窓口など、多くの人が集まるスペースを中心に、スマートフォンを操作する人の姿を見かける機会が増えつつある。同協議会の調査では、2015年の時点で全国の9割を超える施設が院内一部エリアでの使用を認めており、この傾向は今後も続くと思われる。
携帯電話会社や端末を問わず利用できる無料Wi-Fiサービス(公衆無線LAN)は、外出先から気軽にインターネット接続するための仕組みとして、全国的に整備が進められている。新指針により院内での電波利用が可能になったことから、各病院では患者向けサービスとしてのWi-Fiに着目し、導入の検討を開始した。
多くの病院が抱える課題に「待ち時間の長時間化」がある。待ち時間を短縮するための努力は続けられているが、診察人数や診察時間は予測が難しいので実現は容易ではない。そこで「退屈な待ち時間をいかに快適に過ごしてもらうか」を追求することで、満足度を向上させるWi-Fi環境の整備が進められている。
不特定多数の人が訪れる病院の場合、契約や複雑な利用手続きが必要なサービスは実用的とはいえない。だが公共性の高い施設なので、一定レベルのセキュリティの確保が求められる。これらを踏まえ、各病院ではさまざまな検証を実施し、利便性と安全性の両立をめざしている。
現在、無料Wi-Fiを提供しているケースが目立つのは、待合ロビーや受付といった外来患者を対象としたスペース。それ以外にWi-Fi利用に対するニーズが高まっている場所がある。それが入院患者の病棟だ。スマートフォンが日常生活に欠かせないツールになっている現在、Wi-Fiが使えない病室で終日過ごすことは、入院中の患者にとってストレスの原因となる。治療に専念するのは大切だが、気分転換や退屈を紛らわす手段としてスマートフォンが利用できるメリットは大きい。
千葉県の亀田総合病院は病棟内の各フロアにアクセスポイントを設置し、入院中の患者が病室でWi-Fiを利用できる環境を2015年に構築した。患者にとって快適な環境をつくることが医療の充実につながるという考えに基づいた同院の取り組みは、先進的な事例として注目を集めている。
治療への影響などを考慮して、病室でのWi-Fi提供を見送る病院も相当数存在するが、入院患者のQOL(生活の質)を向上し、患者満足度を上げる手段として、近い将来に一般的なサービスとして普及する可能性はあるだろう。
このように広がりを見せている病院でのWi-Fi整備だが、注意すべき課題もある。IT活用が進んだ病院では、電子カルテや医療機器の管理に以前から無線LANが使われ、重要な情報がやり取りされている。
電波を発する機器が多数ある環境では、混信や電波干渉といった現象が起こりやすくなる。スタジアムや駅などでWi-Fiが使いにくい状況になるのと同様に、院内の電波も、利用者が増えれば影響を受ける。
電波環境協議会が2015年に行った調査によると、対象となった病院の約2割が電波利用機器の使用に起因するトラブルを経験している。中にはデータの受信不良で患者の異常発見が遅れたり、電波干渉により電子カルテ端末が使用できなくなったりといった重大なケースも報告されており、不安は尽きない。
基本的に病院は医療行為をする施設なので、電波管理に関する知識を持つスタッフは少ない。人命に関わるトラブルは絶対に避けなければならない。無料Wi-Fi導入に際しては必要に応じて専門事業者の協力を得て、十分な注意を払って進めるべきだ。
執筆=林 達哉
【MT】
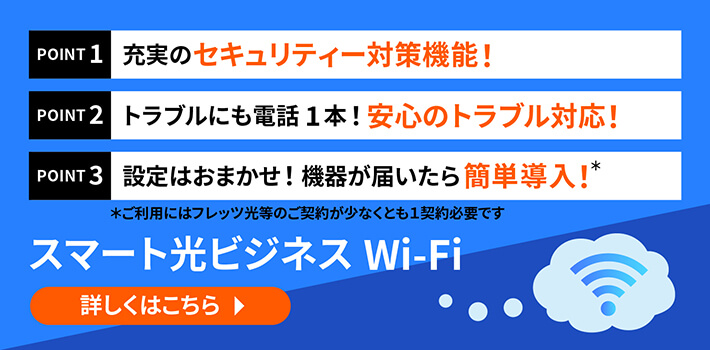
顧客対応でファンを増やす