
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
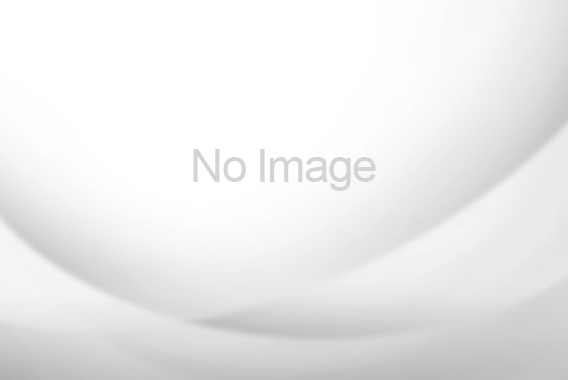 過去の日本において常態化していた「性差に関する差別意識」が、現代日本で徐々に様変わりしてきているのはこれまで説明してきた通りです。前回はその変化を「仕事そのものに対する意識」に求めましたが、今回は「生き方に対する意識」に焦点を当てて説明します。
過去の日本において常態化していた「性差に関する差別意識」が、現代日本で徐々に様変わりしてきているのはこれまで説明してきた通りです。前回はその変化を「仕事そのものに対する意識」に求めましたが、今回は「生き方に対する意識」に焦点を当てて説明します。
一昔前のジャパニーズ・ビジネス・パーソン(主に男性)の生活・人生に関する意識といえば、「仕事ありき。仕事を人生の中心に捉えた生き方の模索」がほとんどでした。ビジネス界では「会社に必要とされる人間になるためにはどう立ち振る舞えばいいのか?」「自己実現を可能にする会社・仕事選びとは?」「管理職のためのメンタルヘルス」というようなトピックが目まぐるしく飛び回り、その都度ビジネス・パーソンの考え方や行動様式に影響を与えてきました。
社会が成熟し、グローバルビジネスやITツールが浸透・常識化するという変化の中にあって、「これまでと同じ考え・働き方をしているだけではその速い流れに振り落とされてしまう」という強迫観念にも似た自己改革・自己啓発意識を持つようになった彼らは、必死に自分磨きの術を模索しました。
そういった生存競争・ふるい落としを乗り越えてきたビジネス・パーソンがいたからこそ、日本はバブル崩壊後の壊滅的な不況下にあってもなお世界に対峙できる経済大国としての立場を守り抜けたともいえます。
しかし一方で、その努力や認識が「サービス残業」「名ばかり管理職」「過労死」といった社会的な大問題を生み出しました。最近ではそれらの問題や違法行為を「社畜」や「ブラック企業」といった言葉に置き換え、必死に働くビジネス・パーソンを使い捨てる企業を問題視する風潮が定着しつつあります。
これまでにも、日本は海外から「エコノミック・アニマル」「ワーカホリック」「働きアリ・働き蜂」と皮肉られていましたが、昨今の風潮はその当時のものとは若干性質が異なります。
というのも、エコノミック・アニマルの頃は、労働者本人はもちろん、国民全体が働くことに意味や価値を見いだし、個人的な大小はあれど、それぞれが使命感や美徳意識を持って仕事に向き合っていました。当時日本人をエコノミック・アニマルと呼んでいたのは、海外のビジネス・パーソンがほとんどでした。
ところが、現在彼らを「社畜」と皮肉っているのは海外のビジネス・パーソンではなく、その大部分が「(自らはそれほど)働いていない日本人」に変化しました。それが「不景気で正社員になれなかった人」なのか、それとも「就業はしているけれど、適切な仕事ができていない人」なのか、あるいは逆に「余裕を持って仕事をしている人」なのかは定かではありません。
どちらにせよ「日本のビジネス・パーソンを積極的に皮肉っているのは日本人である」という点に、エコノミック・アニマル当時との違いが見られるようになりました。
これらの変化が超長期的に世界を襲っている不景気が生み出したひずみであることは想像に難くありません。これを個人的なネタミや国民性としての卑屈根性という視点を除いて考察すると、「これらの変化は、労働者の働き方に関する意識が従来の仕事ありきの精神から脱却しつつあることの裏返し」だと捉えることができるのではないでしょうか。
こう言い切るのはやや乱暴かもしれませんが、少なくとも戦後70年の間に、国民の中に「人生は仕事だけじゃない。自分の人生や生活を豊かにするために、もっと余裕のある働き方を選んでもいいのではないか」という意識が芽生えたのは確かでしょう。また、その考えが、ある一定の市民権を持ちつつあるということも肌で感じられるようになりました。
このような意識の変化の流れを受けてか、数年前から「ワーク・ライフ・バランス」という言葉がいろいろなところで聞かれるようになりました。
今でこそワーク・ライフ・バランスという言葉は一般にも浸透し、多くの企業で取り入れられていますが、言葉が広がり始めた当時は、ビジネス界によく見られる「バズワード(buzzword:言葉自体に意味や説得力があるよう見えるが、実際には明確な定義や普遍性がなく、曖昧なニュアンスのみを有する言葉。新語や造語によく見られる)」の一種として扱われることも少なくありませんでした。
その歴史をひもとくと、最初にワーク・ライフ・バランスという言葉を使ったのは1980年代の米国といわれており、当時は「ワーク・ファミリー・バランス(女性が仕事と家庭のバランスを保つための施策)」という言葉でした。当時米国では、1960年代後半に発生したウーマン・リブ(Women’s Liberation)運動が勢いを増し、高学歴の女性や社会進出に積極的な女性を中心に、その多くがビジネス界に進出し始めていました。
同時に米国式資本主義の成長に伴う経済格差の拡大や貧困層の増大などにより、社会に出て働く気のなかった女性たちも、生活に追われる形で社会に押し出されていきました。こうした背景を受け、米国企業の多くは世界に先駆けて「女性の労働力化」に取り組み始めます。そこで企業がまず取り組んだのは、ワーク・ファミリー・バランス(ワーク・ライフ・バランス)の(現場レベル・実務レベルでの)実現でした。
すでに「男女同権意識」が定着していた米国企業が重要視したのは意識改革ではなく、女性が働くための環境整備や法整備といった具体的な施策。そしてそれらの施策は、「今後企業が成長するためには優秀な女性労働者の確保・定着が必要不可欠。そのためには女性労働者が働きやすい、あるいはその会社で働き続けられる環境こそが大切である」という考えの下、「育児休暇の確実な実施、および質・量の充実」「託児所・育児室・授乳室などの設置」「男性労働者への(女性労働者を受け入れるための)教育」といった形で実現していきました。
当時は「女性労働者独自のライフスタイル」といえば、まず「出産・育児」が筆頭に挙げられるほどだったため、特に「育児」に関する環境整備に力を入れていたようです。
その後時代が変わり、呼び名がワーク・ライフ・バランスに改称され、「女性独自の福利厚生」という意味合いが強かったワーク・ファミリー・バランスは、徐々に「労働者の士気向上」「企業の生産性向上」「企業文化の変革とそれによる現状打破」などに主眼を置いた経営戦略的な色合いを濃くした概念に変わっていきました。
つまりワーク・ライフ・バランスは、当初の「単なる育児支援」から「企業利益を増加させるための企業戦略」として大きく成長したといえます。
執筆=坂本 和弘
1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。
【T】
経営者のための女性力活用塾