
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
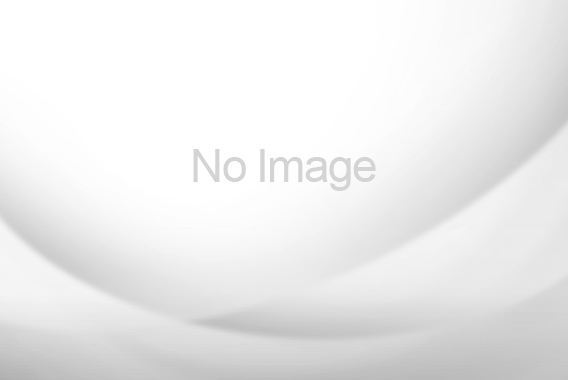 仕事が忙しく、働き過ぎが指摘される学校の教員。業務の負担を軽減し、長時間労働の改善に向けてはITの活用が欠かせない。例えば、教職員の情報共有にグループウェアを活用すれば、職員会議の回数や会議時間を減らせる。
仕事が忙しく、働き過ぎが指摘される学校の教員。業務の負担を軽減し、長時間労働の改善に向けてはITの活用が欠かせない。例えば、教職員の情報共有にグループウェアを活用すれば、職員会議の回数や会議時間を減らせる。
グループウェアを含め、教務や保健、学籍、学校事務などの機能を統合したのが統合型校務支援システムだ。システムの利用で教職員の校務の負担を軽減するだけでなく、学校内の情報の一元管理が行える。円滑な学校運営が可能になる。
統合型校務支援システムの効果はどうだろうか。文部科学省の「統合型校務支援システムの導入のための手引き」(以下、手引き)によると、教員の業務時間の削減効果に加え、手書きしていた業務の電子化で転記ミスが減らせるなど業務の質の向上が可能だという。また、同じシステムを利用している学校へ異動した場合、事務手順に大きな違いがないため引き継ぎがスムーズに行え、時間短縮になる。教育現場で課題の働き方改革にもつながる。
統合型校務支援システムは、児童・生徒の成績や指導、進路、健康診断などの機微な個人情報を扱う。だから万全の情報セキュリティが必須になる。統合型校務支援システムなどの取り扱いについて、文部科学省の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」ハンドブックでは、「重要な情報資産を格納する校務系サーバーはデータセンターなどに集約した上で教育委員会による一元的な管理を行う必要がある」としている。
統合型校務支援システムが置かれるデータセンターと、教育委員会や学校を結ぶネットワークについてもセキュリティが重要になる。万一、児童・生徒の個人情報がネットワーク経由で盗まれれば、その影響は学校だけにとどまらない。"地域の信用"にまで発展する事態になりかねない。
手引きでは、回線種別(専用線・閉域網)と回線帯域についても記載している。回線種別については、利用料金だけでなく、ネットワークの品質と通信速度が担保されているかどうかを踏まえて選定する。さらに、通信事業者が提供する専用線サービスやVPN(仮想閉域網)サービス、都道府県が整備している情報ハイウェイを例示する。
回線帯域については、統合型校務支援システムを利用する端末数や利用時間帯などを踏まえて選定する。通知表を作成する学期末には回線が込み合う。作業に支障を来す可能性もある。学期末など繁忙期を考慮して選ぶ。回線に接続する学校数が約250拠点の場合、1ギガビット/秒の回線帯域が必要になるとしている。
学校では教職員が利用する校務用のほか、児童生徒が利用する学習用のネットワークがある。学習用サーバーは、大容量の動画・画像を扱うので学校内に設置する場合が多い。しかし、小学校でプログラミング教育が始まったり、デジタル教材が使われたりするようになると、各学校で利用するコンテンツを教育委員会が管理するデータセンターに集約する方法も考えられる。
つまり、統合型校務支援システムや学習用デジタルコンテンツなどの利活用に向け、教育委員会と学校を結ぶ通信回線には、高いセキュリティと高速・低遅延、リーズナブルな費用で多数の学校を接続可能といった要件が必要になる。
そうした要件を満たす通信回線として、外部のインターネットに出ることなく通信事業者の閉域網で複数の拠点間をセキュアに接続するVPNサービスがある。さらに、拠点間をダイレクトに接続し、低遅延で安定した通信が可能な新しいVPNサービスも登場している。
児童・生徒の個人情報を扱う統合型校務支援システムは安全な活用が大前提となる。自治体や教育委員会には、教職員の負担を軽減し、働き方改革を促進する施策が求められている。IT戦略を検討することにもなるだろう。その際、ネットワークの重要性を決して軽視してはならない。
執筆=山崎 俊明
【MT】