
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
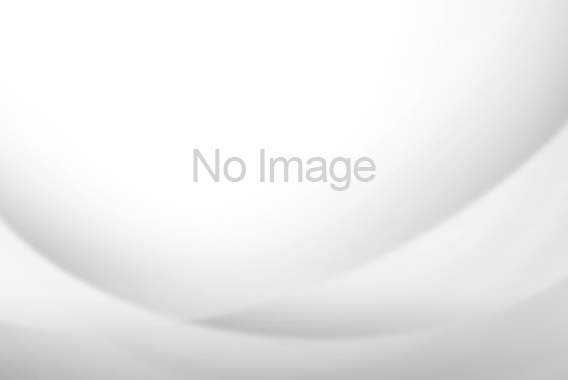 東日本大震災の発生から6年。その後も、熊本地震など大規模な自然災害が起きている。そうしたリスクへの備えとして、災害時にも事業を継続できるBCP(事業継続計画)の策定を進める企業は少なくない。
東日本大震災の発生から6年。その後も、熊本地震など大規模な自然災害が起きている。そうしたリスクへの備えとして、災害時にも事業を継続できるBCP(事業継続計画)の策定を進める企業は少なくない。
大規模な自然災害が事業へ及ぼす影響で代表的なのは、電力、ガス、水道といったインフラの破壊だ。中でも停電はビジネスに大きなダメージを与える。オフィス内はパソコンやサーバーなどの各種情報機器に加え、ビジネスフォンなどの通信機器がネットワークにつながれている。これらの重要な機器は、当然ながら電力がなければ動かない。
停電は大規模災害がなくても起こりえる。2016年10月に変電設備のケーブル火災により東京都内の一部で発生した停電事故は、官庁や企業の業務を一時停止させるなど大きな影響を及ぼした。日本では安定的に電力が供給され、空気や水と同様に電力は“当たり前”の存在として考えられがちだ。こうした事故に驚いたかもしれないが、実は停電は日本各地でかなり頻繁に発生している。
電力会社の業界団体である電気事業連合会が公表している「停電回数と停電時間の推移」によれば、2014年度の停電件数(高圧配電線路、送電線路などの電気事故)は電力会社10社の合計で1万1970件に上る。1日に換算すると32件、全国のどこかで電気事故が発生していることになる。過去5年間の数字を見ても、1万1000~1万4000件で推移する。
各電力会社は、Webサイトで停電の発生を毎日アナウンスしている。東京電力ではWebサイトの停電情報で発生履歴を公表。それによると新年早々の1月3日、東京都中央区銀座で停電が発生している。関西電力では停電情報で過去1週間の履歴を公表している。多い日には停電発生は10件以上にも上る。
停電の原因は、風雨・水害、他物接触、設備不備・保守不備、雷、氷雪などさまざまだ。家庭や会社に電力が供給されるまでには、複数の送電ルートを経由するケースが多い。ある送電線路が事故を起こしても、直ちに停電とはならない。とはいえ、ビジネスを継続する上で、停電のリスクは無視できない。
停電時の大きな問題としては、オフィスや店舗の電灯やエアコンが使えなくなり、業務が遂行できなくなる点が挙げられる。こうした直接的な被害以外で困るのは、オフィスに多数存在する情報通信機器が使えなくなることだ。
パソコンやサーバーなどの情報機器は、停電が起きれば操作ができなくなるだけでなく、データ消失が一番怖い。情報という会社にとって大切なリソースが失われれば、ビジネスは停止してしまうことも考えられる。機器自体が故障するリスクもある。
予期しない停電や落雷などで送電経路を切り替える際は、瞬間的に電圧が低下する「瞬時電圧低下」といった電源障害が発生する。パソコンやサーバーにおける対策としては、機器とコンセントの間に装置を介在させ、内蔵したバッテリーで一定時間、電力を供給するといった方法がある。
情報通信機器に電気が流れなくなるのは、何も電力会社による停電だけではない。オフィスの床にはわせた電源ケーブルを引っ掛けてコンセントから抜いてしまうといった“うっかり”ミスで電源が落ちることだって珍しくない。こうした電源断のリスクは、日常茶飯事だと認識しておいたほうがよい。大切なデータが消失してから、あるいは機器が壊れてしまってから後悔しても後の祭りだ。打つべき対策は打っておく。それほどの投資額にならない方法もあるのだから、検討する価値はあるだろう。
執筆=山崎 俊明
【MT】
万一の備え、事業継続計画策定のススメ