
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
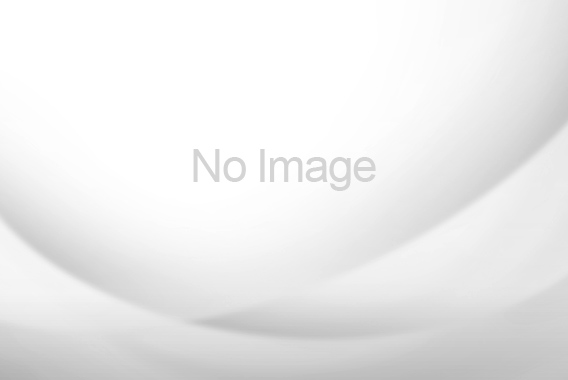
西暦2000年は世紀の変わり目だけではなく、失敗学にとっても大きな節目でした。当時の文部大臣・科学技術庁長官、中曽根弘文氏の私的懇談会であった失敗知識活用研究会(注1)が行った提言の中に「失敗経験の積極的活用のために」(注2)が盛り込まれ、科学技術振興機構が翌年に取り掛かったのが、「失敗知識データベース」(注3)の構築です。
総括を担当したのは、2000年に『失敗学のすすめ』を著した失敗学会会長の畑村洋太郎氏でした。1000件以上の失敗事例を集め、専門家による解説をまとめて2005年に公開されたデータベースでしたが、2011年3月に科学技術振興機構としての公開は終了。当時の事業仕分けの対象となってしまったのです。
この国家的財産を無きものにするのはあまりにもったいないと、畑村会長はその内容を個人事業のホームページに受け継ぎ(注4)、その後、2017年6月にはNPO失敗学会ホームページに移管されました(注5)。
2001年の公開とされている失敗知識活用研究会による「失敗経験の積極的活用のために」を今読み返すと、失敗知識を共有して失敗の未然防止をうたうのは当然ですが、失敗知識から創造力強化や問題解決能力を目指すとしています。
さらに、「不十分なリスク認識」に警鐘を鳴らし、「技術の限界と未知領域においては『失敗は起こり得るもの』とする社会的認識の醸成」を勧めています。まるで、福島原発事故を予見するかのようです。
「失敗学」という言葉を聞くと、多くの人がどうやって知識を共有し、気持ちを引き締めて失敗を繰り返さないようにすればいいかを教えてもらえるものと期待するようです。間違ってはいないのですが、気持ちを引き締める精神論では失敗をなくすことはできません。
知識を共有したときに、創造性を発揮した問題解決を目指す努力を続ければ、身の回りや世の中の失敗を減らすことができます。失敗知識活用研究会の提言を目指さねばなりませんと書くのは簡単ですが、創造力強化は簡単ではありません。
ここのところ、創造性の育成について多くの情報が行き交っています。以前は技術革新が人々の目標でした。革新的なアイデアを思いついても、それを実物として世に出せなければ創造的ではありません。
私は2つの大学院で創造設計を教えています。年度の上期は上智大学で日本語の創造設計の講座、下期は東京大学で英語の創造設計の講座を行っています。残念ながら上智大学には工作を行う環境がありません。この講座は、自分のアイデアをポスターに表現して終了となります。
下期の東京大学の講義では、学生がポスターを作成、その後にプロトタイプも課しているので結構大変ですが、留学生には人気の講座です。ポスターを製作してもらうのには、理由があります。2016年からThe ASF Design Challengeという名前のデザインコンテストを開催していて、設計案をポスターで提示してもらっているのです。
社会人チームも参加しています。主催は失敗学会で、12月の年次大会への参加者による投票で優勝チームを決めています。ただし投票する側も、ポスターの見た目に引きずられてしまう傾向があり、真に創造的で実現可能性の高い設計が優勝するとは限りません。
ある留学生チームは、雨のときに手で傘を持つのがいやだと、常に持ち主の頭上に浮かぶ「きんと雲傘」を考えました。このチームの中心を担っていた2人は講座終了後も試作を継続し、「きんと雲傘」がユーザーの頭を見つけて自動で追従するところまでできました。
子どもがプールで溺れるときは、溺れそうになったら暴れれば見つけやすいのに、静かにうつぶせ状態になる場合が多いのだそうです(注6)。ある社会人チームは、これをいち早く発見して警報を発する「溺水警報ゴーグル」を考えました。このアイデアは、ポスターコンテストで優勝した後、実際に試作されました。毎年の楽しみなイベントの1つです。
講座を通した創造性育成の取り組みについて説明しましたが、実際はどうすれば創造性が高まるのかは、誰もが気になるところでしょう。まず第1に、問題発見が大きな要素となります。日ごろから、「不便」を敏感に感じ取り、それを言葉にする練習が重要です。
言葉にできなければ、何となく感じただけで終わってしまい、月日がたつとその不便さを忘れて、いつの間にか不便と感じないのが人間です。スマホや携帯電話の写真でその不便な瞬間を記録するのも手軽でよいのですが、私はそれを人に説明するときに、手描きの絵で説明することを推奨しています。
私たちは、子どものときは創造性を育む授業を数多く受けてきました。美術、書道、工作、家庭、音楽などです。それらは学年が進むにつれて姿を消していき、高校3年にもなると全くなくなってしまいます。大人になって、手描きのスケッチで何かを説明する人は、設計者でもない限り、ほとんどいません。手描きで白紙にシンプルな絵を描いて、概念が分かるように人に伝えるのは、私たちが失ってしまった創造性を取り戻すための練習になります。
次にアイデアをいかに出すかです。効果的なのは付箋を使うブレーンストーミング。常識人、特に会社で高い役職に就いていると、このブレーンストーミングが苦手なようです。発想が常識の中で行ったり来たりしてしまうのでしょう。
ブレーンストーミングは、脳の中に数多くある概念の組み合わせのうち、今までにつながっていなかったリンクを見つけ、斬新な解を生み出すことを期待して行うものです。とっぴもないと思われる言葉が飛び出してこそ、新しいアイデアにつながるもの。経験や知識を駆使するのは、この次に待っている解を構造化する段で発揮すればよいのです。しかし、このブレーンストーミングも古い方法なので、そろそろもっといいやり方が出てくるのではないかと思います。
私たちが受験戦争や社会人としての業務を通して失った創造性が、今後は必要となってきます。そのときに取り残されないよう、今、創造性を取り戻す努力が必要です。
参考文献
注1:次田彰、失敗知識活用研究会の活動および失敗知識データベースの構築について、安全工学、Vol.41、No.3、2002、NPO安全工学会
注2:失敗知識活用研究会報告書-失敗経験の積極的活用のために-、失敗知識活用研究会
注3:失敗知識データベース、失敗学会
注4:第3回政策首脳懇談会を開催(2011年11月9日)日本MOT振興協会
注5:失敗知識データベース継受、失敗学会、2017年
注6:教育・保育施設等におけるプール活動・水遊びに関する実態調査、消費者安全調査委員会、2018年
執筆=飯野 謙次
東京大学、環境安全研究センター、特任研究員。NPO失敗学会、副理事長・事務局長。1959年大阪生まれ。1982年、東京大学工学部産業機械工学科卒業、1984年 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了、1992年 Stanford University 機械工学・情報工学博士号取得。
【T】
経営に生かす「失敗学」