
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
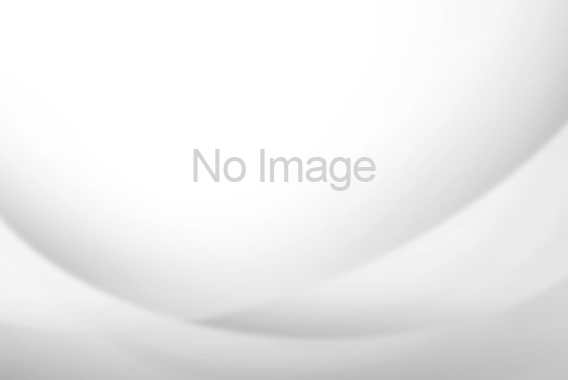
労働者がメンタルヘルス不調になった場合、事業者側の相談先としては、日ごろから労働者の健康管理などについて相談に乗ってもらっている産業医(嘱託産業医)、EAP(従業員支援プログラム)企業など外部の専門機関、労働者側の主治医(かかりつけ医)が考えられます。主治医への相談は、労働者の同意を得ることが前提です。
メンタルヘルス不調者に対する実務上の対応で最も基本的なことは、正しい知識のない者が不用意な対応をしないこと。医療機関での受診を促す際も、一定の配慮が必要です。
●産業医(嘱託産業医)
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければなりません。また、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するために、ストレスチェックを実施しなければなりません。
ストレスチェックは医師や保健師を通じて実施しなければならず、また、ストレスチェックの結果、「高ストレス者」と判定された労働者が申し出た場合、医師による面接指導が必要となります。ストレスチェックの実施や高ストレス者への面接指導は、職場の状況を理解した医師が担うことが望ましく、その点、日ごろから労働者の健康管理などについて相談に乗ってもらっている産業医は適任です。
ただし、常時使用する労働者が50人以上999人以下の事業場は、専属産業医を選任する必要はない(有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合を除く)ため、非常勤の嘱託産業医を選任するのが一般的です。嘱託産業医が、必ずしも精神疾患の治療経験や専門知識を持っているわけではありません。中には、メンタルヘルス関連業務について消極的な産業医もいるようです。
●EAP企業など外部の専門機関
ストレスチェックの結果、医師による面接指導を申し出る場合、その申し出は事業者を介して行います。その際、労働者は自身が「高ストレス者」であると事業者側に知らせることになるため、心理的なハードルが高いとも考えられます。
そのような中、EAP企業など外部の専門機関に委託し、労働者の相談を受け付ける窓口を設ける事業者も増えています。EAPはEmployee Assistance Programの略称で、メンタルヘルスケアなどについて従業員(労働者)を支援するためのプログラムです。
EAP企業など外部の専門機関の中には、労働者に対するカウンセリングだけではなく、事業者(経営者や人事担当者など)に対して、労働者のメンタルヘルスケアに関するコンサルティングを行ったり、メンタルヘルス関連業務に精通した産業医を紹介したりするところもあります。
●労働者側の主治医(かかりつけ医など)
労働者がメンタルヘルス不調で長期欠勤する場合、事業者は労働者が就業規則などの休職事由に該当するかを判断するため、医師の診断書を求めることになるでしょう。また、メンタルヘルス不調で休職中の労働者の復職について、事業者の有力な判断材料となるのが医師の診断書です。
労働者の同意を得た上であれば、事業者が労働者側の主治医に職場や業務の実情、労働者の勤務内容などを説明し、復職の可否について意見を求めることもできます。労働者の同意を得るのは簡単ではないかもしれませんが、復帰後に働ける状態にあるか否かを証明する責任が労働者側にあるのも事実です。なお、主治医と面会する際は、労働者の同意を得ていると主治医に明らかにするために、当該労働者を同席させる場合もあります。
●メンタルヘルス登録相談機関
メンタルヘルス登録相談機関は、国の登録基準を満たしていると確認された機関で、事業者と契約を結び、有料で面接による労働者の心の健康に関する相談を行う専門機関です。労働者健康安全機構がメンタルヘルス登録相談機関のリストをウェブサイトで公表しています。例えば、次のような機関が挙げられます。
・アドバンテッジ リスク マネジメント
アドバンテッジ リスク マネジメントは、東京本社の他、名古屋、大阪に支店を展開し、メンタルヘルス不調の予防、発生対応から復職支援前の総合的なサポートプログラムを提供しています。
事業者向けには、メンタルヘルス関連業務に精通した産業医の紹介や、ストレスチェックの結果を踏まえた施策の立案、フォローアップなどを行っており、他社で実施したストレスチェックのデータでも分析対応します。
・ジェイズ・パシフィック
ジェイズ・パシフィック(愛知県名古屋市)は、愛知県名古屋市に「ルーセントメンタルヘルスマネジメント」を開設し、労働者個人へのカウンセリングと、事業者へのコンサルティングをサービスの柱として、メンタルヘルス不調の予防から復職支援、再発防止まで、トータルサポートを提案しています。
例えば、職場復帰が可能かどうかの審査を行う「職場復帰確認プログラム」では、臨床心理士による復職前面談、オフィスワーク(出勤を想定し、決められた期間、決まった時間に来所し、作業を行う)、顧問医による復職セカンドオピニオン(産業医資格を有する精神科医師による面談・助言)などを組み合わせ、事業者が対象労働者の復帰が可能かどうかの判断を行う材料を提供します。
・日本うつ病リワーク協会
日本うつ病リワーク協会は、うつ病などで休職している人の職場への復職支援を行う医療機関などで構成される業界団体です。加盟医療機関のうち、事業者からの相談を受け付けているところもあります。
例えば、養南病院(岐阜県海津市)は、「リワークセンターSMAP」を開設し、うつ病やうつ状態の患者を対象として、復職・再就職を支援するリワークプログラムを提供しています。SMAPは、S=職場に M=戻ろう A=アシスト P=プログラムの略称です。同病院は、事業者の人事担当者向けに直通ダイヤルを設け、相談を受け付けています。
メンタルヘルス不調者に対する実務上の対応で最も基本的なことは、正しい知識のない者が不用意な対応をしないことです。症状によっては、上司や同僚が悪意なく「頑張れよ」などといった言葉を掛けたのがきっかけで、重症化してしまうことも想定されます。
また、いわゆる「新型うつ病」の対応も難しいものです。新型うつ病は、従来のうつ病とは異なる、「抑うつ体験反応」などと呼ばれる逃避を特徴とする病態の総称で、仕事ではうつ傾向を示すものの、自分の趣味などプライベートに関しては積極的に活動する状態になります。そのため、新型うつ病についてよく知らない人には、ただ怠けているだけのように見えてしまう場合があります。
新型うつ病は、うつ病とは異なる対応が求められるといわれますが、専門的な知識のない者がうつ病と新型うつ病とを正確に見分けられるものではありません。現実的な対応は、医療機関で受診してもらうことです。しかし、本人に自覚がないなど、労働者が医療機関で受診することに対して前向きではない場合もあります。
そのようなとき、「病気かもしれない、受診してきなさい」などと病気であると決めつけるような言い方をすると、反発を招く恐れがあります。そのため、「最近遅刻やミスが多く、疲れているように見える。だから一度体調を診てもらったほうがいいと思う」など、受診を求める理由を伝えるなどの配慮が必要となります。
執筆=日本情報マート
【T】