
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
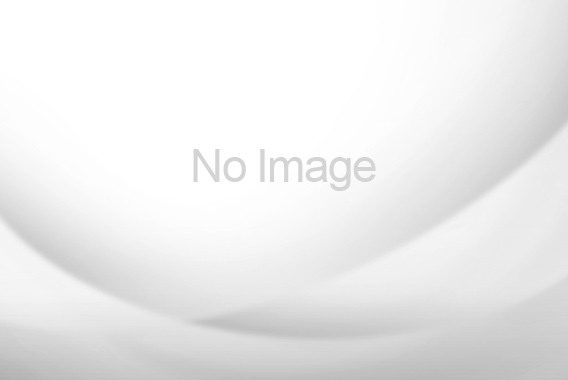
従業員の健康を守る知識や規則を紹介する連載の第2回は、新型コロナウイルス対策の続きです。前回は新型コロナウイルスや感染症について説明しましたが、今回は具体的な対策を解説します。
新型コロナウイルスは無症状者が感染を広めるため、熱があるなど発症が疑われる人だけでなく、すべての人が感染を広める前提での対策が必要です。
ワクチンとオミクロン型により、軽症化が進んできました。しかし、感染のしやすさは増加しています。感染すれば、無症状でも深刻な後遺症が出る危険があります。風邪やインフルエンザと同じには扱えず、決して感染したくない病気です。
ワクチンは、免疫の仕組みを利用します。一般に病原体に感染したときには、抗体がつくられます。抗体はその病原体の形を覚えていて、次に同じ病原体が体内に入ったときに、素早く攻撃態勢をつくります。
ワクチンは、弱毒化または死滅させたウイルスなどの病原体および病原体の成分を含む製剤です。それを接種すると、その病原体に対する抗体がつくられ、感染や重症化のリスクを下げます。
新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種が始まっています。5歳から11歳を対象としたワクチン接種も2022年1月に開始されました。ただ、5歳未満の子どもは2022年2月現在、接種できません。
一定の効果があるためワクチン接種が推進されますが、発熱など、数日間、強い副作用が現れる人が少なからずいます。経営者としては、ワクチン接種を推進すべく、ワクチン接種後、体調を崩してもゆっくり休めるよう、配慮しましょう。
ワクチンは、多くの人に一定の感染予防と重症化予防効果をもたらしますが、すべての人、そしてすべての変異型に効果があるわけではありません。有効期間も無限ではありません。
また、ワクチンを受けられない人もいます。抗体ができないなど免疫不全の人、ワクチンの成分に対するアレルギーがある人、心臓や腎臓、肝臓の疾患、あるいは血液疾患などの基礎疾患がある人などは受けられません。従って、従業員全員にワクチン接種を義務付けるといったことはできません。
感染と重症化を防ぐためには、ウイルスが体内に入る「曝露(ばくろ)」の量を減らすことが重要です。マスクの穴はウイルスよりも大きいのですが、ウイルスを含む飛沫がマスクの繊維に捕集されるため、曝露量を減らせます。
ただし、マスクさえ着けていれば安心なわけではなく、マスクを着けていてもクラスター(集団感染)は発生しています。適切なマスクを正しく着用しなければなりません。
マスクの捕集効果は、布やウレタンのマスクより、不織布マスクのほうが断然高いと分かっています。不織布マスクの中でも、ワイヤ入りのマスクを使い、きちんとワイヤを鼻の形に添わせて密着度を上げると、さらに予防効果が高まります。マスクはできるだけプリーツ型や立体型を用いて、必ず、鼻とあごを覆うように着けてください。
さらに、2枚のマスクを重ねて使うと効果が増します。不織布のマスクでぴったりと鼻と口を覆い、上からウレタンマスクなどで押さえて密着度を高めるのがお勧めです。しかし、不織布マスクは使い捨てでお金がかかるため、布やウレタンマスクを単体で使う人がまた増えています。接客業や、出勤が必要な企業では、従業員にマスク手当を支給したり、適切なマスクを配布したりするなどして、従業員と顧客の健康を守りましょう。
ウイルスは粘膜や結膜を介して体内に入ります。目は口や鼻のように吸引はしないためリスクは低めですが、目からの感染もあります。介護職など、他人との距離を空けられない職業などでは、できるだけゴーグルやフェースマスクで目も守るようにしましょう。
消毒で重要なのは「後」より「前」です。消毒後に何にも触れていなかったとしても、換気が悪い部屋などでは、浮遊しているウイルスを含む飛沫に手指が汚染されているかもしれません。粘膜や結膜を介して感染するので、顔などに触れる「前」、肩より上に手を持って行く「前」に手指を消毒するようにしてください。さらに気を付けるなら、トイレでは用を足す「前」に手指を洗うようにしましょう。
他人に感染させないためにも、「前」の消毒が効果的です。社内のドアノブをつかむ「前」や、複数人で使うコピー機などに触れる「前」に手指を消毒してもらうと、感染拡大の可能性を減らせます。ドアやコピー機などの近くに消毒液を置いて、使用前の消毒をしてもらうようにしましょう。
消毒はさっと手指にアルコールを吹きかけるだけでなく、手指をこすり合わせ、細かい所まできちんとアルコールを届けましょう。飲食の前には、さらに効果が高いせっけんでの丁寧な手洗いをしてください。新型コロナウイルスは、エンベロープと呼ばれる脂質の膜を持つ、エンベロープ・ウイルスの1つです。せっけんによって脂質を分解すれば、新型コロナウイルスを守る脂質の膜が壊され、ウイルスは分解されてしまいます。
人が集まる限り、クラスター(集団感染)のリスクはあります。コロナ禍にある現在だけでなく、今後の人材不足なども見据えて、出勤や出張などの移動時間をできるだけ削減して、業務の効率化を図るよう求められています。リモートワークを進めるためには、ITシステムの整備だけでなく、人事評価制度や教育制度など、さまざまな面の課題のクリアが必要です。最初の緊急事態宣言時は事前準備もなくリモートワークを始めたために、トラブルが起こり、リモートワークに懲りた企業もあります。しかし、新型コロナウイルスにより、人々の価値観は変わりました。できる限りリモートワークができる体制づくりに向けて動きましょう。
クラスターを生むリスクが特に高いのは、飲食です。接客業のみならず、一般企業でも打ち合わせなどで飲食物を提供するのは、コロナ以前は当たり前のサービスでした。しかし、現在は迷惑と感じる人も増えているので、控えましょう。
また、会議も感染リスクを高めます。10分に1回程度、こまめに換気しましょう。リスクの高い飲食をせずに済むように、会議は短時間にしてください。
体調不良を押して出社することが美徳とされるような社風があった企業は、意識改革が必要です。従業員自身はもちろん、家族の体調不良の際にも、休んだほうが企業にとって利益であるという意識を経営者自身はもちろん、社内でも徹底しましょう。
そもそも病気は医師が治すものではなく、患者自身の体力、抵抗力で治すものであり、治療はあくまでその手伝いです。体力があれば、たとえウイルスに曝露しても、感染や発症、重症化しないで済みます。普段から無理をせず、しっかりと睡眠と栄養を取って、体力を付けておくことが重要です。睡眠時間と風邪の関係を調べた研究では、1日7時間以上睡眠を取る人に比べ、6時間未満の人は4.2倍、5時間未満の人は4.5倍も風邪にかかりやすいという結果が出ています。できるだけ残業などをせず、適切に休みを取れる職場づくりを心掛けましょう。
執筆=森田 慶子
医療ライター。1996年から、主に医師をはじめとする医療関係者向けの専門的な記事を執筆。2005年から患者向けや一般向けの医療や健康に関する記事も執筆。特に糖尿病や高血圧といった生活習慣病と、睡眠や認知症、うつ病などの精神科領域を専門とする。
【T】