
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
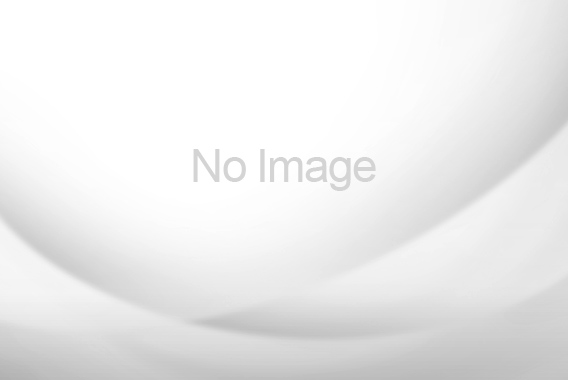
従業員の健康を守ることは経営者の重大な役割です。本連載では、そのために経営者が心得ておかなければならない知識や規則を解説します。最初に説明するのは、現在猛威を振るっている新型コロナウイルス対策です。第1回では新型コロナウイルスと感染症の基礎知識を紹介します。
「コロナ」と略されがちですが、今問題になっているのは新型コロナウイルスです。新型なので解明されていないことがまだ多くあります。新たな変異型が現れるたび、感染や重症化のリスクなど、状況が変わります。最新の専門家の発表など、正しい知識や情報を集め、変化していく状況に合わせた対応が必要です。
そもそもコロナウイルスとは何でしょうか? 王冠に似た構造から、ギリシャ語で王冠を意味するcoronaという名を付けられたウイルスです。人から人へ感染するコロナウイルスは7種類あります。一般的な風邪を引き起こす4種類のコロナウイルスと、2002年に中国広東省で発生して30以上の国と地域に感染が拡大したSARS(サーズ)と、2012年にサウジアラビアで発見されて30カ国弱の国と地域に感染が拡大したMERS(マーズ)、そして今回の新型コロナウイルスです。
新型コロナウイルス感染症の初期症状は、発熱やせき、くしゃみ、頭痛など、風邪と似ていて、自覚症状だけでは感染の判断が困難です。嗅覚異常や味覚異常が起こる場合もありますが、全ての人に起こるわけではありません。
新型コロナウイルスが風邪と大きく異なる点の1つが肺炎です。風邪では上気道、つまり鼻から喉までの炎症にとどまり、肺炎(下気道炎)を起こすことはほぼありません。コロナ前、肺炎の多くは肺炎球菌による細菌性肺炎で、患者の多くは高齢者でした。新型コロナウイルス感染症では、軽症者も含めて、患者の多数が肺炎になりました。オミクロン型で肺炎になる患者割合が減ってきたとはいえ、少なくはありません。後述するように、細菌とウイルスは異なるものです。ウイルス性肺炎は、細菌性肺炎よりも診断も治療も難しい面があります。
もう1つ風邪とは大きく異なるのが、軽症者どころか無症状だった感染者にも、かなりの割合で、深刻な後遺症が起こることです。呼吸器症状など、「なかなか治らない」と感じる長引く症状だけでなく、脱毛や脳の不調など、感染から数週間後に発症する後遺症もあります。
当初は「子どもは感染しない」と言われていましたが、現在は幼児も感染することが判明しています。特に持病のある子どもの場合、重症化リスクもあります。
感染とは、体内に入ったウイルスなどが体内に定着、増殖することです。新型コロナウイルスの感染は、主に飛沫感染、接触感染とされています。飛沫感染とはせきやくしゃみ、会話の際に飛んできた飛沫と共にウイルスを吸い込むと感染することです。
接触感染とは、感染者の口などへの直接接触、またはウイルスが付着したドアノブなどに触れた後、その手で目や鼻、口などに触れる間接的接触により、粘膜や結膜などを通じて感染することです。
新型コロナウイルスが空気感染するかどうかは、専門家の間で意見が分かれていますが、それには医学用語としての「空気感染」の定義が関わっていて、一般の人が「空気感染」という言葉からイメージする空気感染はあるものと考えてください。換気が悪い空間は感染の危険が非常に高いです。
新型コロナウイルスは発症の前後にウイルス排出のピークがあり、無症状者が感染させる点がやっかいな感染症です。常に、自分も感染していて、他人にうつす危険があるという前提で、行動することが求められています。
新型コロナウイルス感染症では、後遺症が大きな問題です。国立国際医療研究センター病院を退院した患者を対象とした、2020年の聞き取り調査では、発症から2カ月で半数近い人に、4カ月後でも3割近くの人に何らかの後遺症がありました。若くても、軽症でも、さらには無症状だった人にも後遺症が見られました。
主な後遺症は嗅覚障害や味覚障害、倦怠(けんたい)感、呼吸困難感などです。倦怠感と聞くと「たかがだるいくらい」と思いがちですが、通勤だけなのに会社に着いたらマラソンを走った後のようなつらさになり、横にならずにはいられないといった深刻なケースが多く見られます。
回復後に出現する遅発性後遺症としては、脱毛、記憶障害、睡眠障害、集中力低下などがあります。発症から1カ月後や3カ月後に症状が出るものもあります。
特に社会生活への復帰の障害となっているのが、「ブレインフォグ」です。脳に霧がかかったようになり、言葉がぱっと出てこなかったり、集中力がなくなったり、記憶障害が起こります。結果、仕事を続けられずに休職や退職するケースも出ています。
後遺症はワクチンを打つと軽減するケースもありましたが、逆に悪化するケースもあり、ワクチンとの関係はまだ解明されていません。多くの後遺症は、原因も治療法も見つかっていません。
新型コロナウイルスについて理解するために、多くの人が混同している細菌とウイルスについて説明します。細菌もウイルスも人間に役立つものと、感染症を引き起こす病原体となるものがあるという共通点もありますが、多くの点で全く別物です。
細菌は1ミクロン(1ミリメートルの1/1000)と、目に見えないほど小さな、1つの細胞しか持たない単細胞生物です。ウイルスはさらに小さく、新型コロナウイルスはわずか0.1ミクロンです。ウイルスには細胞がなく、他の生物の細胞に入り込んで増殖していきます。人体に侵入したウイルスは、人の細胞の中に入り、自分のコピーを作らせて増殖します。単独では増殖できないため、生物ではないとされています。
風邪を引いたときは、抗生物質で治すものだと思っている人が少なくありません。抗生物質とは抗菌薬の一種で、その名の通り、細菌と戦うための薬です。しかし、風邪を引き起こす病原体の約9割がウイルスであり、抗生物質では風邪を治せません。そもそも風邪の治療薬を作ったらノーベル賞ものと言われているくらいで、いまだ風邪を治す薬はありません。
日本では、医師に薬の処方を求める患者が多いこともあり、「ウイルス性の風邪ではなく、万が一、細菌感染症だった場合のため」と、不要な抗菌薬が「念のため」処方されがちです。その結果、日本では薬に強い耐性菌が非常に増えてしまっています。
風邪薬は解熱剤やせき止めなど、全て対症療法の薬です。医師をはじめとする多くの医療関係者は、風邪を引いても、基本的に風邪薬を飲みません。対症療法の風邪薬を飲むことで、しばしば風邪が治るのを遅らせてしまうからです。感染症になったときに熱が出るのは、病原体が苦手とする高温にするためです。せきやくしゃみ、鼻水は体内の病原体を体外に排出しています。解熱剤やせき止めは、人体が病原体と戦う働きの邪魔をします。
ただし、医師が風邪の患者に解熱剤などの対症療法の薬を処方することがあります。それは高熱が続き過ぎたり、せきで眠れなかったりすることにより、患者の体力が落ちてしまう場合です。医師は症状を抑えるメリットとデメリットを比較して、メリットが大きいときのみ、薬を処方します。
新型コロナウイルス感染症の治療薬として現在承認されている薬も、対症療法の薬とウイルス増殖を抑える薬です。
執筆=森田 慶子
医療ライター。1996年から、主に医師をはじめとする医療関係者向けの専門的な記事を執筆。2005年から患者向けや一般向けの医療や健康に関する記事も執筆。特に糖尿病や高血圧といった生活習慣病と、睡眠や認知症、うつ病などの精神科領域を専門とする。
【T】