
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
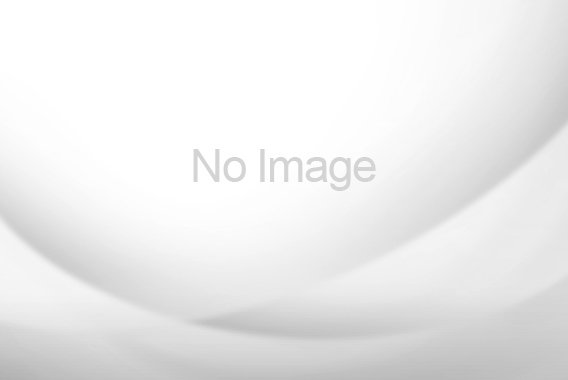
農業支援外国人材を活用するには、労働時間や休暇に配慮し、適切な住居を用意するだけでなく、人材を派遣する事業者に必要な通知・報告をする必要もあります。さらに、場合によっては監督機関から現地調査を受けることもあり得ます。こうして受け入れた外国人の労働期間は通算3年。この期間をいかに実のある時間とするのか農業経営体の工夫が問われます。
前回、外国人材の派遣を受けるための要件として図表1を挙げ、4の労働時間・休暇・休日についての課題を説明し、5の住居についていかに詳細な規定があるのかを説明しました。
■図表1 外国人材の派遣を受け入れるための要件
| 1 | 外国人を過去5年以内に少なくとも6カ月以上雇用した経験があるか、または、労働局が実施する派遣先責任者講習を受講した者を責任者に据えていること |
| 2 | 過去5年以内に労働基準法、出入国管理法に違反したなどの欠格事由に該当していないこと |
| 3 | 外国人材と同じ作業などに従事する労働者をその意思に反して退職させたことがないこと |
| 4 | 外国人材の労働時間・休憩・休日に配慮していること |
| 5 | 住み込みで働く場合には、外国人材の住居内の生活環境に配慮していること |
| 6 | 派遣事業者に対する必要な通知・報告を行うこと |
| 7 | 「適正受入管理協議会」による現地調査を受け入れること |
| 8 | この事業の適切な実施に必要な法令(出入国管理法、労働基準法、労働者派遣法)に基づく措置を行っていること |
そして、受け入れる農業経営体は、こうした要件をクリアするだけでなく、6にあるように派遣事業者に通知・報告をする必要があります。まず、1カ月に1回、通知を行う事項は次の通りです。
・外国人材の氏名
・実際に農作業などに従事した日
・作業従事日ごとの始業・終業時刻および休憩時間
・従事した農作業などの内容
・農作業などに従事した場所
さらに、3カ月に1回は、次のことも報告しなければなりません。
・外国人材と同じ作業などに従事する日本人従業員についての新たな雇用人数など
・外国人材の農作業以外の作業への従事状況、勤務・生活態度など
・外国人材と同じ業務に従事する日本人従業員の就労日数
・外国人材からの苦情・相談件数とその内容
・1カ月当たりの最長労働時間数、最少休日日数、休暇の付与・取得の状況
・健康診断の実施の有無、労働災害の発生の有無など
7の「適正受入管理協議会」とは、関係自治体と内閣府地方創生推進事務局、地方入国管理局、都道府県労働局、地方農政局とで構成され、派遣事業者や農業経営体に対する監督や指導を行うための機関のことです。
農業経営体からの報告は、派遣事業者を通して、この「適正受入管理協議会」に報告され、その報告内容などに関して確認が必要と判断した場合には、「適正受入管理協議会」が農業経営体に対する現地調査を行います。
8については、当然ながら、暴力・脅迫などは刑法犯になりますし、パスポート・旅券の取り上げ、報酬の未払いなどがないようにしなければなりません。このようなことがあれば以後、外国人材の派遣を受け入れることができなくなるのは当然、処罰の対象ともなります。
この特区事業における外国人の労働期間は「3年」です。「3年」のカウントは、通算です。つまり、3年間継続して働くこともできますし、例えば半年働いて半年帰国して、また来日後、半年働いて、というような形で、通算して3年間働くことも可能です。
特区事業における外国人は就業形態が派遣ですので、同じ農業経営体の下でなく、複数の農業経営体の下で働くことも可能です。また、例えば、ある農業経営体が近所の田畑の農作業の委託を受けている場合には、その作業(受託業務)に外国人を従事させても構いません。ただし、受託契約書面がきちんと結ばれていることと、その委託者が外国人に作業指示など(指揮命令)をしないことなどが必要です。
特に、「その委託者が外国人に作業指示など(指揮命令)をしないこと」は、重要です。その作業指示をしてしまうと、結局のところ、いったんある農業経営体が外国人の派遣を受け入れているにもかかわらず、別の所に再派遣しているのと同じことになり、二重派遣になってしまいます。この二重派遣は、職業安定法第44条で禁止されており処罰(1年以下の懲役、または100万円以下の罰金)の対象です。
農業分野における外国人の受け入れは、特区事業によるもの以外に、外国人技能実習制度の活用も考えられます。この2つを比較してみましょう。特区事業は農業の強化のための必要な労働力の確保が目的とされているのに対し、外国人技能実習制度は、あくまでも外国人に対して技術・技能を教えることによる国際協力が目的です。むしろ、技術移転による国際協力以外の労働力の需給調整の手段としてはならないとされています。
特区事業は、特定機関(派遣元)が受け入れ、複数の農業経営体へ派遣することが可能となっています。外国人技能実習制度は、1つの農業経営体が受け入れます。ただし、JAなどが受け入れる場合には、その組合員などの作業を請け負うことは可能です。
■図表2 派遣事業者(特定期間)側の要件
| 1 | 外国人材、またはその家族などから、保証金などの徴収をしてはならない |
| 2 | 受け入れに際して他の機関が関与する場合、その機関は、外国人材、またはその家族などから、保証金などの徴収をしてはならない |
| 3 | 外国人材に対し、次の項目について、必要な研修を実施すること |
| ・農作業などに関する教育訓練(農業の基本的な知識、機械の構造・操作に関する知識などの研修) | |
| ・日常生活・農作業などに必要な日本語(買い物や交通機関の利用、近隣住民とのコミュニケーション、派遣先などとのトラブル時や身を守るための対応、警察や消防への通報など、農業現場での機械、資材などの専門的な用語など) | |
| ・ 理解しておくべき関係法令(在留カードに関する手続き、再入国許可手続き、在留期間の更新手続き、退去強制事由などの注意事項に関する研修) | |
| ・苦情・相談窓口(就労や生活に関する苦情・相談「転職に係る相談を含む」を受ける窓口の研修) | |
| 4 | 外国人材が安心して日常生活を営むために必要な支援を適切に実施すること(「必要な支援」とは、例えば、居住地周辺の医療機関、行政機関、金融機関などに関する各種情報の提供や、それらの機関におけるサービスを利用するに当たっての同行など) |
特区事業は、あくまで仕事ですので、農作業や農畜産物などを使用した製造・加工・運搬・陳列・販売なども行います。外国人技能実習制度は、実習ですので、2年目以降は、従事できる職種作業が限定されています。在留期間については、特区事業は通算で3年なのに対し、外国人技能実習制度は、最長5年ですが、期間内に出たり入ったりというような形態は取れません。
執筆=小澤 和彦
弁護士法人 後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士。第二東京弁護士会の西東京市男女共同参画推進委員会委員長。業務分野は企業法務、知的財産など。主な著作として「相続戦争を勝ち抜く85のルール―相続財産の分配で、モメそうなときに読む本」(九天社)など。
【T】