
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
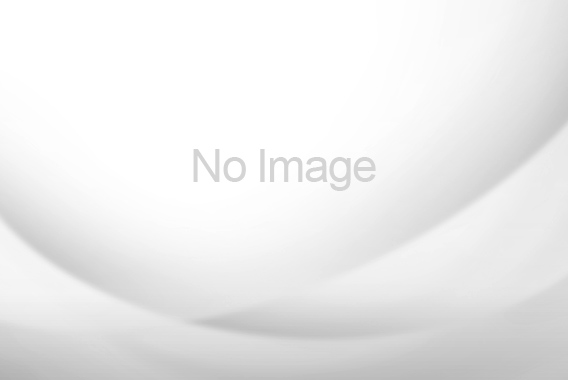
後継者、就労者不足、高齢化で衰退が叫ばれる農業。その新たな担い手として注目されるのが外国人材です。ただし、農業支援人材として外国人を活用するには、受け入れる農業経営体にさまざまな要件が課せられます。農業では難しい労働時間、休暇、休日への配慮が求められるほか、住居についても詳細な規定があるので注意が必要です。
「国家戦略特区」という言葉を耳にしたり、新聞などで目にしたりしたことは少なくないのではないでしょうか。最近は、それほどメディアに出てきませんが、「国家戦略特区」とは、ビジネスを行いやすい環境を整えることにより経済を活性化させようとする目的で、2013年に制定された特区法(国家戦略特別区域法)により指定された地域のことをさします。
そして、特区法と関連法により、規制改革、制度支援、税制優遇などが定められています。規制改革のメニューの中には、都市再生、創業、観光、医療、介護、保育、雇用、教育、農林水産業、近未来技術などがあり、それらの1つに「外国人材」もあります。
そして、「外国人材」に関する規制改革事項としては、農業支援外国人材、家事支援外国人材、創業外国人材、クールジャパン外国人材、外国人雇用相談、高度人材ポイント制があります。この中の農業支援外国人材について説明します。
農業支援での外国人受け入れの規制改革は、後継者、就労者不足、高齢化で経営衰退が叫ばれる中(図表1参照)、経営規模の拡大などによる強い農業を実現し、国内自給率を高めるために、一定水準以上の技能などを有する外国人の入国・在留を認めるものです。もちろん、外国人の人権に配慮することなども、その内容としています。
■図表1 農業従事者は年々高齢化
| 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|
| 基幹的農業従事者数(万人) | 240 | 224 | 205 | 168 |
| 平均年齢(歳) | 62.2 | 64.2 | 66.1 | 66.8 |
出典:農林水産省ホームページ
農業の場合には、直接外国人を雇用し続けるほどの体力がない法人・農業経営体が多いことや、季節により就業内容が大きく異なることなどにより、直接契約(直接雇用)を義務付けると、制度利用が促進されない恐れがあります。
そこで派遣事業者(特定機関、本事業に即した要件を満たす厚労省の許可を受けた派遣事業者)が各農業経営体に、外国人を派遣する形態を取ります。これにより、農業経営体は、必要な時期に必要な人数の外国人の供給を受けることが可能となりますし、他方で、外国人にとっても安定・継続した雇用が確保されることになります。
外国人の適切な労働環境を握るカギはなんといっても、雇用主である派遣事業者と実際に労務を提供する農業経営体にあります。図表2の中の4で問題となるのは、実は農業では、労働基準法上の労働時間・休憩・休日の規定が適用されないことです。
■図表2 外国人材の派遣を受けるための要件
| 1 | 外国人を過去5年以内に少なくとも6カ月以上雇用した経験があるか、または、労働局が実施する派遣先責任者講習を受講した者を責任者に据えていること |
| 2 | 過去5年以内に労働基準法、出入国管理法に違反したなどの欠格事由に該当していないこと |
| 3 | 外国人材と同じ作業などに従事する労働者をその意思に反して退職させたことがないこと |
| 4 | 外国人材の労働時間・休憩・休日に配慮していること |
| 5 | 住み込みで働く場合には、外国人材の住居内の生活環境に配慮していること |
| 6 | 派遣事業者に対する必要な通知・報告を行うこと |
| 7 | 「適正受入管理協議会」による現地調査を受け入れること |
| 8 | この事業の適切な実施に必要な法令(出入国管理法、労働基準法、労働者派遣法)に基づく措置を行っていること |
日本人でも適切な労働環境を整えるのが難しいとされているところで、外国人の労働時間などをどのように定めるかというのは非常に難しい問題なのです。「日本人は休んでいいのに、外国人は休んではいけない」などという差別的な取り扱いが認められないのは当然のことですが、そもそも、そこで働く日本人も含めた労働者の労働時間・休憩・休日について、「適切に」なるように配慮しなければならないとされています。何が「適切か」の答えはありません。
5の「外国人材の住居の要件」として、次のように具体的に定められています。
・火災による危険の大きい物の貯蔵場所、衛生上有害な作業場などの付近を避けること
・寝室が2階以上にある場合は、容易に屋外に通じる階段を2カ所以上設けること
・消火設備を設置していること
・寝室は、1人当たり4.5平方メートル以上で、収納や採光・採暖の設備を設けること
・就寝時間の違う外国人材が2組以上いる場合は、寝室を別にすること
・食堂・炊事場は、照明・換気を十分に行い、食器などを清潔に保管し、害虫などを防ぐこと
・トイレ、洗面所、洗濯場、浴場を設け、清潔にすること
・住居が労働基準法の「事業の附属寄宿舎」に該当する場合は、寄宿舎規則の届け出など、同法の規定を守っていること
また、農業経営体の住居に住み込みをさせる場合には、次の要件も具備する必要があります。
・事前に外国人材の同意を得る
・同じ住居で生活する日本人従業員と同等以上の生活環境を整える
執筆=小澤 和彦
弁護士法人 後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士。第二東京弁護士会の西東京市男女共同参画推進委員会委員長。業務分野は企業法務、知的財産など。主な著作として「相続戦争を勝ち抜く85のルール―相続財産の分配で、モメそうなときに読む本」(九天社)など。
【T】