
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
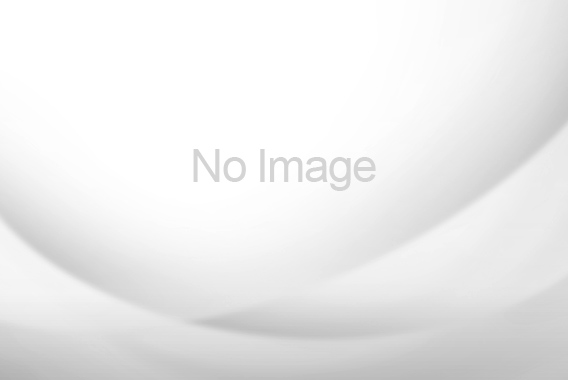
2020年は新型コロナウイルスに始まり、新型コロナウイルスで終わった年となりました。と同時に、社員が新型コロナウイルスに感染することを防ぐために、在宅勤務制度を採用する会社が一気に増えました。それまで在宅勤務にあまり積極的でなかった会社も、在宅勤務を取り入れなければならない風潮になってきたのではないでしょうか。とはいえ、あまりに急な対応を迫られたため、在宅勤務に関する情報も十分とはいえず、またその内容が不完全であった会社も多かったことと思います。
また、この在宅勤務について、長時間労働の温床となっているというニュースも増えてきています。しかし、この在宅勤務制度は、社員の体力と時間を浪費する通勤を削減することができるうえ、うまく使えば、長時間労働を是正するツールになる可能性もある制度といえます。では、在宅勤務をどのように活用すれば長時間労働を是正できるのでしょうか。考えてみましょう。
●事例1 仕事と家庭のバランスが取れない
A社の社員Bは、在宅勤務を行っているのですが、小学校に上がる前の子どもがいるため、仕事になかなか集中できないでいます。そのため、子どもが寝静まった夜に仕事をすることが多くなり、必然的に寝不足が続いています。
在宅勤務のほとんどは、社員の自宅で行われます。社員の自宅で仕事を行うということは、「家庭」を身近に感じながら仕事を行うということです。家族の世話だったり、テレビなどの誘惑だったり、家庭の雑務だったり、どうしても仕事と私的なこととの境目が見えにくくなり、労働生産性が下がることになります。仕事と家事のけじめがないまま、ダラダラと1日を過ごしていているようでは、無駄な労働時間が増えてしまうだけです。
このようなことがないように在宅勤務規程に、始業時刻と終業時刻、休憩時間をしっかり規定しておく必要があります。
また、会社や上司からメールや電話が来ると、社員は義務感から仕事をしてしまうものです。在宅勤務者に対し、始業時刻前や終業時刻後にメールや電話などをすることは、よほどの緊急事態でない限り控えるようにしましょう。
■在宅勤務規程の「労働時間」の規定例
第〇条(労働時間)
1.在宅勤務時の労働時間については、就業規則に定める下記の所定労働時間について勤務したものと見なす。
始業時刻:9時 終業時刻:18時
2.第1項に関わらず、会社の承認を受けたときは、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を変更することができる。
3.休憩時間については、就業規則に定める下記の通りとする。
休憩時間:12時~13時(1時間)
4.会社は、原則として、始業時刻前及び始業時刻後に連絡をしないものとする。ただし、緊急を要する事項についてやむを得ず連絡する場合はこの限りでない。
■在宅勤務規程の「業務の開始及び終了の報告」の規定例
第〇条(業務の開始及び終了の報告)
在宅勤務者は、業務を開始したとき及び終了したときは、次のいずれかの方法により所属長に報告しなければならない。
(1)電話
(2)電子メール
(3)SNS
(4)その他の情報ツール
●事例2 成果を出すのに必死にならざるを得ない
C社の社員Dは在宅勤務をしています。始業時刻と終業時刻は決められているのですが、時間通り働いても、何ら成果を上げることができなければ、上司に何もしていなかったと思われるのではないかと不安になっています。そのため、会社に出社して働くよりも在宅勤務のほうが、肉体的にも精神的にもきつい状況に陥ってしまいました。
在宅勤務は、会社にとっては社員の管理がしにくい制度です。これは社員から見れば、労働の成果を見せにくい制度ともいえます。会社に出社していれば、決められた労働時間を働いていれば、取りあえず仕事をしていると見なされます。
しかし、在宅勤務ではそういうわけにはいきませんから、真面目な社員ほど「成果を出さなければ」と、必死になることになります。日本人は、どうしても「会社=仕事」、「家庭=休み」というイメージが強く、これが長時間労働を助長する結果となってしまいます。
まずは在宅勤務規程において、「原則として時間外労働や休日労働を認めない」旨を規定し、そのうえで、どうしても時間外労働や休日労働が必要な場合は、あらかじめ所属長の指示を仰ぐような制度にしておくことがポイントとなります。
また、社員の1日の業務の成果が分かるように「業務報告書」を用意し、その日の成果を報告してもらう仕組みをつくっておきましょう。
■在宅勤務規程の「時間外労働及び休日労働」の規定例
第〇条(時間外労働及び休日労働)
1.原則として時間外労働及び休日労働は認めない。
2.やむを得ない事由で時間外労働及び休日労働を行う場合は、事前に電話又はメールなどにより、所属長の指示を受けるものとする。
■宅勤務規程の「業務報告」の規定例
第〇条(業務報告)
在宅勤務者は、所定の「在宅勤務業務日報」又は「業務週報」を所属長に提出し、自己の業務の進捗状況などを会社に報告しなければならない。
●事例3 チーム内で意思の疎通が取れていない
E社の社員Fは在宅勤務を命ぜられ、自宅で仕事をしています。現在、プロジェクトチームの方向性が見えないため、「ああでもない、こうでもない」と、考え悩んでいます。その結果、毎日、夜遅くまで仕事をせざるを得なくなっています。
部署やチームの意思統一、情報の共有ができていないと、やらなくてもよい仕事をやってしまったり、同じ仕事を複数の人が行ったりして、労働生産性が落ちる結果になります。
インターネットが発達した昨今、WEBで行われる会議は当たり前のものとなっています。定期的にWEBでの会議を開くことにより、部署やチームの意思統一や情報の共有を行いましょう。そのためにも、自宅にWi-FiやWEBカメラなどの情報通信機器の用意がある者に対してのみ、在宅勤務を認めることが重要です。また、このWEB会議についても、やむを得ない事情がない限り、就業時間内に行わせるようにしましょう。
■在宅勤務規程の「在宅勤務の定義」の具体例
第〇条(在宅勤務の定義)
在宅勤務とは、社員の自宅、その他自宅に準ずる場所(会社指定の場所に限る)において情報通信機器を利用した業務等をいう。
■在宅勤務規程の「WEB会議」の規定例
第〇条(WEB会議)
1.WEB会議は、原則として、就業時間内に行わなければならない。
2.やむを得ない事情により、始業時刻前又は終業時刻後にWEB会議を行う場合は、あらかじめ所属長の承認を得るものとする。
■在宅勤務規程の「適用範囲」の規定例
第〇条(適用範囲)
1.本規程において「在宅勤務者」とは、原則として全日の在宅勤務を行う社員をいう。
2.在宅勤務は、在宅勤務を希望し、自宅の執務環境、セキュリティ環境のいずれも適正と認められる者のうち次の条件のいずれかを満たす者に適用する。
(1)社員が申請をし、所属長の承認を得た者
(2)感染症が流行しているときに会社の指示を受けた社員
(3)その他会社が必要と判断した者
●事例4 ルールがよく分かっていない
G社の社員Hは、上司から在宅勤務を命じられましたが、何をどうしていいか分らず、家でパソコンに向かっているだけです。在宅勤務をする際のルールのようなものがほしいと考えています。
事例1から事例3にも書いた通り、まず会社としてやるべきことは、在宅勤務のルール作りです。会社は「在宅勤務規程」のようなものを作成し、社員全員に周知させる必要があります。そのうえで、例えば社内報などを作成し、「原則として時間外労働や休日労働は禁止であること」や「在宅勤務を行う際のさまざまな手続き」など「在宅勤務をする場合の注意点」を社員に明示、周知する必要があります。
在宅勤務制度は、最近長時間労働の温床になっているようにいわれがちですが、うまく使えば、通勤時間もなくなりますし、労働生産性も上がり、労働時間の削減にもつながります。長時間労働を防ぐためには、「会社=仕事」、「家庭=休み」という旧態依然とした認識を変えることから始めなければなりません。そのうえで在宅勤務規程を整備し、社員が安心して在宅で勤務できるような制度にしていきましょう。
執筆=嘉瀬 陽介
1963年、秋田県生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。2003年、横浜で社会保険労務士事務所を開業。2006年、特定社会保険労務士の附記を受ける。社会保険労務士の業務と並行して児童文学の執筆をしている。趣味はスポーツをすることとドラマを見ること。
【T】