
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
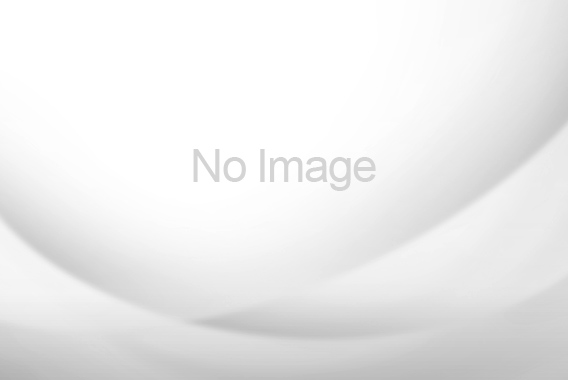
従業員が時間外労働をした場合、賃金を割り増しして支払う必要があることは、日本の経営者も労働者もよく知っている。時間外労働の際の割増率を、労働基準法では「法定割増賃金率」として、月60時間以内の時間外労働について25%以上とすることが定められている。このあたりまでは多くの人が理解しているところだろう。
法定割増賃金率は、2010年の労働基準法の改正で一部引き上げられ、月60時間を超える時間外労働では25%から50%へと改正された。と言ってもこれは大企業が対象の話で、中小企業には猶予措置があり25%に据え置かれていた。ところがこの猶予措置が、働き方改革関連法によって終了することになった。2023年4月からは、月60時間を超えた時間外労働について企業規模にかかわらず一律50%の割り増しが必要になる。
月60時間を超える時間外労働が不可欠なケースでは、従業員に適正な割増賃金を支払うことで適正な労働対価を提供できるようになるだろう。一方、経営者から見れば、従業員が本当に必要な仕事を効率的に行っているのかなかなか判断しにくい。しかし、仕事の仕方を変革して効率的に業務を終わらせ、時間外労働を減らしたい(=割増賃金を減らしたい)という思いは強いはずだ。
従業員側でも、長時間労働をするような職場環境は以前よりも好まれなくなっており、効率的に仕事をして残業を減らし、ワークライフバランスを保った生活を送りたいという考え方は強くなっている。
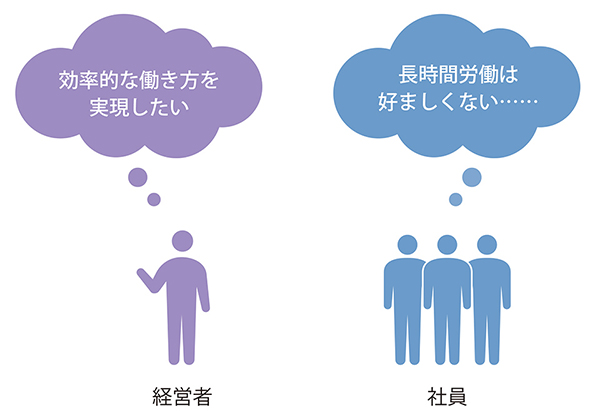
業務効率化を実現するにはどうしたら良いのだろうか。その1つの方法が、業務可視化ツールの活用である。労働の実情が分からないままでは、対策の施しようがないからだ。特にパソコンを使った業務は誰が何をしているのかを把握しにくい側面もある。これらを可視化して棚卸しできるのが業務可視化ツールというわけだ。
主な機能は、パソコンなどのデジタルデバイスを使った業務の作業内容ログを記録し、業務時間実績を把握すること。その上で、ログから作業の繰り返しや重複を分析して業務内容を丁寧に可視化する。可視化した分析結果を元にして、業務効率化に向けたアクションが起こせるという流れである。例えば、繰り返し作業をRPAなどの自動化ツールに移行したり、重複作業を業務フロー改善によって集約することで無駄を省いたりできるようになる。
業務の可視化を進めることは、ビジネスコミュニケーションの見直しにもつながる。業務の重複が実は日常的にコミュニケーションを取ることが少ない部署間に発生していた場合、チャットツールなどを導入しコミュニケーションの活性化を図ることで業務を効率化できるケースもある。
時間外労働の法定割増賃金率がアップすることをきっかけに、業務の棚卸しを実現できれば、企業にとってもメリットは大きい。業務可視化ツールなどを使って業務の無駄や重複を浮き彫りにすることで、長時間労働の是正にも役立つだろう。今まで「見える化」されていなかった働き方を、デジタルツールで可視化・分析して、業務の変革につなげていくデジタルトランスフォーメーション(DX)の第一歩と言える取り組みだ。
常態的な長時間労働は、現在の従業員を疲弊させるだけでなく、将来の従業員募集にも悪影響を与えかねない。業務効率化が進んで長時間労働の懸念が少ない職場のほうが、今後の求人には有利に働くためだ。さらに、業務可視化によって、不用意なデータの持ち出しや、その先にあるデータの盗難・紛失といったセキュリティ面のリスクを減らすこともできる。業務可視化ツールのようなデジタルツールを適用することで、これまで対応できなかった業務上の課題に解決策が見えてくる可能性は少なくない。
企業が成長するためにはDXが不可欠だと言われるが、DXとは最先端のITシステムやAI(人工知能)の助けを借りることだけを意味するものではなない。セキュリティ対策の拡充や人材不足への対応、そして長時間労働の是正など、自社の抱える事業に応じて広い視野でデジタルツールを上手に適用し、業務変革につなげる視点・発想を持つことが、今後の企業成長に欠かせない。
執筆=岩元 直久
【MT】
“新常態”に対応せよ