
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
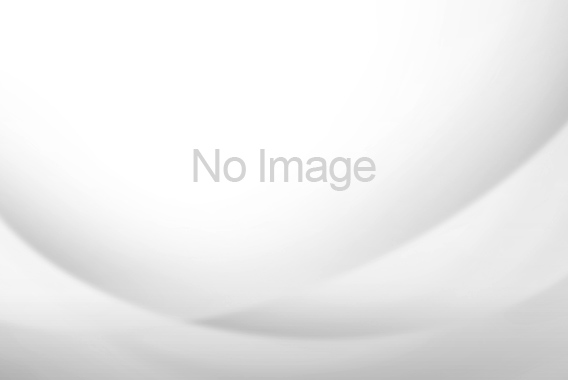 「わずかな食料と最低限の道具だけで、無人島で3日間暮らす」という、過酷な研修を行っている企業があります。「チキンラーメン」「カップヌードル」でおなじみの日清食品ホールディングスです。
「わずかな食料と最低限の道具だけで、無人島で3日間暮らす」という、過酷な研修を行っている企業があります。「チキンラーメン」「カップヌードル」でおなじみの日清食品ホールディングスです。
同社がこのようなサバイバル研修を行う理由としては、肉体的・精神的な「骨太さ」を身に付けるためです。困難にくじけない強さを培うだけでなく、自社商品への愛着まで深める狙いもあるといいます。
瀬戸内海に浮かぶ、電気も通らない無人島でのサバイバル研修に挑む社員に与えられるのは、わずかな食料と最低限の道具だけ。食料は同社のヒット商品であるチキンラーメン3袋と、水、米、小麦粉、道具も釣り糸と釣り針、ビニールシートとひも、そして火起こし器です。
さらにいえば、スマートフォンや時計、ライターといった私物は無人島に持ち込むことはできません。そのため、ネットで情報を調べる、時刻を知るといった、日常生活であれば簡単なこともできなくなります。
火もわざわざ火起こし器を使う必要があるため、チキンラーメンを作ることでさえも困難になります。落ち葉を集めて、火起こし器でわざわざ点火をしなければいけませんし、鍋や器の代わりとなるようなものを用意する手間もあります。火がおこせない場合は、チキンラーメンをそのままポリポリと食べるしかありません。
実はこの研修、「管理職の新人」に向けた研修の1つです。日清食品ホールディングスでは、「1人で生き抜く力」を養い、身体的・精神的に骨太な管理職を育成するために、このような大自然の中でのサバイバル研修を実施したとしています。
確かに、身体面でも精神面を鍛えるには、無人島は最高の環境かもしれません。先ほど触れたように、食料はわずかほどしか与えられないため、足りない食料を補うためには自力で調達するしかありません。ですが、釣りをするにしても、用意されている道具は釣り糸と釣り針だけ。これらを拾った棒にくくり付けて、自作の釣り竿を作る必要があります。
もちろん、釣り竿ができたとしても、魚が確実に釣れるとは限りませんし、釣れたとしても、火をおこして焼く手間があります。「食」に関する度重なる障壁の連続に、参加者は精神的な負荷を感じることでしょう。
体力面でも負荷があります。研修は9月に実施されるため、参加者は晩夏の日差しにさらされることになります。しかも、布団やベッドもないため、ゆっくりくつろぐこともままなりません。特に雨や風が厳しい場合は、シートを活用してうまくしのぐことが求められます。
無人島は、あらゆる場面で創意工夫をしなければならない、ビジネスの現場以上に困難な環境なのです。
日清食品では、この研修について「食の大切さを再認識する」目的もあるとしています。
無人島では、「食べる」ために多大なる労力が必要になります。前述の通り、魚を釣っても焼かなければ食べられませんし、生で食べるにしても魚をさばくための包丁やまな板もありません。また、野草を採取しても湯が沸かなければおいしく食べられませんし、そもそも湯を沸かすのも一苦労です。
参加者は、当たり前に入手できる「食」が文明の力で成り立っているということと、食材から食べられる状態にするまでにさまざまな過程があり、食品ビジネスはその過程から生まれたものであることを、研修で改めて実感することになります。研修終了後には、手軽に食べられるチキンラーメンのありがたさを知り、自社製品に愛着を深める参加者もいたようです。
参加者は無人島での過酷なサバイバル研修の中でどう切り抜けるか、アイデアを生み出し、トライアンドエラーを繰り返す自分に気付くはずです。それも、この研修の目的の1つです。
ビジネスリーダーの中には、従業員の解決能力の乏しさに頭を悩ませている人も多いかもしれません。困難に直面しても自力で解決できず、ただ困ってばかりの社員では、激しく環境が変わり続けるビジネスの現場で、結果を出し続けることは難しいでしょう。逆に、こうした困難な状況でも、やり抜く気持ちを失わず、苦境を切り抜ける発想力を持った人材こそが、ビジネスを支える人材といえそうです。
無人島研修の参加者の中には、島に生えている竹を使って食器を作ったり、小麦粉をこねてうどんを作ったりするといった人もいたそうです。もし、難題を課しているのにもかかわらず、自らアイデアを出して解決しようとする従業員なら、事業が困難な局面を迎えたときにも、諦めずビジネスを続けようとする人材へと育っていくかもしれません。
執筆=風間 梢
フリーライター。企画、人事、ECサイト運営などを担当したのちに独立。現在は就職、流通、IT、観光関連のコラムやニュースなどを執筆している。
【T】