
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
オフィスには電話やパソコン、サーバーなどさまざまな情報通信機器が備えられ、円滑な業務を支えている。万一、情報通信機器が使えなくなれば、取引先との連絡や業務に支障を来し、場合によっては事業継続にも影響を与えることになりかねない。
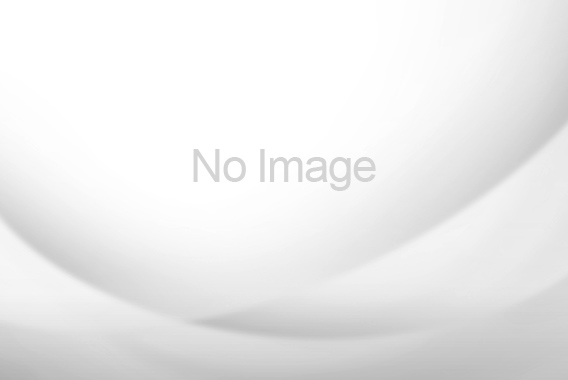 こうした事態を防ぐためには、まずトラブルの原因を理解し、適切な対策を講じる必要がある。トラブル要因は、情報通信機器の故障や人為的な操作・設定ミス、停電による電源障害、災害などさまざまだ。これらの中で、ちょっとした予算措置で“備えあれば憂いなし”となるのが停電対策だ。
こうした事態を防ぐためには、まずトラブルの原因を理解し、適切な対策を講じる必要がある。トラブル要因は、情報通信機器の故障や人為的な操作・設定ミス、停電による電源障害、災害などさまざまだ。これらの中で、ちょっとした予算措置で“備えあれば憂いなし”となるのが停電対策だ。
工場などの生産施設では、自前の発電設備を備えることがある。だが、オフィスビルでは外部から電力会社が電気を供給するのが一般的だ。災害や事故で、その供給がストップするのが「停電」である。また、オフィスビルでは、設備などの定期的な法定点検で一定時間、電源供給が停止されるときがある。法定点検は休日に行われることが多く、事前に通知されるので突然の停電と事情が異なるが、休日にも業務を行うオフィスでは注意が必要だ。
停電時の対応のために、独自の非常用電源設備を備えるオフィスビルもある。ただ、電力供給は、防災設備、避難設備、保安設備、非常用エレベーターなどに対して行われる場合がほとんどだ。テナントが借りているオフィススペースのパソコンやサーバー、ビジネスフォンといった情報通信機器への電源供給は、テナント自身で無停電電源装置(UPS)と呼ばれる設備を用意しなくてはならないのが一般的だ。
ビジネスフォンやパソコン、サーバーなどの情報通信機器にUPSが必要なのは、予期しない停電や電圧が瞬間的に低下する瞬時電圧低下(瞬低)により、システムが異常停止し、最悪の場合はデータの消失や機器故障のリスクがあるからだ。停電から復旧したとしても、消失したデータや故障した機器を復旧させるのが困難だったり、多額の費用を要したりすることになるので、事業継続を考えれば停電対策は必須といえるだろう。
オフィスに普及したビジネスフォンの弱点として、停電で使えなくなるところが挙げられる。以前のアナログ回線を使った固定電話は、電話線を通じて給電されていた。だから停電時でも、電話が使えなくなることはなかった。だが近年ビジネスフォンなどはデータ通信系と統合されて、1本の光回線に接続されているケースがある。その場合、電源が断たれてルーターなどの通信機器がダウンすると通話ができなくなってしまう。
もし、停電により取引先との電話が不通になっても、相手は事情が分からない。こうしたリスクを減らすために、導入を検討すべきなのがUPSである。無停電電源装置という呼称から誤解されがちだが、停電している間電力を供給し続けるわけではない。突然の停電や瞬低が発生したときに、一定時間、電力を供給する装置だ。
通話中であれば、相手先に「停電になったので電話を切らせていただきます」と失礼のないように事情を伝える時間や、パソコンやサーバーなどの情報機器をきちんと手順通りにシャットダウン操作するための時間を確保できる。
ビジネスフォンのほか、数台のパソコン、サーバーなどがネットワークに接続された小規模なオフィス環境の場合、常時商用給電方式またはラインインタラクティブ方式のUPSが選択肢になる。常時商用給電方式は、通常時は商用電源から給電し、停電時には蓄電池からインバーターを通じて給電する。ラインインタラクティブ方式は、常時商用給電方式の機能に加え、電圧変動時、簡易的に電圧を調整する機能を備えている。だから電圧変動による機器の故障リスクを回避できる。
UPS選びのポイントは、接続したい機器の消費電力と、停電からどの程度の時間を確保したいかを考えることだ。シャットダウンの対象となるデスクトップパソコン(ノートパソコンはバッテリーが搭載されているのでUPSの対象から除外)、サーバー、ルーター、ビジネスフォンなど、ネットワークに接続された情報通信機器に応じてUPSのバッテリー容量を選択する。もし1台のUPSで給電が賄えない場合は、複数台を導入する方法もある。UPSは、バッテリーが大きくなると価格が高くなる傾向があるが、ギリギリではなく、ある程度余裕を持った出力の機器を選びたい。
少し前はUPSといえば、パソコンやサーバーなどの付属装置というイメージもあった。しかし最近はネットワーク全体のリスク軽減策として、ビジネスフォンやルーターまでをカバーするために設置するケースがある。そのため、通信事業者もビジネスフォンとUPSをセットで販売している。
例えば、NTT西日本が扱っている無停電電源装置「Biz Box UPS」は、最大出力容量が750VA/500Wの「SMT750J」と、同1200VA/980Wの「SMT1500J」の2タイプをそろえる。SMT750Jの場合、ランタイム(UPSに接続する合計消費電力「W」に対する電力供給時間の目安)は200Wで22分、300Wで12分、500Wで5分だ(利用環境により変動する)。
ビジネスフォン「SmartNetcommunity αA1」(以下、αA1)の主装置の消費電力は最大で約130W、給電HUB(8ポート)は同95Wなどで合計約230W。ほかにUPSに接続される機器がなければ、停電時に20分程度の給電が可能だ。通話中であっても、相手に事情を説明して電話を切る程度の時間は十分に確保できる。
ビジネスフォンに加え、ファイルサーバーの「Biz Box Server」(消費電力約250W)をUPSにつなぐ場合、合計消費電力は約480Wとなり、5分程度の給電が行える。この間にファイルサーバーを適切にシャットダウンし、データ消失や機器故障のリスクを回避できる。さらに、インターネットに接続するルーターといったネットワーク機器やデスクトップパソコンなどにも給電が必要なら、合計消費電力は増える。より大容量のバッテリーを備えたSTM1500Jを選択するとよいだろう。
実はαA1は、故障・災害時などのアクシデントに備え、ビジネスフォンデータのバックアップ機能を標準装備(※1)する。速やかにデータの復旧ができ、業務への影響を最小限に抑えられる。さらにオプションとして「ビジネスフォンサポート」(※1)(※2)がある。異常発生時にオペレーターから状況を通知してもらえる「システム監視機能」(※3)などのサービスも、復旧対策として併用できる。
UPSに加えて、こうしたビジネスフォンの機能やサポートサービスを組み合わせることで停電対策はより強固になる。事業の継続という重要な目的を考えれば、UPSは決して価格の高い装置ではない。設置場所もそれほど取らない。事業継続計画の中では、実行しやすい対策といえるだろう。
※1 フレッツ 光ネクスト等の契約・料金が必要
※2 ビジネスフォンサポートの利用は、別途契約・料金が必要
※3 ビジネスフォン全ての監視・異常検知およびオペレーターからの能動的連絡を全て保障するものではない
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=山崎 俊明
【M】