
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線

これまでの連載で、顧客の今のニーズだけに安易に応えることの限界について幾度となく考えてきました。第3回のコラムでは、「意味のイノベーション」を提唱するロベルト・ベルガンティが新しい価値の提案を説明する際に用いる「贈り物」の比喩を紹介しましたが、少々うがった見方をすると、相手のことを考えた「贈り物」が単に贈る側の「押し付け」に思えなくもありません。これを企業の製品・サービスづくりに置き換えると、「つくり手の想い」にあふれた製品は顧客に感動を与えるものか? はたまた、「企業のエゴ」を顧客に押し売りするようなものなのか? その境目はなかなか際どいのではないでしょうか。
一部の社会・倫理的に問題のある企業を除き、ほとんどの企業は顧客のことを第一に考えて日々ビジネスをし、製品やサービスをつくっていると思います(少なくとも私はそう信じたい)。しかし、ある製品は顧客の心を魅了し、また別の製品はそうはならないのはどうしてなのでしょう。今回は、大阪のある中小企業の製品を事例に考えてみたいと思います。
大阪府東部に位置する八尾市は、古くから製造業を中心とした中小規模の企業がたくさん集まっています。2024年に創業100年を迎える木村石鹸工業株式会社(以下、木村石鹸)もその一つです。従業員数は50名ほどで、家庭用や工業用など多様な洗剤・石鹸を製造しています。
かつて木村石鹸では、他社製品のOEM製造が売り上げの大半を占めていました。現在社長を務める4代目の木村祥一郎さんが事業を承継された2016年を境に、自社ブランドの製品開発をスタートしました。現在では自社ブランド製品の販売が売り上げの約40%を占めるまでに成長。事業ポートフォリオを短期間で大きく転換することで成長を続けています。
また、自社の経営ビジョンともいえる社訓の第一項目に「家族を愛し仲間を愛し豊かな心を創ろう」(図1)と宣言。社員とその家族の幸せを第一に考え、それを徹底している優良企業でもあります。
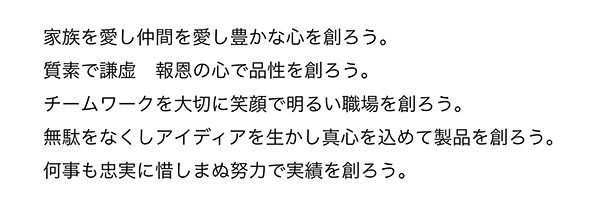
図1:木村石鹸の社訓(同社ホームページに記載の情報を元に筆者作成)
同社が自社ブランドの開発に力を入れる中で生まれた製品のひとつに、「12/JU-NI」(ジューニ)というシャンプーがあります(図2)。
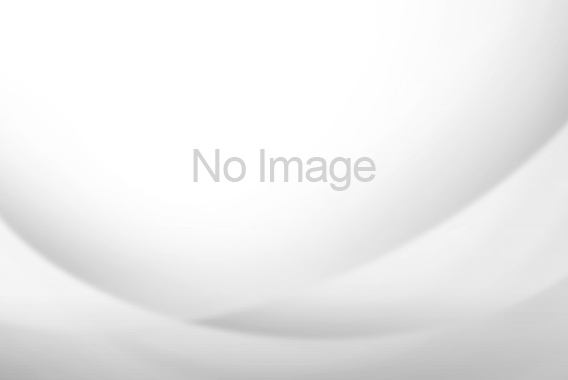
図2:12/JU-NIの製品イメージ(木村石鹸提供)
12/JU-NIは、ダメージヘアやくせ毛にとって「本当に良いものをつくりたい」という開発者の想いから生まれました。流行や慣習にとらわれず、本当に髪をよくするにはどうするべきかを突き詰めて研究されています。昨今はやりのオーガニックな製品ではなく、シリコンやケミカルも使っています。
もともと木村石鹸は、100年近く前から「釜焚き製法」という伝統的な製法を使って製品づくりをしてきました。このつくり方は季節や材料の状態に応じていろいろな調整が必要で、熟練した職人の経験と勘が求められます。非常に手間がかかる製法ではありますが、安全・安心・環境にも優しいことをモットーにした高品質な製品づくりには最適であることから、同社では現在に至るまでこの製法を採用しています。品質にこだわって石鹸と向き合い続けてきた知識と経験が、脈々と受け継がれているのです。
そうしたカルチャーのもと、ある開発者が「髪にとって本当に良いもの」を考えたとき、常識とされている考え方とは異なる提案をすることになりました。自然派の製品が当たり前に良いものと認識されている中、正しい知識を基に髪の構造や環境への配慮を突き詰めると、シリコンを配合し、界面活性剤と呼ばれる化学成分を用いることが本当に髪に良い、という考えにその開発者は行き着いたのです。
ビジネスの観点から見ると、流行や、マーケティング的にも合理的に説明・訴求できるものにある程度合わせた製品にしたほうが効率はよかったことでしょう。その上、髪にとって本当に良い成分にこだわった配合はとても高度な技術を要します。絶妙なバランスで成分を配合し、高い技術によって製品としてまとめあげないと沈殿が生じて品質が保てないそうです。それでも開発者は原価度外視で「髪に本当に良いもの」にこだわり、12/JU-NIを完成させました。
その結果、500ml入りのシャンプーとコンディショナーのセットで定価は5,500円(税込)と、市場相場と比べて相当高価になりました。さらに、髪質によって合う人と合わない人がいる、という極端な製品になってしまったのです。それでも経営陣は「もっと正直な開発がしたい、本当に効果のあるもの、良い原料をたっぷり使って良いものを作りたい」という気持ちで他社から木村石鹸に中途入社した開発者自身の想いを信頼し、その熱意とこだわりを否定することなく製品化することを決断したのです。
そのような開発者の本気のこだわりと、ある意味で市場の常識に対する問題提起から生まれた12/JU-NIは、一言でその良さが理解されるようなものではありませんでした。そこで同社は、普通のやり方でシャンプー市場に出してしまうと消費者に理解してもらえないと考え、最初の販路としてクラウドファンディングを選びました。「本当に髪に良いもの」に対する妥協のないこだわりやそれを実現する高い技術、世間で誤解されている石鹸の成分にまつわる真摯な説明、そして「合う人と合わない人がいる」ことを正直に伝えました。
かなりの覚悟を必要とするチャレンジだったことは容易に推察できますが、蓋を開けてみると、髪の悩みを抱えてきた多くの人々から絶大な人気を集め、一般販売にたどり着くことができたのです。今ではその品質もさることながら、真剣に顧客を思い、品質に向き合うまっすぐな姿勢が高く評価され、人気の製品となりました。同社の「正直さ」が顧客を魅了したのです。
顧客に真摯に向き合う企業と、それを理解し価値を認める顧客。12/JU-NIの事例は、つくり手と顧客の良い関係を体現する事例です。しかし、他の多くの企業も木村石鹸と同様に顧客のことを大切に考え、真摯に製品・サービスづくりをしているはずです。にもかかわらず、木村石鹸がなぜこれほどまでに顧客を魅了できたのでしょう。私は、その疑問を解くひとつの鍵が「職人的こだわり」にあるのではないか、という仮説を提起したいと思います。
話は急に変わりますが、アラスデア・マッキンタイアというアメリカの倫理哲学者が、著書『美徳なき時代』(みすず書房)で、フランス革命を契機とする西欧における近代化の流れの中で個人主義が行き過ぎたことが、自分が属する共同体や他者に対する思いやり、そして道徳や倫理観といった社会における「美徳」が急速に個人化し失われてしまったことを批判しています。
マッキンタイアは、美徳を復権するために古代ギリシアの哲学者アリストテレスの考えに立ち戻り、「共通善(common good)」の重要性に着目しました。共通善とは、個人と自分自身が属する社会(共同体)を分離せず、自分という個人は共同体に埋め込まれつくられている存在なのだから、共同体にとっての善を追求することは、結果的に自分自身にとっての善にもなる。利己と利他を二元論で分けて考えるのではなく、共同体にとって善いことを考え、実践することでそれらの融合をめざそう、という考え方です。つまり、マッキンタイアにとっては共通善の追求こそが「美徳」であり、その最たるものが職人(アルチザン)だと言っています。
職人は、第一に自分自身の技の卓越性を追求しますが、それは決して自分だけのためではなく、自分が属する共同体である職人集団への知の共有と還元を企図するものです。そして、共同体を捉える視野は、職人集団の範囲にとどまらず自分が生きている社会全体にも同様に広がります。その世界観の中では利己と利他という分断はもはや存在せず、社会全体を善いものにするために自分自身の信念を基準にして技が追求され、それによって共通善が生まれ、共同体に価値として分配され循環するとマッキンタイアは考えたのです(くしくも、技芸の名人を意味するヴィルトーゾ[virtuoso]という言葉の語源は、美徳を意味するヴァーチュ[virtue])。
このマッキンタイアの考え方を本論に引きつけると、単なる顧客追従でも、エゴとしての自己満足でもなく、信念と覚悟で共同体にとっての共通善を考えることが「美徳」と言えます。私には、12/JU-NIがこだわり追求しようとした「正直」な姿勢が、このアルチザン的な共通善の追求の姿勢と重なるように思えます。
それは見方を変えると、サービスデザインの考え方の根底にある思想とも重なります。すなわち、顧客と製品・サービスの世界を局所的に見るのではなく、関与する人々や多様な要素(アクター)から構成される関係性ネットワークを俯瞰(ふかん)的に見て、その中で価値が共創・循環される「価値のエコシステム」をデザインするのだという思想そのものではないでしょうか。
木村石鹸の正直さが実現した12/JU-NIの事例、そしてマッキンタイアが考える美徳の根幹にある「共通善」の考え方は、企業のエゴを超越した本当の「つくり手の想い」を提案する製品・サービスを考える上でのヒントになるのではないでしょうか。
執筆=井登 友一
株式会社インフォバーン取締役副社長/デザイン・ストラテジスト。2000年前後から人間中心デザイン、UXデザインを中心としたデザイン実務家としてのキャリアを開始する。近年では、多様な領域における製品・サービスやビジネスをサービスデザインのアプローチを通してホリスティックにデザインする実務活動を行っている。また、デザイン教育およびデザイン研究の活動にも注力し、関西の大学を中心に教鞭をとる。京都大学経営管理大学院博士後期課程修了 博士(経営科学)。HCD-Net(特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構)副理事長。日本プロジェクトマネジメント協会 認定プロジェクトマネジメントスペシャリスト。
【T】
これからのビジネスをつくるための「サービスデザイン思考」