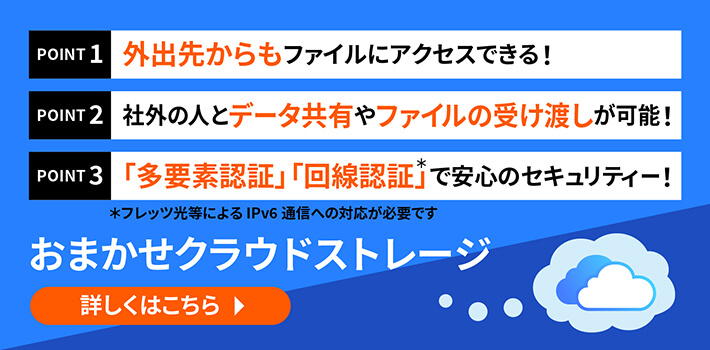オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
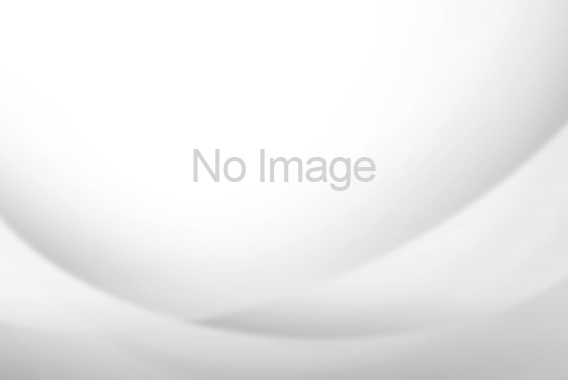
社内のファイル共有ツールとして、社内ネットワークに接続されたストレージである「NAS」(Network Attached Storage)を利用している企業は多いかもしれません。しかし、そのNASをクラウドストレージに変えることで、ビジネスをより便利に、より安全な方向に変えていくことも可能です。今回はNASと比較したクラウドストレージのメリットを紹介していきます。
日々の業務の中で、データは毎日生成・蓄積され続けます。例えば、顧客やビジネスパートナー宛てに作られた文書ファイルや、さまざまな数値データが記載された表計算ファイルなどは、業務が進む度に更新・生成されていくものです。しかし、個人パソコンの容量には限りがあるため、大容量のストレージ(ハードディスク)に保存する必要があります。
ファイルの保存場所としては、冒頭でも触れたように、社内ネットワークに接続されたストレージである「NAS」がよく利用されます。NASはストレージ容量が大きいため、データの保存容量には余裕があります。たとえ容量が不足したとしても、製品によっては後からハードディスクを追加できるものもあります。
しかもNASは社内のネットワークとつながっているため、オフィスで働く従業員が共同で利用が可能です。チームで共同利用するファイルをNAS上に置いておけば、メンバー全員がそのファイルにアクセスできるようになります。
2022年1月に改正された電子帳簿保存法では、メールなどWeb上における電子取引で受領した取引書類をすべて電子データで保存し、検索できる状態にしておくことが義務化されましたが、こうした取引書類のデータもNASに保存しておけば、同法の基準もクリアできるでしょう。
NASにはこのようなメリットがある一方で、デメリットも存在します。例えば、オフィス外では簡単には利用できない点です。
テレワークや出張・外出先で業務を行う場合、NASに搭載されているリモートアクセス機能、もしくはVPNにて社内ネットワークに接続しない限り、NASは利用できません。たとえ社外から利用できる設定にしたとしても、不正アクセスされないようセキュリティ対策を講じておく必要もあります。
また、NASは基本的には社内に設置するため、オフィスが被災した場合、被害がNASにも及ぶ恐れもあります。たとえオフィスが被災しなくても、長年使い続けることによる経年劣化で、故障が発生することもあります。場合によっては、NASに保存されたデータが復旧できず、消失するリスクも考えられます。
カスタマイズ性にも限界があります。NASに空きスロットがある場合は、ハードディスクを追加することで容量が増やせますが、スロットがすべて埋まった場合、ハードディスクに加えてNAS自体も追加する必要があります。新たにリモートアクセス機能を追加したい場合も、同機能を備えたNASに新調しなければなりません。

NASには遠隔利用、セキュリティリスク、カスタマイズ性の面で課題がありますが、これらのマイナス面は、クラウドストレージを利用することで解決が可能です。
クラウドストレージは、インターネット上に設置されたストレージにファイルを保管するサービスのことです。クラウドストレージの最大のメリットは、社内だけでなく社外からもアクセスできる点にあります。
NASは社内に設置されたストレージにアクセスするため、基本的には社内での利用を想定していますが、クラウドストレージはインターネット上のストレージにアクセスするため、社内でも社外でも利用可能です。テレワークや出張時でも、インターネットに接続できる環境であればどこでもアクセスできます。
さらに、NASと同様、クラウド上で複数のメンバーによるファイルの共同編集にも対応しています。例えばWeb会議中に、参加メンバー全員で1つのファイルを見ながら、資料を逐一更新していく、といった業務にも対応できます。
クラウドストレージがNASと特に大きく違う点は、顧客や取引先など社外の人ともファイル共有が容易になる点です。
メールでファイルを共有する場合、一度パスワード付きzipファイルに変換して送付し、その後パスワードが記載された別メールを送付しているケースも多いかもしれません。このファイル共有方法は、識者から“手間がかかるうえ、セキュリティ面でも危険がある”と指摘を受け、日本政府や一部の企業ではすでに廃止されています(いわゆる「PPAP問題」)。
しかし、クラウドストレージであれば、そもそもメールには何も添付せず、保管場所のURLのみ記載されるため、メールは1通で済むうえ、パスワードを共有する必要もありません。もちろん大容量のファイル共有も可能です。
BCP対策としてもクラウドストレージは有効です。クラウドストレージ上にアップされたデータは、サービス提供会社が契約するデータセンターに保存されます。多くのデータセンターは災害のリスクが低い場所に建てられているため、たとえオフィスが被災したとしても、ストレージにアップしているデータが破損する可能性は低いです。
このほか、NASは本体とハードディスクを購入し、オフィス内に設置して社内ネットワークに接続する必要がありますが、クラウドストレージではその手間は不要になります。初期費用も不要で、月額もしくは年額の利用料金のみでスタートできます。ストレージの容量や同時接続人数は随時変更できるため、自社に合った運用が可能になります。
| NAS | クラウドストレージ | |
| 初期費用 | 機器の購入費用がかかる | 多くの場合不要 ※サービスによる |
| 運用費用 | 基本的には不要(光熱費のみ) | 金額はサービス、プランによって異なるが、月額で費用が発生する |
| 社外からのアクセス | 別途設定やセキュリティ対策が必要 | 可能。共同編集もできる |
| 管理 | 導入時の設定、機器の更改、故障に備えたバックアップなど自社で対応する必要がある | サービス提供会社が行う |
もし自社のビジネススタイルが「外出するスタッフが多い」「テレワークをより本格化したい」「社外の人とデータをやり取りする機会が多い」のであれば、NASをクラウドストレージに切り替えることで、業務効率化やコスト削減などのメリットが得られるかもしれません。選択肢の1つとして、検討してみても損はないでしょう。
※NTT西日本グループでは恒常的なウイルス監視を行い、メール送信時は誤送信防止の仕組みを導入しています
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆= NTT西日本
【M】