
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
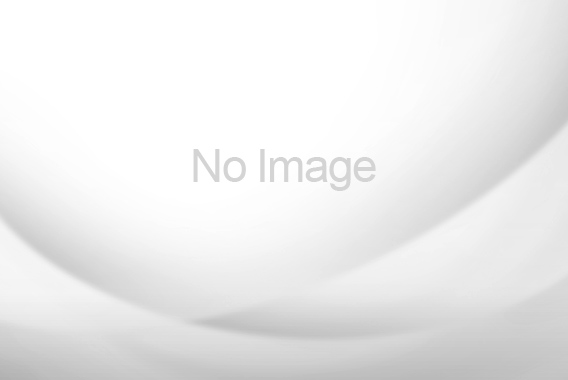
外国人に期待する介護分野の人材供給。しかし、従来は日本で介護について学び、資格を取得する必要があり活用のハードルはかなり高くなっていました。しかし、2019年の入管法改正によって即戦力の介護人材も受け入れる道が開かれました。今後、ますます必要になる介護分野の人材確保の手段として、外国人活用を積極的に進めることが今後の日本経済にとっても大きな意味を持つでしょう。
在留資格「介護」というのは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が、介護または介護の指導を行う業務に従事する活動」に認められる資格であり、具体的には、介護福祉士養成施設を卒業し、「介護福祉士」の資格を取得した者が、日本の介護施設などと雇用契約を結んだ上で、取得するものです。
そのため、一度も日本に来たことがないけれども、介護関連の仕事をしていた人が、「介護」の在留資格の申請を出したところで、認められるというわけではないのです。一方、日本にまず留学に来て、学校に通って生活を成り立たせるなどというのは、経済的にとても大変なことです。
日本の福祉専門学校に入るとしても、その前提として、日本語学校にも行く必要があります。もちろん、海外のお金持ちの子女が留学するというケースもあるでしょうが、そういう人が介護の世界で、その後も働いてくれるのかというと極めて疑問です。
とある自治体では、介護就業意欲がある外国人が在留資格「介護」を取得することができるモデルケースとして、次の方法を確立しようとしています。日本に在留資格「留学」で来ている学生に、学費・生活費はアルバイトなど(原則週28時間)で稼いでもらい、さらには、事業主が貸付制度などを設けて、卒業後、何年間か仕事をした場合には、その返還を猶予するというモデルです。
それでも、いろいろ問題はあります。例えば、事業主は将来、自己の施設で働いてくれると信じて貸し付けたものの、何のかんのと理由をつけて、お宅の事業所では働きたくないと外国人が言い出した場合、「それでは、約束が違う。絶対に辞めさせない。辞めるのなら、即刻、全額返せ」というトラブルになることは必定です。かといって、我が国の労働基準法上、そのような返還約束は、違約金による不当な拘束と判断される恐れが大です。
ここまで述べてきたように、EPA、在留資格「介護」、技能実習(介護)、どれも介護業界の人手不足に対して外国人労働者招へいに寄与するような決定的な対策とまでは言い切れません。そこで、前にも説明した通り、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)の1つとして、「介護分野」が認められることになりました。
受け入れの趣旨としても、「介護分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する」と言明されています。
介護業界の人手不足は、単なる民間の経済問題にとどまりません。介護保険制度の枠組みに従って適切な介護がなされなければ、我が国の社会保障制度そのものが機能しなくなります。介護のために本来の仕事を続けられないなどの家族が出てくることは、国家経済にとって損失ともいえるのです。
特定技能ビザを認める出入国管理法の改正は、2019年4月から施行され、5年間での受け入れ見込み数は最大6万人とされています。特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、「介護技能評価試験」に加え、一定の日本語能力試験にパスすることが求められます。
また、特定技能1号で従事できる業務は、身体介護等(入浴、食事、排せつの介助など)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など)であり、訪問介護などの訪問系サービスにおける業務は対象となりません。
さらには、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とする」「直接雇用に限る」などの条件があります。国は「大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置をとること」とされています。
問題は、「介護技能評価試験」と日本語能力試験の難易度です。これをとても難しくすれば、試験に限ってですが、能力的に優秀な人材に絞り込むことはできるでしょうが、それでは必要な数は集まらないかもしれません。他方で、極めて簡単にしてしまえば、日本語もろくに話せず、外国人自身も日本に来てから苦労するでしょうし、雇用した施設側も労働力として当てにできなかったとなると、雇った意味がなかったと後悔することにしかなりえません。
当面は、合格者(受け入れ者)とその後の働きぶりを見ながら、試験の難易度を調整することが要求されることとなるでしょう。もちろん、受け入れた外国人が本当に事業所の戦力になるか否かは、試験の成績だけで判別できることではありません。これは本制度固有の問題ではなく、試験の難易度を調整することだけがこの制度の課題ではありません。
また、せっかく優秀な外国人を確保できたとしても、その外国人が日本での生活を続けることに困難を感じて、就労を断念してしまってはこれまた意味がありません。そこで日常生活の支援、例えば、住居・食事・医療・宗教・その他文化慣習などのサポートや困りごとについてのカウンセリング・相談窓口の設置などが必要となるのです。もはや、外国人を受け入れるという消極的な形だけでは、人材は集まりません。これからは行政も含めて日本全体で積極的に動いていかなければ、適正な数の介護職員を確保できない時代になっていくことは間違いありません。
執筆=小澤 和彦
弁護士法人 後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士。第二東京弁護士会の西東京市男女共同参画推進委員会委員長。業務分野は企業法務、知的財産など。主な著作として「相続戦争を勝ち抜く85のルール―相続財産の分配で、モメそうなときに読む本」(九天社)など。
【T】