
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線

急増する要介護・要支援者によって、介護分野の人材ニーズは拡大しています。しかし、離職率が高く、他のサービス業よりも賃金水準が低いこともあって人材確保には非常に苦労しています。それをカバーするために東南アジアを中心とした外国からの人材の受け入れにさまざまな手段で取り組んでいますが、従来型の技能実習制度などの仕組みでは限界があることも明らかになってきています。
介護保険制度が施行されて以来、2000年度は218万人だった要介護・要支援者は、その後も数が増え続け、2015年度には、ついに600万人を超えました。このように増大していく要介護・要支援者に対するサービスのニーズも増えていますが、必要な数の介護職員を確保できないということが、どこの施設も抱える悩みとなっています。
介護に関する有効求人倍率が、全産業より高い水準で推移しているのは、要するに求人を出しても、他の産業に比して人が集まりにくいことを示しています。もちろん、都市部か地方かによる違いなどもありますが、例えば、2021年9月における全職業の有効求人倍率の平均が1.05倍であるのに対して、介護の有効求人倍率の平均が3.63倍にもなっていて、介護分野の求人がかなり大変なことがうかがえます(厚生労働省「一般職業紹介状況(2021年9月分)」)。
さらに問題なのはその離職率の高さです。離職率が低下してきているとはいわれていますが、厚生労働省のWebサイトにある「介護労働の現状」によると、全産業との比較では、介護職員の離職率が上回る状況が続いています。もちろん、職種の違いこそあれ、どんな職業でも大変な側面というのは必ずあります。なぜ、介護の分野での離職率が高い傾向にあるのでしょうか。
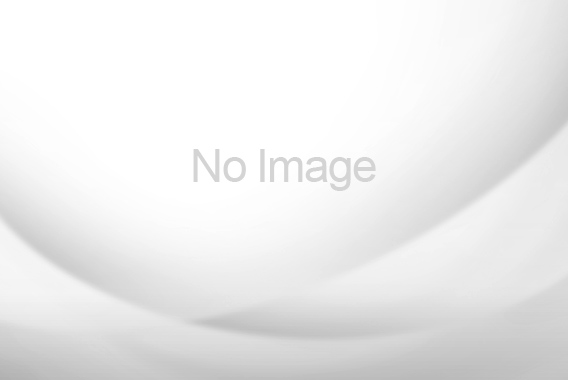
(出典:厚生労働省「介護労働の現状」)
公益財団法人介護労働安定センターの「平成29年度介護労働実態調査」によると、離職の理由としては、「職場の人間関係に問題があったため」 「結婚・出産・妊娠・育児のため」「事業所の理念や運営のあり方に不満があったため」「他に良い仕事・職場があったため」「自分の将来の見込みが立たなかったため」「収入が少なかったため」「新しい資格を取ったから」などが挙げられています。
以上の理由を見て、どのような感想を持ちますか? この手の離職理由はどの分野、どの職場でも見られる離職理由で、何も特別、介護特有の離職理由ということではないようにも思われます。
問題は、他の対人サービス産業との比較です。国の「ニッポン一億総活躍プラン」においても触れられていますが、介護分野で人材確保が困難な理由として、介護職員の賃金が他の対人サービス産業と比較し、賃金が低いことが挙げられています。つまり、介護の仕事で働いても、他の仕事よりも給与が安いのであれば、別の仕事に就きたいと考えるのは自然なことです。
しかし、介護というのは、その売り上げが保険料収入に依拠するところが多いため、払える給与の上限が決まってしまいます。そのため、政府が政策的に関与をしていかなければ、介護職員の確保は難しいのです。実際、介護職員の確保のためのさまざまな施策、「介護職員処遇改善加算(給与増額)の拡充」「再就職準備金の貸付制度」「介護福祉士をめざす学生への奨学金制度」「介護ロボット・ICTの活用推進」などが政府により実行されています。
これらの施策がどの程度の効果を有し、今後、ニーズを満たす介護職員を確保できるか否かは不明です。というより、難しいと思われます。例えば給与にしてみても、いきなり5万円も10万円も昇給できるわけではありません。1万~2万円程度の上乗せが小さいとは言いませんが、それで多くの人が介護労働市場に流れ込んでくるということにはならないでしょう。
外国人に目が向いているのは、今の日本の給与水準でも働きたいと思ってくれる人に介護業界に入ってきてもらいたいからです。いろいろな施策を打ってはいるものの、介護分野で十分な日本人職員を確保できる可能性は低いので、外国人に期待しているということです。
「外国人、特に給与水準・生活水準が日本よりも低い国の人なら、今の日本の給与でも高いと思って介護業界で働いてくれるのではないか」と考えているため、受け入れを想定している国としては先進国ではなく新興国、あるいは少なくとも日本よりも給与水準が低い国です。アメリカやフランスを想定しているわけではありません。地理的な関係から、やはり主として、アジアの国々ということになります。
我が国では、2008年から経済連携協定(EPA)に基づき、あくまでも、経済連携の強化観点から、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国から介護福祉士候補者を受け入れています。就労期間は4年で、国際厚生事業団という公的な団体が仲介をしています。これまでの約10年間の間に、約3000人を超える受け入れ実績を築き上げてきています。
しかし、日本にやってきたすべての外国人が、試験に合格できているわけではありません。本格的に外国人の日本における介護就労を認めるために、2017年9月に入管法を改正することにより、在留資格「介護」を創設しました。就労期間は5年で更新することもできます。そして矢継ぎ早に、2017年11月に、今度は技能実習生として介護も認めることとし、中国、タイ、ミャンマー、ラオス、カンボジアなどの15カ国を送り出し国として、受け入れを開始しました。就労期間は3年です。
EPAはあくまでも経済協力(支援)を目的としており、技能実習は日本から海外への技能(技術)移転を図ることによる諸外国支援を目的としています。技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないとされています。
現実には、事業主は労働力不足解消のため受け入れを当てにしているのに、建前上は、経済支援や技術指導など。日本が恩恵として外国人を受け入れて「あげる」、という実態と制度趣旨の不一致が生じていました。
例えば、技能実習制度において、希望外国人には、「働いて給与ももらいながら技術習得もさせてあげるから」と言って外国から招いているのに、現実問題としては、労働力不足の穴を埋めるために単純労働をひたすら行わせるだけで、その技能実習生のキャリアアップなど何も考慮されていないという企業もありました。
外国人からすれば、「技術指導とか、技能実習とか言っていたのに、誰もきちんと指導してくれない。これはだまされたのではないか」「技能実習だから給与が安いのは仕方ないと思っていたけど、これは普通に働かされているだけじゃないか。それだったら、逃げ出して、もっと給与のいいところで働いた方がいいんじゃないか」と不審を招いたり、不満を抱かせたりするのは当然です。
執筆=小澤 和彦
弁護士法人 後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士。第二東京弁護士会の西東京市男女共同参画推進委員会委員長。業務分野は企業法務、知的財産など。主な著作として「相続戦争を勝ち抜く85のルール―相続財産の分配で、モメそうなときに読む本」(九天社)など。
【T】