
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
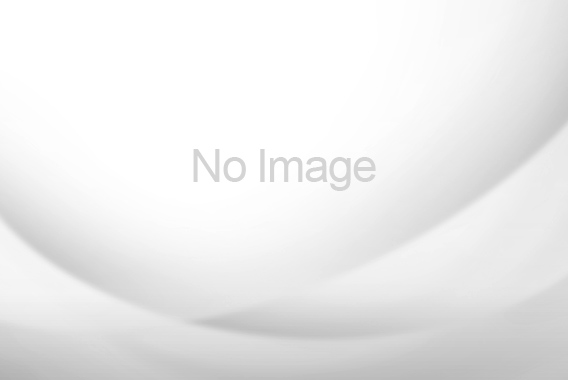
人手不足に悩む日本経済。建設、介護、飲食など多くの業種で人材確保に悩む企業が増えています。その解決策の一つとして外国人労働者の活用が注目されています。これを促進するために2019年4月には改正出入国管理法(出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案)が施行されました。それ以前から進む外国人労働者の受け入れの流れと、実績を整理します。
2018年12月8日、外国人労働者の受け入れ拡大などを内容とする改正出入国管理法が参議院において可決、成立しました。その後、2019年4月1日に施行されています。
「拙速である」「議論が尽くされていない」などという野党の批判があり、以下のような問題点が指摘されました。
1. 技能判定を実際にどの程度の厳格さで、実施するのか?
2. 受け入れ後の外国人は、どの程度、日本人と同じような社会保障などの保護を受けられるのか?
3. ブラック企業で、低賃金でこき使われるという人権問題は生じないのか?
4. 受け入れ後の外国人の追跡をどのように行っていくのか?
その一方、正直な感想としては、ようやくという感が否めません。そもそも、なぜ、外国人労働者の受け入れを拡大するこの法案を作成することとなったのかという根本を踏まえて批判しなければなりません。
建設、介護、飲食、宿泊、農業、漁業、自動車産業など業種を問わず、企業が膨大な募集広告費用をかけて、時給(給与)を上げて求人しても、十分な人手が確保できていません。シニア・女性活用については別の連載で解説していますが、それでも足りないと思われます。
外国人を入れると治安が悪くなるのではないか、受け入れたはいいものの、逃亡者が出たり、企業の業績が悪くなったりしたらどうするのかなど、不安が出るのは予想されたところです。おそらく、それらの不安は当たるでしょう。文化や習慣の違う外国人が日本に来てトラブルにならないはずはありません。仕事がきつくて逃亡し、お金がなくなって犯罪を起こす外国人も出てくるでしょう。
企業でも人手不足を解消しようとして外国人を大量に雇い入れても、その業績を維持し拡大し続けられる保証などどこにもありません。そもそも外国人を雇ってはみたものの、全く仕事ができず、やる気もないということもあり得ます。そんなことは別に外国人固有の問題ではなく、日本人の場合だって、よくある話です。だからといって、外国人の受け入れ拡大そのものをやめるというのでしょうか?
「やめろと言っているのではない」「外国人受け入れのリスクをなくしたうえで実施しろと言っているのだ」ということなのでしょう。しかし、それでは、いつまでたっても実施はできません。なぜなら、そのようなリスクは絶対になくならないからです。
そういうリスクを抱えてまで外国人の受け入れを拡大するか、人手不足で悩み続けても断固外国人の受け入れ拡大に反対なのか、という選択なのです。ただし、今回の改正法案の中身がよく分からないまま、漫然と賛成したり、反対したりしているだけの人が多く見受けられるので、まずは、今回の改正法案がどのようなものであるかをよく理解したうえで、自分の意見を持つ必要があります。
実は、外国人の受け入れ拡大の措置は、今回の改正以前からも始まっていました。2012年5月には、経済成長への貢献が期待される高度な能力を持つ外国人については、優遇措置を講じるという「高度人材ポイント制」が施行されています。
これは外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」「高度専門技術活動」「高度経営管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設けて、ポイントの合計が70点に達した場合に、在留期間5年を付与したり、配偶者だけではなく親や家事使用人も帯同することを認めたり、入国手続きを優先処理するというものです。
次に、2015年4月には復興事業、東京オリンピック関連の建設需要に対応するために、2020年までの時限的な措置ではありますが、建設分野の技能実習修了者を外国人建設就労者として受け入れる事業で、認定を受けた適正監理計画に基づき2020年度末までに就労を開始した外国人建設就労者については、最長で2022年度末まで建設特定活動に従事することができます。
さらには、2017年9月には、介護分野の深刻な人材不足を解消するために、介護福祉士の国家資格を有する外国人を対象とする新たな在留資格「介護」が創設されています。加えて、特区事業もすでに行われています。2013年11月には、地域活性化総合特区で、日本の伝統料理の調理に従事する外国人の受け入れが始まっています。これを「特定伝統料理普及事業」といい、要するに、京都で京料理を外国人に学んでもらって、それを海外に普及してもらおうという事業です。
2015年9月には、国家戦略特区における家事支援外国人の受け入れ措置が、2017年9月には、農業支援外国人の受け入れ措置が講じられています。また、2017年9月には、「技術 人文知識 国際業務」「技能」の在留資格に該当するクールジャパン、インバウンド(訪日外国人旅行)分野の活動を行う外国人について、地域固有の視点から上陸許可基準を緩和する措置が実施されています。
「クールジャパン、インバウンド事業」について補足すると、以前は在留資格として、「技術 人文知識 国際業務」「技能」の現行の上陸許可基準を満たす「学歴」や「実務経験」がなければ、入国や在留ができないとされていました。この「クールジャパン、インバウンド事業」が発足したことにより、たとえ、「学歴」「実務経験」がなくても、何か代替できる資格や受賞歴があれば、関係省庁、ないし関係自治体が協議して認めることができるというものです。
このように規模感は小さいものの、外国人労働者の必要性から、さまざまな受け入れ措置が設けられてきているのです。厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況まとめ」によると、2017年は127万8670人と対前年度比18%増。2007年に届け出が義務化されて以来、過去最高を更新しています。このうち在留資格の「専門的・技術的分野」の労働者は約24万人で対前年度比18%。「技能実習」は約26万人で同22.1%増になっていました。改正出入国管理法施行前にも、外国人労働者の受け入れはかなり増加していたわけです。
執筆=小澤 和彦
弁護士法人 後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士。第二東京弁護士会の西東京市男女共同参画推進委員会委員長。業務分野は企業法務、知的財産など。主な著作として「相続戦争を勝ち抜く85のルール―相続財産の分配で、モメそうなときに読む本」(九天社)など。
【T】