
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
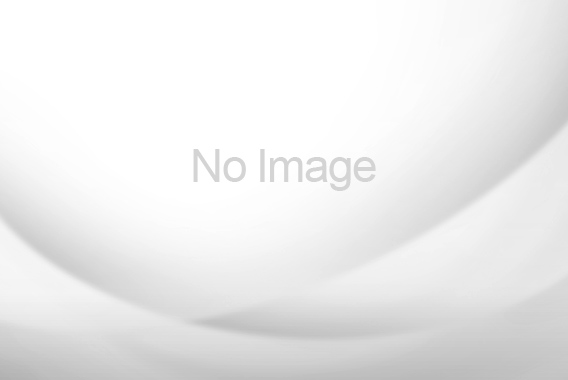
心と体の両面で健康を保ち、生産性を上げる方法を紹介する連載の第9回と第10回は精神の病への対策を取り上げています。前編の第9回では、心の病が社会問題になっていることを指摘して、完璧主義を止めるなど考え方によって、それに陥るリスクを減らせることを説明しました。そして、今回、後編の第10回では、より具体的な抗うつ力アップ法として、運動の効果や、食事のとり方などを紹介します。
最近のいくつかの研究で、有酸素運動がうつ病予防に役立つことが判明しています。ある研究では、運動量が最も少なかった群は、最も運動量が多かった群よりも、うつ病を患う確率が約75%も高いという結果でした。さらにその中間の群も、最も運動量の多い群に比べて、うつ病になる確率は約25%高かったのです。
うつ病の人が運動することで良くなる例も多くあります。なぜ、運動がうつ病を予防したり、改善したりするのか、細かなメカニズムは判明していませんが、血流や血糖値、血圧の改善に加えて、運動による睡眠の改善が関係しているのではないかと考えられます。
会話しながらできる程度の強度の運動が適切とされています。ウオーキングや水泳、ラジオ体操などがおすすめです。激しいスポーツ、くたくたになるほどの運動は逆効果になります。毎日が理想ですが、週に3日以上行うと、効果が期待できます。
抗うつ力をアップさせるためには、バランスがとれた食事を適量食べることが最も大切です。野菜やフルーツ、豆類、ナッツをしっかりと食べ、魚を中心に、肉と油は適度に取りましょう。魚に含まれる脂肪酸のEPA、DHAはうつ病だけでなく、認知症など、脳の病気予防に効果的です。しかしEPAやDHAのサプリメントは認知症予防に効果がないという研究結果があり、基本的に食事で取ることをおすすめします。油や肉の食べ過ぎはいけませんが、極端に減らすべきでもありません。
うつ病の脳で不足するセロトニンは、トリプトファンという物質から作られます。そこでトリプトファンを含んだ食品、チーズや納豆、たらこなどを食べることが、うつ病の予防になるという考えもありますが、実際にうつ病の予防に役立つかどうかは、まだ科学的には証明されていません。
アルコールは飲み過ぎないようにしてください。飲み過ぎは内臓に多くの負担をかけ、脳にダメージを与えます。規則正しい食事は、体内リズムを整えるのに役立ちます。早朝覚醒に困っている人以外は、起きたらすぐ朝食をしっかりと食べ、夕飯は早めに食べましょう。
それにより、体内リズムが整い、血圧が安定したり、睡眠の質が上がったりします。早朝覚醒に悩んでいる場合は、逆に朝食を起床後すぐではなく、遅らせるようにしましょう。ただし、夕食に関しては食事時刻を遅くすると、消化できずに睡眠が浅くなる可能性があるため、無理に遅くするのはやめましょう。
脳の病気全般でそうですが、特にうつ病に関しては、睡眠が重要なカギを握っています。睡眠は記憶を脳にとどめ、嫌な記憶や気分を消す作用があり、睡眠が不足すると、気分が落ち込みます。長ければいいわけではありませんが、睡眠不足は非常に大きな危険です。最近話題の「睡眠負債」のように、毎日少しずつの睡眠不足であっても、それが積もり積もると、体にも脳にも大きなトラブルをもたらします。
休日に目覚ましをかけずに寝ていると、平日よりも1時間以上長く寝ている場合は平日が睡眠不足だったということです。さらに2時間以上長く寝てしまう場合は、平日の睡眠時間が危険なほど不足しています。睡眠時間をきちんと取るための方策を早急に考えてください。睡眠時間を削ると仕事の効率が落ちて、適切な考えが浮かばなくなります。仕事は時間をかければいいわけではありません。より良い仕事をするために睡眠時間を確保してください。
昼間、しっかりと光を浴びて、体内リズムを整えることも、うつ病予防には大切です。うつ病を含めて、いくつかの精神科の病気に光を浴びる療法が行われています。日光並みの強さの光をしっかりと浴びることは、それほど脳の健康にとって重要です。
執筆=森田 慶子
医療ライター。1996年から、主に医師をはじめとする医療関係者向けの専門的な記事を執筆。2005年から患者向けや一般向けの医療や健康に関する記事も執筆。特に糖尿病や高血圧といった生活習慣病と、睡眠や認知症、うつ病などの精神科領域を専門とする。
【T】
健康が一番!心と体の守り方、鍛え方