
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
前編では睡眠を適切に取る意義を解説しました。後編は、睡眠力を低下させる原因を紹介した上で、実際に、睡眠力をアップする方法を説明します。ぜひ参考にしていただき、充実した睡眠を取ってください。
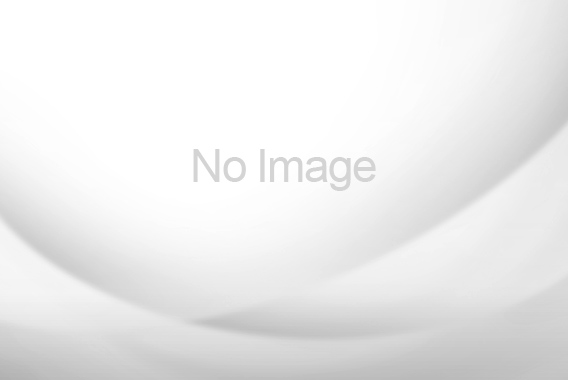
動物の体の中には時計があり、光が一切ない地下牢(ろう)のような場所に入れられても、しばらくの間は夜になれば眠くなり、朝になれば目覚めます。食事をして何時間かすれば自然におなかがすきます。しかし、長い間、その環境にいると、次第に時計は狂いだします。
体内時計は睡眠や食欲だけでなく、血圧や体温その他多くに関して、いつどうするかをつかさどっています。例えば血圧は朝、起床前から1日の活動に向けて上がり始め、日中、多少上下して、夜は睡眠に向けて次第に下がり、眠るとさらに下がります。糖尿病と深く関係するインスリンも時刻によって分泌の量が異なります。体内時計が狂うと、血圧や体温まで狂い、その結果、体内時計がまたずれるというふうに相互に関係しています。
寝床に就いてもいつまでも寝付けなかったり、眠りが浅くなったり、長時間寝ても寝足りなくなるのは、体内時計が狂ったせいです。睡眠力を上げるには、体内時計を整えることが大切です。
早起き習慣を身に付けたいと思ったときに、多くの人が「その分、いつもより早く寝よう」と考えます。睡眠時間だけ考えればそれでいいはずなのですが、実際には早く寝ようとしても寝付きが悪くなることが多く、朝は寝起きが悪くなりがちです。寝ている時間よりも、重要なことは時刻です。
実は体内時計は起床から計った時間で動いています。起きてから何時間後に血圧や体温を高め、何時間後に活動のピークを持っていき、何時間後に脂肪をすばやくエネルギーにするか、何時間後に眠くなるかということが決まっています。
従って、すっきりした目覚めを得るためには、寝る時刻が何時でも起きる時刻は一定にすることです。前夜が遅かったからといって起床時刻を遅らせると、体内時計が狂い、その夜の寝付きが悪くなります。
特に平日の睡眠不足を補おうと、休日に遅くまで寝ていると、休日明けの朝がつらくなり、1週間かけて、狂った時計を少しずつ直し、週末になるとまた時計を狂わせ……というつらい状況になります。
体内時計は日々少しずつずれていて、毎朝の光と朝食で時計合わせをしています。寝起きが悪い人は、朝しっかりと光を浴びるようにしてください。実際、睡眠障害の治療では、太陽光に近い、強い光を浴びる治療法があるくらいです。
朝起きたら、すぐ朝食をしっかりと食べてください。朝食抜きでは体内時計が狂います。朝食を食べることで体のスイッチが入り、活動しやすく体温や血圧が調整されます。朝食のメニューはできればすべての栄養素が入っているバランスが取れたものがいいですが、少なくとも炭水化物とたんぱく質は取るようにしてください。夜は明るい光を避けて、特にパソコンやスマートフォンなどの液晶画面から発せられているブルーライトを見ないようにしましょう。
高齢者が早朝覚醒に悩んでいる場合は、起きてすぐは光を避け、本来起きたい時刻までは、光を浴びないようにしましょう。できれば朝食もその時刻まで食べないようにします。夕方早い時刻に眠くなってしまう場合は、ブルーライトを浴びて、できるだけ覚醒時間を延ばしましょう。
寝付くときは深部体温を下げる必要があります。昼間、運動したり、就寝時刻の1時間から2時間くらい前にお風呂に入ったり、しっかりと一度体温を上げてください。それにより体温が下がりやすくなります。眠くなると手足が温かくなるのは、深部体温を冷やすために放熱しているからです。
お風呂の温度は、40度以下のぬるめが向いています。ゆっくりとつかりましょう。温度の高いお風呂は目覚めてしまいます。目覚めの悪い人は「活動の神経」といわれる交感神経を刺激する熱い湯の風呂に朝、入ると、しゃきっと目覚められます。
寝付きが悪い、眠りが浅いなど睡眠の問題がある際、医師が最初に行うのは、睡眠を妨げているものがないかチェックすることです。起きているときならなんでもない、ささいなことが眠りに就こうとするときには大きな妨げになることがあります。
ベッドは窓際を避けます。仕事をしている人は社会に合わせて定時に起きなければなりません。窓から入る太陽の光で朝を感じてしまうと、季節で変わる日の出時刻に体の起床時刻がセットされてしまうため、太陽の光を寝室に入れないようにしましょう。
寝るときの寝室は暗くしましょう。街灯などが近くにあって窓から光が入ってしまう場合には、遮光カーテンなどを使って光を遮ります。音はできるだけ入ってこないようにしてください。防音効果のあるカーテンもあります。どうしてもうるさい環境の場合には、耳栓を使うのもいいでしょう。
寝室は眠るための場所。心身にそれを刷り込むことも大切です。眠くならないうちにベッドに入って眠れない時間を過ごすと、眠れない場所と感じるようになってしまいます。寝付きが悪いときは寝室を出て、暗めの環境で、リラックス効果のある静かな音楽でも聞きながら過ごしましょう。眠くなってからベッドに入ります。スマートフォンやテレビなど起きているときのための道具は寝室にできるだけ持ち込まないようにしてください。
執筆=森田 慶子
医療ライター。1996年から、主に医師をはじめとする医療関係者向けの専門的な記事を執筆。2005年から患者向けや一般向けの医療や健康に関する記事も執筆。特に糖尿病や高血圧といった生活習慣病と、睡眠や認知症、うつ病などの精神科領域を専門とする。
【T】
健康が一番!心と体の守り方、鍛え方