
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
撤退の決断を紹介する連載の第3回は、父親から受け継いだ卸売業から撤退し、ファブレスメーカーへと転換したケースを紹介する。創業者である父親との葛藤や社員の不安を乗り越え、新しい事業を軌道に乗せるまでのプロセスは、多くの経営者の参考になるはずだ。
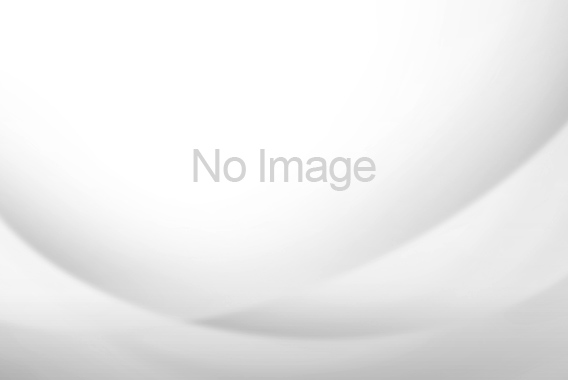
ツルガの敦賀伸吾社長。1999年に父が始めたネジ卸に入社。2003年から事業改革に着手し、2004年に社長就任。2013年末にはネジ卸の取引先からすべて撤退した(写真:大亀京助)
「父が開拓した取引先からの撤退を進めていくのはきつかった。私がこれまで育ってこられたのも、取引先あってのことだった」
父が始めたネジ卸に入社し、2004年に後を継いだツルガ(大阪府東大阪市)の敦賀伸吾社長は、ネジ卸から2013年に撤退。ネット経由でネジの企画から請け負うファブレスメーカーに転換した。
ツルガは1976年の設立。自動車部品メーカーなどネジの販売先を創業者の父が開拓し、ネジの製造を東大阪周辺の専門工場に委託する仕事を手掛けてきた。卸ではあるが、納入先は特定の工場に決まっていた。
敦賀社長が父の会社だったツルガに入ったのは1999年。当時は、製造業で新興国との競争が厳しくなり始めた時期。ネジは1本1円足らずの安いものだが、ツルガはさらに厳しく値下げ要請を受けるようになった。
その一方で、海外製品との競争の中で、部品メーカーからのネジの品質要求も厳しくなった。敦賀社長が入社して最初の仕事は、納入先から「不良品が多い」と呼び出され、10万本のネジを全品検査することだった。
しかし、相手の工場を訪れてみると、契約時に定めた品質は十分満たしていた。これ以上に高めるなら製造を委託するネジ工場の品質管理を強化してもらうしかない。ネジを発注していた工場にそのことを伝えると、「品質を求めるなら、ネジの価格を上げさせてくれ」と、単価アップを求められた。
敦賀社長は、自動車部品メーカーなどの納入先と、ネジ工場の板挟みになると、今後ますます利益が圧迫されるようになるとみた。しかし、この立場でいる限り、ネジの仕様は決められており、利益率の高い独自製品を投入することはできない。しかも、安定して仕事が入るメリットはあるが、相手が生産を縮小したら、その影響をもろに受けてしまう。
そこで、敦賀社長は、顧客の相談に乗って企画・設計段階からネジを受注するファブレスメーカーになろうと考えた。特殊なネジならば単価が数十円というものもあり、利幅も大きくできる。それに、取引先が広がり、特定の取引相手の業況に左右されない安定した事業にできる期待もあった。
ただ、敦賀社長には、ネジ卸からの撤退に躊躇(ちゅうちょ)もあった。ネジ卸をやめることは、父が苦労して開拓した、自動車部品メーカーとの取引をすべて断る形になるからだ。父に撤退について相談するたび、けんかになった。
「長年世話になった取引先に迷惑をかけるのか」「安定した仕事を確保できる保証はどこにもないぞ」と怒鳴られ、その様子を見ていた母にも、「ネジ卸をやめて大丈夫?」と心配された。敦賀社長の決意は揺らいだ。
これまでネジを工場に発注するために雇っていた主婦パートも、新しい仕事への不安を口にした。今までは決まったネジの型番と数を工場に伝えるだけで済んだが、今度はお客から幅広い注文を受け、それを工場に伝える複雑な仕事になる。敦賀社長は父から会社を継いだものの、どうしたら両親や長く働いてくれているパート社員たちに既存事業からの撤退を納得してもらえるかと悩み続けた。
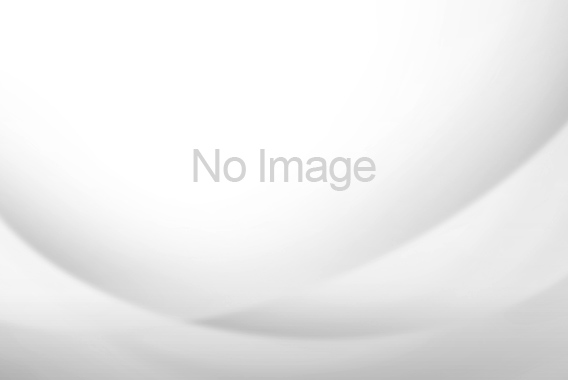
特定メーカーの下請けをやめ、ネットから広く注文を受ける形に転換した
ネジ卸の仕事をやめると売り上げが何割減り、ファブレスメーカーとして同水準の売り上げを確保できるまでには何年かかるか。敦賀社長はシミュレーションを繰り返し、さまざまな課題に優先順位をつけることから始めた。
顧客管理システムの整備といった設備投資の資金は足りるか、今までの従業員で無理なく新しい仕事を回せるのか、新しい市場で顧客が確保できるのか。事業の転換に必要な要素を洗い出し、その実現可能性を1つずつ確かめては自らの自信に変えていった。
2008年にはネジ卸を続けながら、ネット経由で広くネジの受注をする通販サイト「ネジクル」を立ち上げ、特殊ネジの受注もスタート。通販サイトを立ち上げると、研究機関や飲食店など、今まではまったく縁のなかったところからも注文が入るようになった。
なかなか注文が入らないときには、父を説得しようとしていた敦賀社長自身が「自分が間違っているかもしれないと、めげそうになったこともあった」という。しかし、実績ができると自信がつき、けんか腰だった父も敦賀社長の話を聞いてくれるようになった。
サイト開設から2年後には、それまで最大の顧客だった自動車部品メーカーとの取引から撤退できた。「今以上安い価格では取引を続けられない」と率直に説明し、理解を得た。
2013年末にはネジ卸としてのすべての取引先から撤退を終えた。そして、ネジ卸だけの時代に比べると、ネジ1本当たりの粗利を2割以上多く確保できるようになった。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2016年2月)のものです
執筆=敦賀 伸吾(つるが・しんご)
株式会社ツルガ代表取締役社長。1999年に父が始めたネジ卸に入社。2003年から事業改革に着手し、04年に社長就任。13年末にはネジ卸の取引先からすべて撤退し、ネット経由でネジの企画から請け負うファブレスメーカーに転換した。
【T】