
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
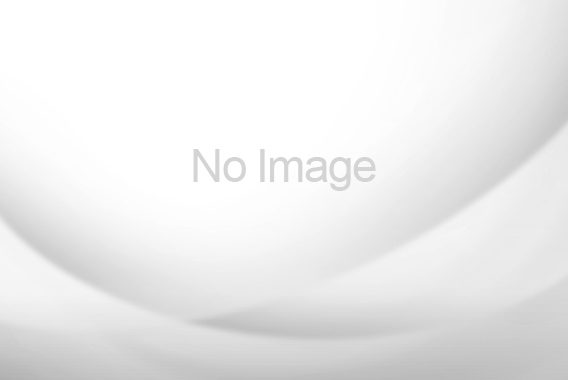 IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)、ロボティクス技術、3Dプリンターなど、さまざまな革新的技術が全世界の人々の暮らしを劇的に変え始めています。本コラムでは、産業の大パラダイムシフトを迎えた今日において、世界中で日々生まれるニュービジネスを紹介します。
IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)、ロボティクス技術、3Dプリンターなど、さまざまな革新的技術が全世界の人々の暮らしを劇的に変え始めています。本コラムでは、産業の大パラダイムシフトを迎えた今日において、世界中で日々生まれるニュービジネスを紹介します。
まずは、世界中に広まりつつある「シェアリングエコノミー」という経済システムの新サービスです。シェアリングエコノミーとは、不動産などの資産、モノやノウハウ、サービスといった資源を、必要とする人に必要なときに提供し、皆で活用する新たな経済のことです。代表的なものとしては、民泊、ルームシェア、タクシー配車などがあり、提供者と利用者を仲介するサービスで、マッチングビジネスの一種です。
急速な広がりを見せるシェアリングエコノミーの世界で、ロシアでは「Umer」(ウーマー)という、遺族と葬儀関連サービスをマッチングさせるビジネスが登場しつつあります。
ロシアの人気天気情報Webサイト「ヤンデックス・フォーキャスト」のオーナーである、ドミトリー・ゲラニン氏が開発したUmerは、葬式に関するマッチングビジネスサービスです。
Umerの使い方は非常にシンプルです。利用者がUmerを起動すると、亡くなった人の情報を入力する画面が表示されます。そこに亡くなった人の名前や、亡くなった日、宗教のタイプ、住所などを入力すると、条件に合った斎場や霊園の情報が料金と共に5分以内に提示されます。このとき、オプションで火葬か土葬の選択をしたり、墓石、棺おけ、花を注文したりすることもできます。
ここで提示された条件に利用者が納得すれば双方合意となり、マッチングが成立します。マッチングが成立すると葬儀コーディネーターが実際の式をつかさどるという流れになります。
Umerは操作が簡単で、普通の葬式の手続きよりも迅速に簡単に事が運べ、料金も明朗だとゲラニン氏は説明します。さらに亡くなった際に、必要な提出書類の代行作成もしてくれます。
人生の終点である死と密接なものである葬式をマッチングさせるというアイデアは、ロシア国内でも賛否両論を呼んでいます。ビジネス自体の趣味が悪いと批判する声や、先行する自動車配車アプリ「Uber」(ウーバー)の社名をダジャレにした名称は不謹慎だという声、あるいはロシアのインターネット普及率の低さから、利用が広まるとは思えないという声などが上がっているそうです。
Umerで大きな課題となっているのは、葬儀や埋葬における細かい条件をどのように料金設定するかという問題です。例えば亡くなった人の遺体の処理方法、遺体の運搬方法と距離、棺おけや墓石の選択、土葬の場合は誰が穴を掘るのかといったことを、Umerはすべて取りまとめ、それらにかかる費用を算出する必要があります。よって単に移動手段を提供するライドシェアリングのUberのように、簡単にサービスを提供するのは難しいのでは、という指摘もあります。
この他にも、「リピーターに特典はあるのか」「知人を紹介すると割引が受けられるのか」など、サービス自体をちゃかすような質問が投げ掛けられています。
それでもゲラニン氏は強気です。同氏によると、すでにベラルーシとエストニアの企業とフランチャイズ契約の交渉を始めており、ロシアでの事業立ち上げが完了したら、直ちにロシア以外の国でも事業を展開すると息巻いています。
ロシアを含むヨーロッパでは斎場や霊園を紹介するサービスはいくつかあるものの、Umerのように本格的なマッチングビジネスは展開されていません。Umerほど積極的にマーケティングしている会社はなく、「利用者はUmerを記憶し、必要なときに必ず利用してくれる」とゲラニン氏は期待しています。
シェアリングエコノミーのさらなる拡大を見越して、日々さまざまなマッチングビジネスが生まれていますが、当然ながら、すべてが成功するわけではありません。
マッチングビジネスを成立させるには、前提として一定のユーザーニーズが存在する必要があります。Umerの場合は、葬式という一定のニーズを対象にしている点において、クリアできているといえるかもしれません。ですが、ユーザーニーズの発生頻度、提供するサービスの多様性、ユーザーの意思決定にかかる各種の要素など、乗り越えなければならない課題は決して少なくないでしょう。
Umerは果たして成功するのでしょうか?実際のところ、これはやってみないと分かりませんが、いずれにせよ、死という領域にもマッチングビジネスが浸透し始めたという点は注目すべきことといえるでしょう。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2017年2月20日)のものです。
執筆=前田 健二
大学卒業後渡米し飲食ビジネスを立ち上げ、帰国後海運企業、ネットマーケティングベンチャーなどの経営に携わる。2001年より経営コンサルタントとして活動を開始。現在は新規事業立ち上げ支援を行っている。アメリカのビジネスに詳しく、特に3Dプリンター、ロボット、ドローン、IT、医療に関連したビジネスを研究、現地から情報収集している。
【T】