
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
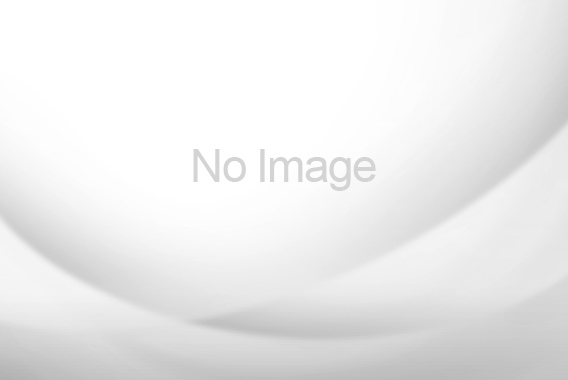 働き方改革を推進するツールとして、このところ大きな盛り上がりを見せるRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)。人手不足に悩む企業や、業務効率化をめざす組織で注目の的になっている。
働き方改革を推進するツールとして、このところ大きな盛り上がりを見せるRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)。人手不足に悩む企業や、業務効率化をめざす組織で注目の的になっている。
アプリケーション操作を自動化する仕組みは以前から存在する。代表的なのはExcelのマクロ機能だ。では、ExcelのマクロとRPAはどこが違うのか。簡単に説明すると、ExcelのマクロはExcel上での作業しか自動化できないのに対し、RPAは複数のアプリケーションをまたがったパソコン操作(アプリケーション起動、データ入力、照合、保存、終了の繰り返し)を自動化できる。つまりRPAは、定型的な業務の多くを自動化するポテンシャルを秘めている。単一のアプリケーション作業しか自動化できない従来のツールとは、一線を画す。
RPAのメリットは省力化だけではない。人為的ミスの減少も実現する。単調で定型的な作業をRPAは正確に繰り返す。手順を教え込むだけで、導入初日から即戦力として活躍するのは大きな魅力だ。
RPAツールは現在、ITベンダーから数多くの製品が提供されている。ツールにはそれぞれ特徴があるが、各ベンダーは欠けている機能を次々と追加し、違いは見えにくくなってきた。そこでRPAの活用フローに応じ、その部分に強い、または力を入れているツールにどんなものがあるかを紹介していこう。
初めに確認しておきたいのがRPAの活用フローだ。通常、「業務の“視える化”」→「ツールの選択」→「ロボットの作り込み」→「継続的な改善」と進む。RPAは導入したら終わりではないところに注意したい。
まず「業務の視える化」では、ロボットにどんな仕事をさせるかを決める。パソコンを使う業務は多岐にわたる。単純な定型作業であっても、操作手順はユーザーごとに違う。漠然と「効率化したい」という捉え方では、たちまち行き詰まる。まずは日ごろ行っている仕事について、個々の詳細な内容と構造を明らかにしなくてはならない。これが「業務の視える化」だ。
RPAツールを提供する多くのITベンダーは、ロボット化の対象となる業務の選定に協力してくれる。社員への聞き取り調査を実施するなどの、コンサルティングサービスだ。
世界トップクラスのユーザー数を誇るRPAサービス「Automation Anywhere(オートメーション・エニウェア)」を扱う販売代理店がいくつかある。その1つである日立ソリューションズは、業務を視える化する導入コンサルティングを行う。別の販売代理店ビットも導入コンサルティングのメニューを持つ。視える化の部分は、製品によって違うというよりも、提供企業によってサービスが変わるといえる。
面白いところでは、NTTスマートコネクトが「AIログ分析」というサービスを、トライアルで提供している。通常、コンサルタントが業務の視える化に取り組むところを、AIがパソコン操作のログを分析して業務を視える化する。
<業務の視える化の選択肢>
・コンサルタントなど専門家による視える化
・AIなど専門ツールによる視える化
業務の視える化で現状の問題点(ロボットで効率化したい部分)が見えてきたら、具体的なRPAツールの選択を始める。RPA提供ベンダーがコンサルティングを行っている場合は、ほぼ自動的にベンダー提供のRPAツールを導入することになる。
いくつかのRPAツールを挙げながら、選択ポイントを解説していく。ツールの選択基準は、2019年1月7日時点の公開情報を基にBizClip編集部で判断した。今後、各ツールの機能や提供方法が変わることもあるので、導入検討の際は各ITベンダーに確認してほしい。
<RPAツールの例>
まず確認したいツール選択ポイントはRPAを使う「ユーザー数」だ。何体のロボットが必要かによって、導入するツールも違ってくる。多くのRPAツールはライセンス数で利用料金が変動する。大規模ユーザーに向いているものと、小規模から対応するものがある。ほとんどの規模に対応するRPAツールもある。自社の導入規模に適しているかどうか、各ITベンダーに確認しよう。
次に、RPA導入に際して注意したいのが、「ロボットの作り込み」という作業だ。従来のITシステムは、「納入したら即運用可能」な製品が多かった。RPAは事前にロボットの動作手順(シナリオ)を作成し、十分なテストを繰り返した上で稼働させる。言い換えれば、RPAは使える状態に仕上げて初めて使い物になる。そのままではまったく役に立たない。
ロボットの作り込みにおいて、RPAツールは大きく2つに分かれる。プログラミングが必要なツールと、ノン・プログラミングのツールの2つだ。前述したRPAツールでいうと、Automation AnywhereとBlue Prismは前者であり、プログラミングが必要だ。一方、NEC Software Robot SolutionやUiPath、WinActorは、プログラミングなしでロボットが作れる。
こう書くと、プログラミングなしのほうがいいと思うかもしれないが、プログラミングでロボットを作るほうが、自由度が高く自社のニーズに合わせやすい。
開発とテストが完了すると、いよいよ実戦配備だ。しかし多くの場合、「こうしたほうがよいのでは?」などの指摘が現場から次々と出てくるだろう。効率よく仕事をこなすためには、継続的改善が欠かせない。
すでにRPAを導入済みの企業で、最近問題になっているのが「野良ロボット」だ。管理者が不明のまま放置されたロボットの意味で、ユーザーが意図しない勝手な動作を行ったり、誤った処理を延々と繰り返したりといった深刻な事態を引き起こす。だから一元管理ができるかどうかは、改善プロセスに大きく影響するといえる。
例えば、BasicRoboは複数のロボットをサーバーで一元管理し、統合的に運用監視する。野良ロボット発生を防止しやすい。また、SynchRoidはロボット開発担当者向けにeラーニングや教室型研修などのメニューを用意し、手厚いサポート体制を整備している。
<継続的な改善のために有利な特徴>
・RPAがサーバー型で一元管理機能がある
・販売代理店のサポートが手厚い
いいことずくめに見えるRPAにも課題はある。それは、満を持して導入されたものの、ほとんど使われず放置されてしまうことだ。RPA活用のスタートダッシュに失敗すると、ロボットの多くは現場から「使えない」と評価されて放置される。使えるロボットに育てるには相応の手間がかかる。認識しておこう。
RPA導入の成功ポイントは、RPAに対して過度な期待を寄せず、担当させる業務を事前に絞り込むことだ。導入前に定型業務の手順を再確認し、RPAが効果的と思われるパソコン操作に、ピンポイントで使う姿勢が大切となる。また、顧客情報など重要なデータを扱う業務システムにアクセスする場合は、セキュリティの確保にも十分配慮したい。
少し前まで「一部の大企業が使いそうなもの」と思われたRPA。最近は企業規模を問わず、あらゆる業種で導入が進んでいる。生産性向上へのステップとして検討する価値は大きいといえる。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=Biz Clip編集部
【M】