
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
ライフスタイルアクセント 山田敏夫社長
――日本初のファクトリーブランド専門ECサイト「ファクトリエ」を立ち上げ、今アパレル業界のみならず各界から大いに注目されるライフスタイルアクセント代表・山田敏夫氏。“日本の工場から、世界一流のブランドを作る”という目標を掲げ、通常は顧客の目には触れないアパレル工場の名前をブランドの一部として表舞台に引っ張りだした。これまでの経緯とその狙いを聞いた。(聞き手はトーマツベンチャーサポート事業統括本部長、斎藤祐馬氏)
斎藤:まず「ファクトリエ」とは一体どんなものなのですか?
山田:ファクトリエは日本のアパレル工場と一般の消費者をつなぐ通販サイトです。もともと工場の意味の「ファクトリー」とそれらが集まる場所である「アトリエ」を足した造語です。
斎藤:工場? それは例えばどんな工場でしょうか。
山田:実は日本には、世界の一流ブランドを手がけている無名だけどもすごい工場があります。それこそアルマーニやエルメスやシャネルにヴィトンだって、一部のものは日本の工場で作られている。一方で、過当競争や職人の高齢化で工場が激減している。本当に価値のあるメイド・イン・ジャパンって何だろうと。そんなことを考えていくうちに日本全国にある最上級のものを作っている工場を探そうと思いついた。
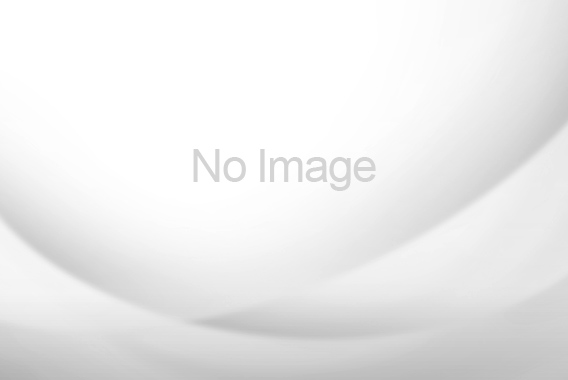 ――山田さんはもともと熊本市内で創業1917年と100年近い歴史のある婦人服店の次男だ。将来的に店を継ぐことを考え、ファッションを学ぼうとフランスに留学。方々に手紙を書いて、なんとかグッチのパリ店にもぐりこんだ。その有名ブランドで働くスタッフたちはエルメスやヴィトンなど横のつながりも強く、またみな販売員という仕事にも誇りを持っている。そこであることに気付かされたという。
――山田さんはもともと熊本市内で創業1917年と100年近い歴史のある婦人服店の次男だ。将来的に店を継ぐことを考え、ファッションを学ぼうとフランスに留学。方々に手紙を書いて、なんとかグッチのパリ店にもぐりこんだ。その有名ブランドで働くスタッフたちはエルメスやヴィトンなど横のつながりも強く、またみな販売員という仕事にも誇りを持っている。そこであることに気付かされたという。
山田:例えばエルメスの販売員が研修で工房見学へ行くわけです。そうすると、職人が1つの革製バッグの全行程を1人で丸縫いしている。約20時間、丸2.5日もかけてやっている。だからケリーバッグは50万円もするわけです。しかも裏側には手がけた職人の番号が書いてあって、修理の際には必ず自分のところに戻ってくる。
面白いのがその工房は親子3代で受け継がれていたりして、亡くなった先々代が手がけたものの修理を孫が引き受けて、やっぱりすごい作りをしていたんだな…なんて見ることができたりする。彼らの文化にはやはり物づくりが一番の根っこにあって、その先にコレクションや流行のカラーや販売戦略がある。
日本のアパレルブランドの状況を尋ねられて、ワールドやオンワードやユニクロや無印良品やいろいろあると答えたんです。そうしたら、それって物作りじゃないよねと。小売りだと。そういうものはブランドじゃないと大まじめに否定されたわけです。世界で本物のブランドは物づくりありきだと。「日本には本物のブランドはない、いずれ中国のほうがブランドになるかもよ」と言われるわけです。
それはもうショックでした。そのときに売り言葉に買い言葉で、「日本の工場からお前たちがびっくりするような世界ブランドをつくってやる!」みたいなことを言ったのが、今のファクトリエにつながる最初のきっかけです。
斎藤:「本物のブランドをつくる」と意気込んで帰国したと。そこでいきなりファクトリエを思いついたのですか。
山田:いや、普通に日本の企業に就職しました(苦笑)。2002~2003年当時はアパレル業界が下降線の一途で、親戚一同がこの業界への就職を止めるわけです。その時に読んだ孫(正義)さんの『志高く』という本に、インターネットというのはこれから一番大きな可能性を秘めているとあった。そこでソフトバンク系のベンチャー企業に入りました。4年間いてインターネットを学んだあとに、アパレル系のイベントやネット通販をやっている会社に移りました。イベントを手がけるなど色んな経験をさせてもらいました。
ちょうどその頃にFacebookが流行りだして、フランス時代のグッチにいた友人たちと一気につながったわけです。そこで「ブランドはできたか」と聞かれたんです。みんな本当によく覚えているんですよ。
自分でも分かってはいたんです。忘れていたわけではないんですけど、僕がそのときにやっていたのは、中国、韓国ですごく安く作って輸入して、モデルに着せてランウェイを歩かせて、1ステージで何億売るかみたいなことだったわけです。そして、今から3年ほど前にこれじゃダメだと思うようになったんです。
斎藤:具体的に何がダメだと思ったのでしょうか。
山田:アパレル業界はすでにかなりの飽和状態だと思っています。お客さんもお腹いっぱいなのに、安いから、セールだからと買っている。それは本当に欲しいものなのかと。アパレル業界って100のうち3つの型がヒットしたら、それを急いで追加で作って、残ったらセールで売って、ファミリーセールもやって。それでも売れないものは捨てる。年間40億着のうちの約半分、20億着が廃棄されている、異常な世界なんです。
斎藤:一部だけ切ってみると利益率はものすごく高く見えるけど、全体で見ると実際はすごく低いということですね。
山田:そうなんです。だから原価率20%ほどで、セールでは70%オフになるものもある。もう訳が分からない状態ですね。
斎藤:山田さんがやろうとしていることはある意味、アパレル業界の構造改革であり、工場が幸せになることで、消費者も幸せになるといえますね。
 山田:そうですね。インターネットやネット通販の仕組み、物流については一通りやってきたので分かった。あとは日本の工場で物づくりをと考えたときに、もうそれが絶滅危惧種だと知るわけです。手元にあった50万円を資本金に動きはじめたのが2012年のことでした。
山田:そうですね。インターネットやネット通販の仕組み、物流については一通りやってきたので分かった。あとは日本の工場で物づくりをと考えたときに、もうそれが絶滅危惧種だと知るわけです。手元にあった50万円を資本金に動きはじめたのが2012年のことでした。
斎藤:今、アパレル工場は日本にどれぐらいの数があるんですか?
山田:1980年に6万5000あったといわれる事業所数が、今はだいたい7000~8000ぐらいです。国産比率でいいますと、1980年に50.5%あったものが、2012年には3.7%まで減っています。全盛期の約10分の1です。このまま時代に流されると本当にゼロになってしまうかもしれない。でも今ある工場の中には、世界遺産と呼べるくらい素晴らしいものがある。それをなくしちゃいけない、という思いがあった。
斎藤:なるほど。そこで先ほど話にあった、工場と消費者をつなぐというイメージは分かるんですけど、具体的にこれまでのアパレル製造や販売と何が違うのですか。
山田:これまでにもいろいろな工場が、自前で楽天などのECサイトに出してみるなど、そういう試みはあったと思います。でも、いいものは作れるんだけど、製品を魅力的なものとして変換できないし、お客に届ける術がなかった。やはりデザインもマーケティングもセールスもPRも必要です。だから僕たちはその変換装置としての機能をするわけです。
斎藤:しかし、そういうマーケティングやセールスを代行するような取り組みはこれまでにもあったと思うのですが。
山田:もちろんそうですが、まず誰も直接工場にアクセスしていなかった。安いじゃなく腕のいい工場を探したいわけです。でもアクセスしようとしてもホームページもないわけで、探しようがないのです。
日経トップリーダー/藤野太一
執筆=斎藤 祐馬
※トーマツ ベンチャーサポートは、2017年9月1日より「デロイト トーマツ ベンチャーサポート」に社名変更しました。
【T】