
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
都市への人口集中が続く中、過疎地域が日本中で増加している。地域の人口減による市場縮小は、多くの分野で供給側の撤退・新規進出敬遠を招く。それが、さらなる人口減少・市場縮小を生むという負のスパイラルに陥っている。
供給側の撤退・新規進出敬遠が、国の根幹である教育に及んでいることも問題視されている。市場規模の小さい地方は都会と比べて予備校や塾が少ないといった教育機会の格差が存在するからだ。子どもの将来を考えると、いくら自然環境が良くても、教育レベルが低くては子育ての場所に適さないのではないか。そんな問題が地方活性化の妨げになりかねない。
文部科学省の「学校基本調査」を基に高等学校卒業者の大学への進学率を計算すると、全国平均では約54.5%になる(平成27年度速報値)。一番高いのは東京都で約66.8%。60%を超えているのは京都府、神奈川県、兵庫県、奈良県、広島県の順で6つ。一方、北海道、東北の各県はすべて40%台、九州も福岡が50%を超えている以外は軒並み40%台で、沖縄は40%を下回っている。人口が集中する“都市圏”を抱える都府県のほうが、大学進学率は高い傾向が顕著だ。
大学進学率を左右する要素は、地元にある大学の校数、親の年収や学歴などさまざまなものが考えられるが、都市と地方の教育機会の格差も見逃せないだろう。人口が多くて市場規模が大きい都市部には、多くの塾や予備校がある。優秀な人材やノウハウを備えた塾や予備校がしのぎを削っている状況だ。
一方、地方、特に過疎化が進行している地域は、市場規模が小さく塾や予備校にとって魅力的とは言い難い。優良な教育環境がなければ、どうしても大学進学率は上がりにくい状況になる。子どもを大学に進学させたい親は、それを理由に都市部へ流出してしまう。これも人口減がさらに進む要因の一つといえるだろう。
地方が人口減を食い止める手段として、都市部から「Uターン」「Iターン」による移住を促す手段が考えられる。しかし、自然が豊かで、物価も安いという地方の魅力だけでは、子どもの将来を考える子育て世代を誘引するのは難しいだろう。やはり教育環境も充実している地域で我が子を育てたいと考える親心にも応えないと、移住希望者はちゅうちょしてしまうのではないだろうか。
そんな地方で、教育環境の整備を実現する追い風になってくれそうなのが「eラーニング」だ。eラーニングとは、 ITなどの情報通信技術を用いて行う学習システムのこと。eラーニングで近年注目を集めているのが、ライブ配信による遠隔授業だ。これにより各教室に専任の教師を配置しなくても、都市部と同じ高レベル授業を地方でも実施できる。
学ぶ側の手段や環境も多様化してきた。学びたいときにすぐ適切な動画コンテンツを見ることができるビデオ・オン・デマンド、リアルタイムに遠隔地にいる教師に質問などが可能な双方向のオンライン授業、パソコンやスマートフォンでいつでもどこでもインタラクティブに学習を進められる自習教材など、さまざまな工夫を凝らしたeラーニングシステムが提案・構築されるようになってきている。
eラーニングを活用して教育の地域格差をなくす目的で設立されたNPO法人も現れている。例えば「特定非営利活動法人みやざき教育支援協議会」では、eラーニングを使って、教育格差をなくす実験検証を行ったり、各種研修会、生活困窮世帯の学習支援を行ったりしている。また、地方自治体やNPO法人と、教育関連企業がコラボレーションするパターンも目立っている。例えば、リクルートマーケティングパートナーズの「勉強サプリ」は、認定NPO法人カタリバとのコラボレーションにより、岩手県大槌町で一流カリスマ先生のオンライン授業を開講した。
そのほかにも、フィオレ・コネクションは「オンライン双方向授業」で、現役東大生講師と過疎地域の子どもを結ぶ試みを実施している。さらに、シンドバッド・インターナショナルでは、高知県の公立中学・高校と映像授業の学習効果を共同検証した。こうしたeラーニングを使った教育格差是正プロジェクトが各地で動いている。
また、シンドバッド・インターナショナルは「住んでいる地域や経済的な理由による教育機会の不平等を解消したい」という姿勢を示しており、日本最大級のeラーニングサイトとうたっている「スタディ・タウン」も運営している。ほかに「スクールTV」を配信するイー・ラーニング研究所も、eラーニングを活用することで経済格差による教育格差のスパイラルを解消していきたいという思いを示している。
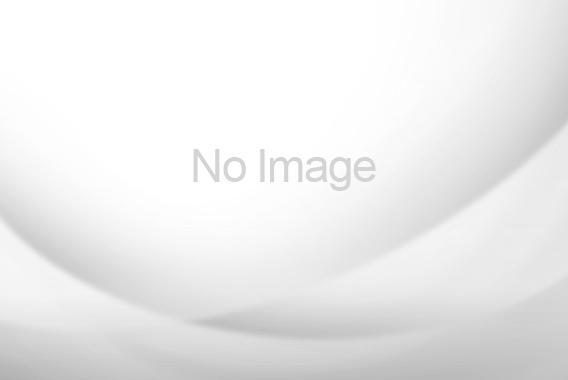
eラーニングで地方を救うためのIT人材の育成を打ち出している企業もある。オンラインプログラミングスクール「CodeCamp」を運営するトライブユニブは、政府が掲げる地方創生の考え方に賛同し、オンライン学習教材やオンライン学習システムなどを無償で提供し、地方におけるIT人材育成を支援する。
このような各種取り組みが、全国各地ですでに始まっている。eラーニングで教育環境を整え、教育の地域格差を解消すれば、アピールポイントの一つとして訴求できることや、将来的な定住化を促進することも可能になるなど、教育環境への不安感による人口流出を防ぐ一助となるかもしれない。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【MT】
少子化時代を生き残る塾・予備校・専門学校のIT戦略