
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
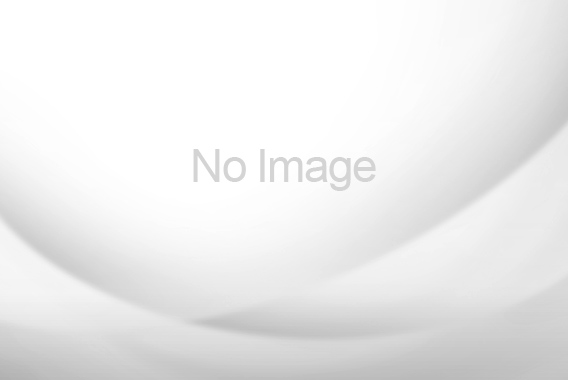
次は「何をほめるか」について説明します。先の例(成果を上げた部下A)で考えると、当然ほめるべきポイントは「成果を上げたこと」であり、基本的にはこれ以外の選択肢はありません。
しかし、それだけでは「Aさん、今回の成果は本当に素晴らしいね」という一言で終わってしまいます。前述のように1つの成果は複数の人の見えない努力が結実した結果です。企業にとって最も大切なのは成果や実績であることは間違いありませんが、それをもたらした社員にとっては準備や失敗を含めた過程を経て、その成果が生まれます。
つまり、ここでのポイントは「成果をほめるときは、成果そのものだけでなく、そこに至るプロセスを含めてほめる」こと、そして「部下にとっては、過程や準備期間や失敗も含めてその成果があるということを、上司がきちんと理解しておく」こととなります(図表2参照)。
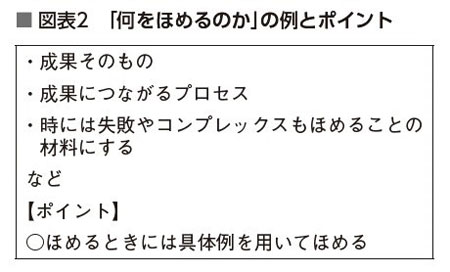
重要なのは、ほめる際には「具体的にほめる」ことです。例えば「今月はみなさんのおかげで目標が達成できた」と全体的にほめるより、「今月はみなさんの頑張りのおかげで、売り上げが前月比15%もアップした」というように具体的な数値を盛り込んでほめるほうがほめられるほうもうれしいですし、上司としても今回の成果のポイントを部下に伝えやすいというメリットがあります。
また数値で表しにくいプロセスをほめる際にも、「いつもより2日も早く仕事が仕上げられて助かった」や「あなたが毎日お客さまの元に通ってくれたから今回の契約につながった」など、数値以外の部分も具体的な表現で盛り込んでほめることが大切です。
また目標が未達成だったり、成果に対して失敗が多かったりしたとしても、仕事のプロセスにほめるべきポイントがあるような場合には、「今回は目標に届かなかったけれど、ここまでまとめてきた資料は次回の企画に再利用できるんじゃないか」などのように、会社に寄与した部分や次回の仕事につなげられる点などを伝えるようにしましょう。
そうすることで部下は今回の結果を気に病むことなく、「今回の努力は決して無駄ではなかった(会社の役に立った)」という前向きな気持ちで次の仕事に臨むことができるようになるでしょう。ミスを指摘して叱ることで、部下が落ち込んだ気持ちを次の仕事に引きずるより、気持ちが前向きになる分、生産的です。ただしミスはミスなので、ほめることに終始するのではなく、反省すべき点も盛り込むようにするとよいでしょう。
執筆=坂本 和弘
1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。
【T】