
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
毎日、社員同士が雑談することで社員が育つ。驚くかもしれませんが、これは事実です。といっても、方法を工夫すれば、という前提条件付きの話です。
具体的な方法を紹介する前に、なぜ雑談が重要なのかについて、少し解説させてください。最近は業務効率化という掛け声の下、職場で雑談するのは好ましくないという風潮があるように思えます。確かに、長々と雑談をして肝心の仕事が手につかないのは考えもの。しかし、遠回りに見えて、実は雑談にはさまざまな効果があります。
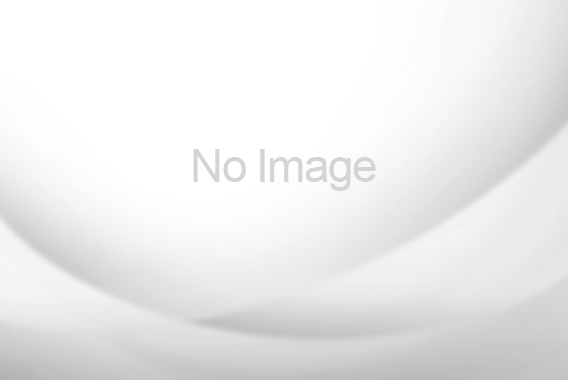 では、雑談の効果とは何か。まず仕事と直接関係なくても見聞きしたことを自分の言葉で表現すると、物事を頭の中で整理する訓練になります。これは周囲から得た知識を「自分事」として捉え、後に知恵として生かすことにつながります。
では、雑談の効果とは何か。まず仕事と直接関係なくても見聞きしたことを自分の言葉で表現すると、物事を頭の中で整理する訓練になります。これは周囲から得た知識を「自分事」として捉え、後に知恵として生かすことにつながります。
また、雑談で他の人から聞いたさまざまな情報に関心を持つことによって興味が湧き、より詳しく調べるきっかけにもなります。そもそも雑談をするには、それなりにネタが要ります。そのネタを仕入れるために、日常生活の中でちょっと新しい体験をしたり、身の回りで起きた出来事を注意深く観察したりするようになります。
さらに、他人の話を聞くことで、自分と異なる価値観を持つ人がいることをあらためて認識でき、相手に対する理解が深まります。
どんな事象、どんな人物にも自分が知らないプラスの面があります。関心がないものから目を背けず、積極的に接点を持てば、新たな気付きや刺激を受けることができます。これが各社員の視野や考え方の幅を広げるのです。慣れ親しんだ物事や人物ばかりに目を向けていては、ものの見方や思考が偏り、なかなか成長は見込めません。つまり雑談は、社員が知恵として生かせる知識を身に付けたり、視野や考え方の幅を広げたりするのにうってつけ。だから、社員が成長する源泉となり得るのです。
雑談の効果を上手に引き出す方法があります。朝の始業時間前や昼休みなどに10分程度時間を割いて、仕事に関係ないことも含めて日ごろ感じていることを社員同士で話し合う機会を設けてみてください。注意点は特定の人が話すのではなく、持ち回りで話し始める人を変えて偏りをなくすこと。最初は同じ部署の社員同士でスタートしても問題はないですが、慣れてきたら他部署のメンバー同士で雑談してみるといいでしょう。
毎日繰り返していると、徐々に社員の態度が変わってくるのが実感できると思います。自分の言葉で話すのが苦手だった人が積極的に発言するようになったり、驚くほど社員が活気づいたりすることがあります。
実際、社員同士の雑談を毎日続けたところ、社員の働きぶりが大きく変わった食品メーカーがあります。この会社では、社員の大半が昼食時に社員食堂を利用しています。しかし、同じ部署のメンバーと食事をする人が多く、部署を超えた交流がほとんどありませんでした。
「これでは新たな発見はない」と判断した私は、他部署のしかも年代が違う社員同士で雑談をしながら昼食を取るようにアドバイスしました。すると、最初はぎこちなかったものの、徐々にコミュニケーションが活発化。半年後には、各社員が他部署の業務内容や部署ごとの役割をよく理解するようになったのです。
その結果、社員同士が自主的に業務を改善したり、進んで協力し合ったりするようになりました。例えば、お客さま相談窓口のスタッフが、顧客からの意見を企画開発や販売促進部門に伝え、パッケージや商品説明の表現を見直すといった具合です。もちろん業績も上がりました。
社員に見聞きしたことを話してもらい、多くの物事や人に関心を持たせる――。雑談をルーティンにして社員を育てる。この点を忘れないでください。
執筆=著者=東川 広伸(ひがしかわ・ひろのぶ)
1969年大阪府生まれ。大阪産業大学を中退し、電気設備工事会社に勤務した後、リクルートの代理店に入社し、営業職で1年目に社長賞を受賞。その後、化粧品会社やインテリア商社に勤務。2004年、自分で考えて動く社員を育てる「自創経営」の創設者で、父の東川鷹年氏による指導の下、自創経営センターを設立、所長に就任した。これまで中小企業を中心に9000人以上の社員を成長させてきた。
【T】
お金をかけずに“ざんねん社員”を育てるルーティン