
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
江戸時代、各藩から将軍家や朝廷に差し出された献上品。地元の特産物からえりすぐったその品々は、藩にとって自慢の逸品でした。この連載では、そんな逸品の中から今に伝わる「将軍様のお気に入り」を、当時のエピソードとともに紹介していきます。
第2回は、福島県の会津地方に伝わる伝統工芸品「絵ろうそく」です。
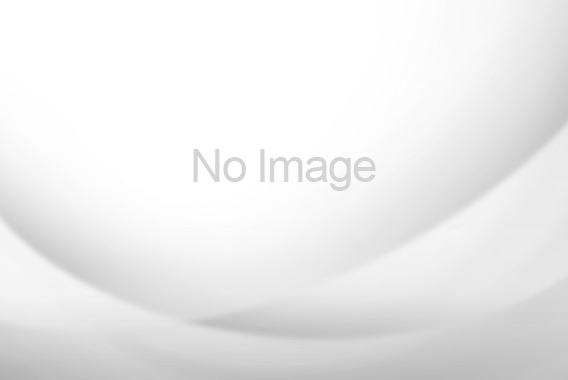 11月7日に立冬を迎え、日に日に寒さが増してくるこのごろ。今回紹介する「絵ろうそく」は、一説によればそんな寒さの厳しい会津地方が発祥といわれています。
11月7日に立冬を迎え、日に日に寒さが増してくるこのごろ。今回紹介する「絵ろうそく」は、一説によればそんな寒さの厳しい会津地方が発祥といわれています。
絵ろうそくとは、北国の雪のような白いろうそくに、菊や牡丹など色鮮やかな花の絵を描いたものです。火を付けるのが惜しくなるこの工芸品は、当時は大変な高級品で、主に将軍家や朝廷への献上品として、あるいは寺社への奉納品となっていました。
もともと会津をはじめとする東北地方では、ろうそくの生産が盛んでした。ろうそくの原料は、樹液が漆器としても使われる漆(うるし)の実。つまり、1本の漆の木から会津漆器とろうそくという2つの工芸品が生み出されていたのです。藩の財源となる工芸品の生産を支えるため、会津藩は“ろう”を年貢として徴収する政策をとるなど、大いに漆の木の栽培に力を入れてきました。
史料によれば、この地方でろうそくに関する記述が初めて見られるのは今から500年ほど前のこと。時の領主・蘆名盛信が漆の木の栽培を奨励したことに始まり、蒲生氏郷や保科正之ら歴代の藩主の努力により、産業として確立していきました。会津藩が19世紀初頭に編さんした地誌『新編会津風土記』には、1576年にこの地方を領国としていた戦国大名・蘆名盛隆が、織田信長にろうそく1000本を贈ったことが記されています。
もともとろうそくの生産が盛んだった会津藩ですが、ろうそくに絵を描くようになったのは、会津地方の気候が関係していました。
豪雪地帯である会津地方は、冬になると生花を入手することが非常に困難になります。深い雪に覆われる冬の間、仏壇に供える花の代わりになるものはないか……。そう考えていた会津の人々は、いつしかろうそくに花の絵を描くことを思い付きます。色彩豊かな絵ろうそくをもって、仏花の代わりにしようとしたのです。
絵ろうそくは人々の祈りが込められた伝統工芸品でした。そんな絵ろうそくらしいエピソードが残っているのが、徳川幕府第5代将軍・綱吉に献上されたときのことです。
初代藩主の保科正之以降、将軍家の守護を自認する会津藩は、生来体が弱かったという綱吉に、何か気の利いた献上品ができないかと思案していました。そこで、ある年の参勤交代の際に、会津藩は南天と福寿草の花を描いたろうそくを献上します。「南天福寿(なんてんふくじゅ)」と呼ばれるこの絵柄に込められたのは、「難を転じて福と成す」という祈り。これに気付いた綱吉は非常に喜び、以来絵ろうそくは会津藩の代表的な献上品となっていきました。このことから、南天福寿は現在まで伝わる絵ろうそくの代表的な絵柄となっています。
明治時代に入ると、より安価で手軽に作れる西洋ろうそくの普及にともない和ろうそくは姿を消していきます。しかし、その中でも1本1本に繊細な花を描く絵ろうそくは、儀式や贈答用に生産が続けられ、現在も福島県の代表的な伝統工芸品となっています。
2001年からはこの絵ろうそくの魅力を知ってもらおうと「会津絵ろうそくまつり」が毎年2月に開催されています。2016年は約1万5000本の絵ろうそくが、雪景色の中で幻想的に輝きました。2017年は、会津若松城などを会場に開催予定です。冬の福島県に出張する際は、ぜひ足を運んでみてください。
お祭りの開催期間外でも、絵ろうそくは福島県のお土産店で手に入れることができ、中には絵付け体験ができるところも。価格は大きさによっても異なりますが、およそ2本入りで1500~3000円ほどです。
徳川綱吉を勇気づけた「南天福寿」の絵ろうそく。ぜひお土産として贈ってみてはいかがでしょうか。
執筆=かみゆ歴史編集部(www.camiyu.jp)
歴史コンテンツメーカー。歴史関連の書籍や雑誌、デジタル媒体の編集制作を行う。ジャンルは日本史・世界史全般、アート、日本文化、宗教・神話、観光ガイドなど。おもな編集制作物に『日本の山城100名城』(洋泉社)、『一度は行きたい日本の美城』(学研)、『戦国合戦パノラマ図鑑』(ポプラ社)、『系図でたどる日本の名家・名門』(宝島社)、『大江戸今昔マップ』(KADOKAWA)、『国分寺を歩く』(イカロス出版)など多数。お城イベントプロジェクト「城フェス」の企画・運営、アプリ「戦国武将占い」の企画・開発なども行う。
【T】