
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
フレーミングにより意思決定の目的が明らかになった。次に行なうべきなのは情報収集。様々な情報を集め、整理して、意思決定の選択肢を絞り込む。このとき、リーダーである中間管理職は、直接情報収集は行なわずに部下の集めてくる情報を取捨選択する立場になることが多い。このような局面で、中間管理職はどのようにふるまうべきだろうか。
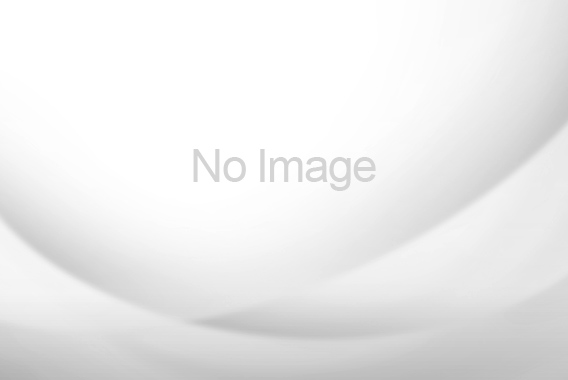 会社の開発室に新しい装置を導入することになった。開発室の課長であるAさんは、この装置を使った開発に長年携わった経験から、装置購入の責任者になり、新人部下のBさんに装置のリストアップを依頼した。翌日、Bさんが送ってくれたリストを見ると、いくつかの候補の中に一つ、非常に安い装置があった。そのメーカーXはAさんの知らない会社であり、Bさんに聞いてみると、ホームページに載っている情報も少なく、よく分からないという。Aさんは低品質の製品を安価で売っているのだろうと思い、結局、候補のリストから外してしまった。
会社の開発室に新しい装置を導入することになった。開発室の課長であるAさんは、この装置を使った開発に長年携わった経験から、装置購入の責任者になり、新人部下のBさんに装置のリストアップを依頼した。翌日、Bさんが送ってくれたリストを見ると、いくつかの候補の中に一つ、非常に安い装置があった。そのメーカーXはAさんの知らない会社であり、Bさんに聞いてみると、ホームページに載っている情報も少なく、よく分からないという。Aさんは低品質の製品を安価で売っているのだろうと思い、結局、候補のリストから外してしまった。
ところが、後で分かったことだが、このメーカーは大手メーカーの社員が独立して最近立ち上げた会社であり、品質上の問題はなかった。また、新しい会社なので取引実績を作りたいと考えており、そのために思い切って低価格のオファーを出していたのだった。
ーーもし、AさんがBさんにより詳しい調査を依頼したり、別の人にも話を聞いていれば、もしかしたら上記のような実情に気づくことができたかもしれない。「自分はこの装置に詳しく、自分が知らないメーカーはない」というAさんの過信により、情報収集が適切に行なわれなかった事例である。
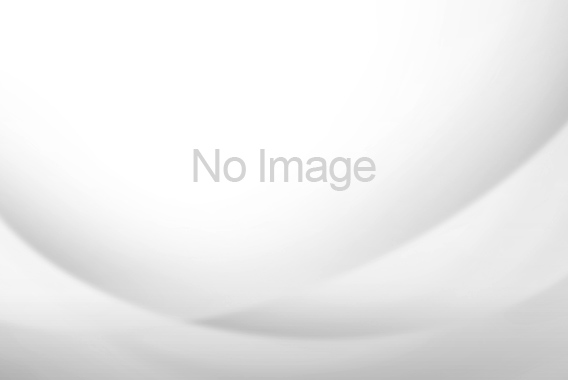 J・エドワール・ルッソ著「勝てる意思決定の技術」の第4章に、「確証バイアス」という概念が紹介されている。一度「自分の考えは正しい」と思うと、多くの情報の中から自分の考えに合致するものを重視したり選択的に認知したりすることをいう。過信というのは、人が最初に持っている自分の予想や予測が、確証バイアスによって増幅されることで生まれる。優秀な人ほど予測に長けているため過信に陥りやすく、せっかく部下が集めてくれた情報を正しく取捨選択することができなくなる。
J・エドワール・ルッソ著「勝てる意思決定の技術」の第4章に、「確証バイアス」という概念が紹介されている。一度「自分の考えは正しい」と思うと、多くの情報の中から自分の考えに合致するものを重視したり選択的に認知したりすることをいう。過信というのは、人が最初に持っている自分の予想や予測が、確証バイアスによって増幅されることで生まれる。優秀な人ほど予測に長けているため過信に陥りやすく、せっかく部下が集めてくれた情報を正しく取捨選択することができなくなる。
情報収集の際、過信を避けるにはどうしたらよいか? それには情報を集めてくれた相手の話をよく聞くことだ。ではどうしたら「相手の話をよく聞く」状況を作れるか? それには「誰にこの情報を集めてもらうのがよいか」を事前によく考えることが重要である。
例えば、先に挙げた装置購入の場合、Bさんが業界に精通していれば、例えばメーカーXのホームページを見たときに、その代表者の名前から事実を知ることができたかもしれない。
一方で、新製品の開発方針を決定するために、自社技術と他社技術を項目別に比較したい場合を考えてみる。会社経験が長い人には「自社技術が最も優れている」という思いが強く、自社技術をひいき目に見てしまいがちな人もいる。いっそのこと、業務経験が浅い新人に調査を任せてみる、というのも一つの手である。
いずれにせよ、「この人なら、自分より公正に情報を集めることができる」と思える人に情報収集を依頼することが重要だ。
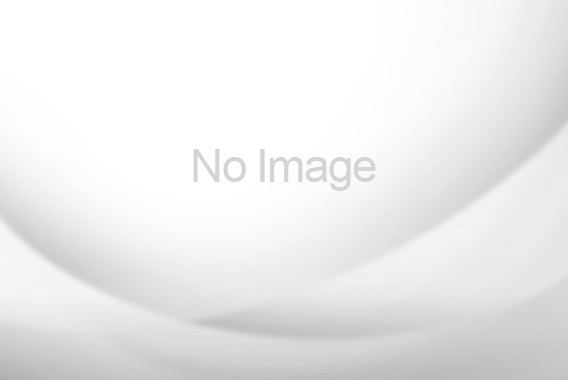 このように、情報収集の段階では、過信により適切な情報の取捨選択ができなくなる。一方で、意思決定を下した後には過信がよい効果をもたらす場合もある。
このように、情報収集の段階では、過信により適切な情報の取捨選択ができなくなる。一方で、意思決定を下した後には過信がよい効果をもたらす場合もある。
Apple社のiPadは、それまでのコンピュータの概念を変える画期的な製品だったが、発表された当初は「何に使うかが分からない」「ノートパソコンがあれば十分ではないか」という意見も多かった。当時のApple社CEO、スティーブ・ジョブズの「この製品の開発に反対する人も多いが私は必ず成功すると信じている」という、過信ともいえる強い意志がなければ、開発という決定が下されることはなかったかもしれない。Apple社は、iPadの開発にあたり、膨大な情報収集をしたはずだ。情報収集を通して、あらゆる可能性を検討してきたからこそ、このような強いメッセージを発することができたのではないだろうか。
「意思決定」と「実行」はまったく別のものである。意思決定を下す前の情報収集の段階では、現実主義者として冷静にふるまうべきである。しかし、ひとたび実行にうつったならば、自分やチームを信じ、楽観的に行動することが最良の結果をもたらすこともある。
執筆=林 きのこ/studio woofoo(www.studio-woofoo.net)
1981年生まれ、京都大学工学部卒。米国研究開発型ベンチャー企業の研究マネジャー。新エネルギー開発プロジェクトを担当する一方で、経済や環境技術関係のコラム執筆も行なう
【T】