
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
上司と部下の板挟みの中で、たくさんの意思決定を行なっている中間管理職。ビジネスや日常生活において、適切な意思決定を行なうためのプロセスを「目的の明確化」「情報収集」「結論の導出」「フィードバック」の4段階に分け、各プロセスを重要なキーワードで紹介する。今回のキーワードは、「目的の明確化」=「フレーミング」だ。
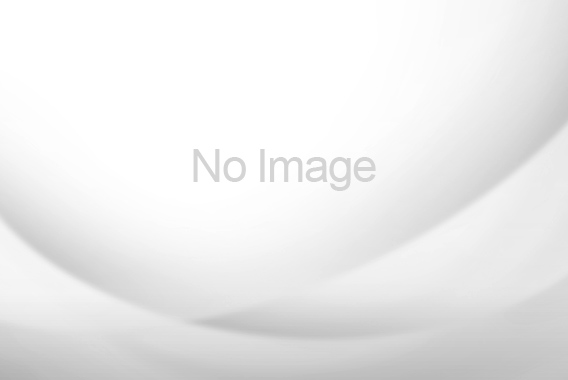 意思決定を行なう上で、まず始めにすべきなのは意思決定における目的やその前提事項を考えることである。これを「フレーミング」と呼ぶ。
意思決定を行なう上で、まず始めにすべきなのは意思決定における目的やその前提事項を考えることである。これを「フレーミング」と呼ぶ。
そもそも、フレーミングとは写真を撮る際に構図(フレーム)を決めることを言う。例えば観光地で写真を撮る場合ひとつとっても、観光地にある景色を美しく撮りたいのか、そこにいる家族の楽しそうな笑顔を写真におさめたいのかによって、自ずと構図は変わってくるだろう。
意思決定でも同じように、まずフレーミングによって、意思決定の構図を決めることが重要だ。
ある家電メーカーで会議があった。会議の目的は、「スマートフォンで操作できる家電製品の開発」。ここでもし、他社メーカーがすでにスマートフォンで操作できるエアコンを開発中で、なおかつ会議に出席しているメンバーのうち数名がそのことを知らないまま議論を交わしているとしたら、どうだろう。また、上層部が他社の状況を知った上で、会議の議題としてとりあげているのかどうかを誰も知らないとしたら? 「他社に先駆けた新製品」の開発と「先行する他社にミートした新製品」の開発では、同じ製品開発でも180度異なることは想像に難くない。このように、フレーミングによって意思決定の目的や前提事項を明らかにしておかないと、議論の焦点がぼやけ、意思決定の精度も下がってしまう。
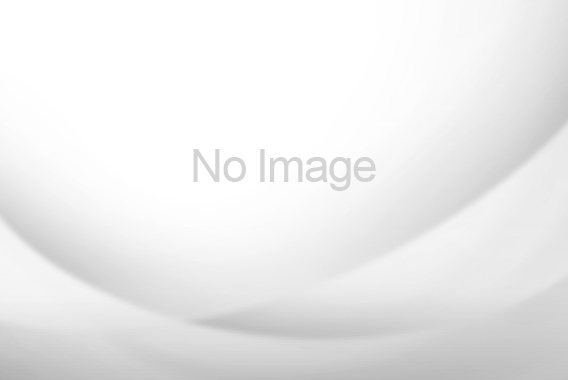 フレーミングの結果次第で、意思決定の方向性が大きく変わる。フレーミングで失敗をしないために、中間管理職が気をつけるべきことは2つある。
フレーミングの結果次第で、意思決定の方向性が大きく変わる。フレーミングで失敗をしないために、中間管理職が気をつけるべきことは2つある。
1つ目は、「目的や前提は人によって異なる」ということ。たとえ働く会社が同じであっても、それぞれの活動の目的は必ずしも一致しない。例えば「良い製品とは何か」という話題について、生産技術部には「効率よく、低コストで生産できるもの」であると考える人が多いだろうし、一方で営業部には「たくさん売れるもの」と考える人が多いのが普通である。自分の上司や部下の立場から物事を考えることで、決めるべきことの目的や前提条件が少しずつ明らかになる。
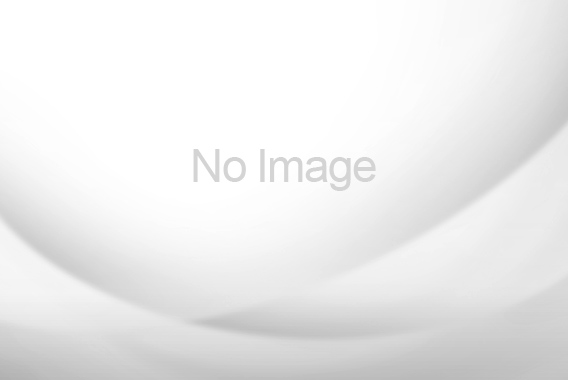 2つ目は、「フレーミングによって削ぎ落とされる要素が必ずある」ということ。
2つ目は、「フレーミングによって削ぎ落とされる要素が必ずある」ということ。
例えば先に紹介した会議の例で、とにかく他社に先駆けて発売することが最重要項目だと仮定しよう。その場合、開発期間を短縮するために、イチから製品を企画することはあきらめて、既存製品の改良での開発を考えるべきかもしれない。また、対応スマートフォンをアンドロイドOSに限定すればアプリ側の開発期間を大幅に短縮できるかもしれない。このようにフレーミングは、意思決定の目的を明確化させるが、それによって削ぎ落とされる要素も明確化させる。ただし、フレーミングにより削ぎ落とされる要素の中に、外してはならないものが含まれていないか、慎重に吟味をすることが重要だ。
フレーミングとは窓枠のようなもの。窓に近すぎると窓枠に気づかないように、自身のフレーミングに気づくことは、簡単なようで難しい。これらに気づくには、窓から一歩後ろに下がればいい。つまり、自分を客観的に見ることが大事だ。「自分はなぜ、会議であんな発言をしたのか?」「自分はなぜ、このメニューを注文したのか?」「なぜ、8番アイアンで打つことにしたのか?」。
一歩引いて自分の決断を眺めるクセをつけることで、目的や前提条件に気づき、上手にフレーミングを行なえるようになるはずだ。
【参考書籍】
勝てる意思決定の技術 J・エドワール・ルッソ、ポール・J・H・ショーメーカー著 ダイヤモンド社出版 2003年2月
執筆=林 きのこ/studio woofoo(www.studio-woofoo.net)
1981年生まれ、京都大学工学部卒。米国研究開発型ベンチャー企業の研究マネジャー。新エネルギー開発プロジェクトを担当する一方で、経済や環境技術関係のコラム執筆も行なう
【T】